
ABOUTCYBER VALUEとは
『CYBER VALUE』とは株式会社ロードマップが提供する、
風評被害トラブル発生時の企業イメージ回復、ブランドの価値維持のためのトータルソリューションです。
インターネット掲示板に企業の悪評が流される事例はこれまでもありましたが、近年はSNSの普及で、
より多くの人が気軽に企業やサービスに対する意見や不満を投稿するようになり、
それが発端で炎上が発生することもしばしばあります。
ネット炎上は一日3件以上発生するといわれます。
企業に対する悪評が多くの人の目に入れば、真偽に関わらず企業イメージや売上、信頼の低下につながりかねません。
このようなリスクから企業を守り、運営にのみ注力していただけるよう、私たちが全力でサポートいたします。
REASONCYBER VALUEが
選ばれる理由
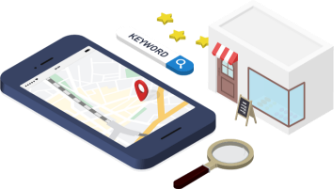
SEO対策の豊富な実績
株式会社ロードマップは2012年の創業以来、長きにわたりSEO対策をメ
イン事業としており、その実績は累計 200件以上。そのノウハウをもとに
したMEO対策や逆SEO、風評被害対策に関しても豊富な実績がありま
す。
長くSEO対策に携わり、つねに最新の情報を学び続けているからこそ、
いまの検索サイトに最適な手法でネガティブな情報が表示されないよう
に施策、ポジティブな情報を上位表示できます。
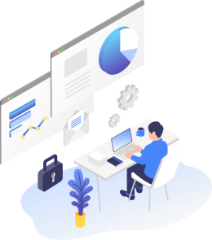
事態収束から回復まで
ワンストップ
株式会社ロードマップには、SEO対策やMEO対策などWebマーケティン
グの幅広いノウハウをもつディレクター、高度な知識と技術が必要なフ
ォレンジック対応・保守管理の可能なセキュリティエンジニアが在籍し
ており、すべて自社で対応できます。
そのため下請けに丸投げせず、お客さまの情報伝達漏れや漏えいといっ
たリスクも削減。よりリーズナブルな料金でサービスの提供を実現しま
した。また、お客さまも複数の業者に依頼する手間が必要ありません。

弁護士との連携による
幅広いサービス
インターネット掲示板やSNSにおける誹謗中傷などの投稿は、運営に削
除依頼を要請できます。しかし「規約違反にあたらない」などの理由で
対応されないケースが非常に多いです。
削除依頼は通常、当事者か弁護士の要請のみ受け付けています。弁護士
であれば仮処分の申し立てにより法的に削除依頼の要請ができるほか、
発信者情報の開示請求により投稿者の個人情報を特定、損害賠償請求も
可能です。

セキュリティ面のリスクも解決
株式会社ロードマップは大手、官公庁サイトを含む脆弱性診断、サイバ
ー攻撃からの復旧であるフォレンジック調査・対応の実績も累計400件以
上あります。
風評被害対策サービスを提供する企業はほかにもありますが、セキュリ
ティ面を含めトータルに企業のブランド維持、リスク回避をおこなえる
企業はありません。
こんなお悩みありませんか?

検索サイトで自社の評判を下げるようなキーワードが出てくる

自社にどのような炎上・風評被害の潜在リスクがあるか整理できていない
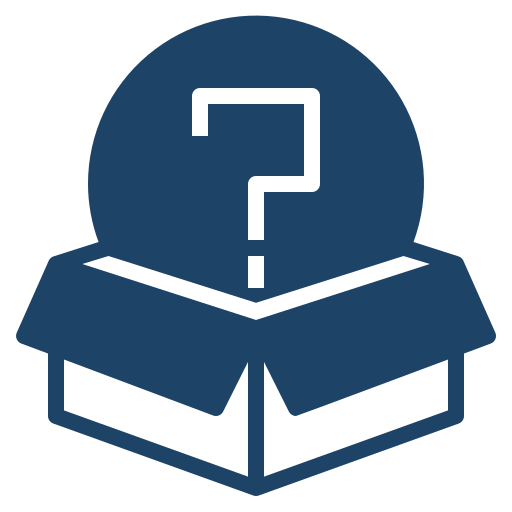
セキュリティ専門家による定期チェックを実施しておらず、課題や必要予算が見えていない
SERVICEサービス内容
企業イメージの
回復・維持を総合サポート

問題の解決
企業イメージに大きく関わる、つぎのような問題をスピード解決いたします。
検索サイトのサジェストにネガティブなキーワードが出るようになってしまった
サジェスト削除(Yahoo!・Google・Bing)
逆SEO
インターネット掲示板やSNSの投稿などで風評被害を受けた
弁護士連携による削除依頼・開示請求
サイバー攻撃を受けてサーバーがダウンした、サイト改ざんを受けてしまった
フォレンジック調査+対応

原因の究明・イメージ回復
風評被害やトラブル発生の原因となったのはなにか、どこが炎上の発生源かを調査し、 イメージ回復のためにもっとも最適な施策を検討、実施します。
企業やサイトの評判を底上げする施策
SEO対策(コンテンツマーケティング)
MEO対策
サジェスト最適化戦略支援
セキュリティ面のリスク調査
ホームページ健康診断

価値の維持
風評被害、サイバー攻撃被害を受けてしまった企業さまに対し、 つぎのような施策で価値の維持までトータルでサポートいたします。
セキュリティ運用
保守管理(月一度の検査ほか)
バックグラウンド調査
リスク対策を多角的にサポート

サイバーチェック
取引先や採用の応募者の素性を調査し、取引・採用前に素行に問題のない 人物であるか確認しておける、現代のネット信用調査サービスです。
反社チェック
ネット記事情報をもとに犯罪・不祥事・反社関連の情報を収集します。 採用・取引の最低限のリスク管理に。
ネットチェック
SNS・掲示板・ブログなどから会社・人に関する情報を収集。 企業体質・人物健全度のリスクを可視化します。
TRUST CHECK
匿名アカウント、ダークWebすべてのサイバー空間を網羅ネットの 深部まで調べあげる、究極のリスク対策支援ツールです。
COLUMNコラム
一覧を見る社員の不祥事がSNSで炎上…企業イメージ失墜を防ぐために今できること
社員による不適切な言動や不祥事が、SNSを通じて一瞬で拡散し、企業の信頼やブランド価値を揺るがす事例が後を絶ちません。たった一人の行動が、組織全体の評判や業績に深刻な影響を及ぼす時代です。
「社員の不祥事でSNSが炎上」「謝罪対応が後手に回り、信用を失った」といったニュースは他人事ではありません。特に、情報発信のスピードが加速する今、リスクへの備えと初動対応が経営における重要課題となっています。
本記事では、社員の不祥事が企業にもたらすダメージや炎上のメカニズム、対応の基本、そして再発防止のために必要な組織体制の整備について解説します。
あわせて、リスクを可視化し、予防と対策を支援する「CYBER VALUE」の活用方法もご紹介します。
社員による不祥事が企業にもたらす3つのダメージ
社員が関与した不祥事は、企業の信用や経営に大きな影響を及ぼします。ここでは主な3つのダメージを紹介します。
SNS炎上によるブランドイメージの悪化
近年、問題行動を起こした社員の映像や発言がSNSで拡散され、企業名が巻き込まれる事例が急増しています。悪質な場合には、炎上が長期化し「ブラック企業」というレッテルを貼られることもあります。
ある飲食チェーンではアルバイト従業員の迷惑動画が炎上し、店舗の一時閉鎖や売上大幅減に追い込まれました。
取引先や顧客からの信頼を失うリスク
不祥事が報道やSNSで拡散されると、取引先や顧客は「この企業と関わって大丈夫か?」と不安を抱きます。
取引停止や契約打ち切りといった直接的な影響だけでなく、入札除外など中長期的な取引機会の喪失にもつながる恐れがあります。
採用への悪影響をもたらす
不祥事をきっかけに社内に不信感が生まれると、社員のモチベーションが下がり、生産性や定着率が低下します。
また、SNSや口コミサイトで企業のネガティブ情報が共有されると、採用活動にも悪影響を及ぼします。
厚生労働省の調査によると、労働環境の悪化や企業イメージの低下は若手人材の応募離れに直結しているとの報告もあります。
SNSで不祥事が広がるメカニズムとは?
社員の不祥事がSNSで一気に広がるのは、現代のデジタル環境における情報流通の速さと、コンテンツの拡散構造に理由があります。
よくある炎上パターンとその特徴
炎上の典型的なパターンとしては、以下のようなものがあります。
- 社員による不適切なSNS投稿
- 店舗やオフィス内での迷惑行為を撮影した動画の投稿
- ハラスメントや差別発言の暴露やリーク
これらの投稿がX(旧Twitter)やTikTok、YouTubeなどに投稿されると、数時間以内に数万人規模に拡散することもあります。
ある物流企業の社員が配達物を故意に破損させる動画を投稿し、メディアにも取り上げられる事例もあります。
企業の謝罪と処分発表はあったものの、企業イメージは一時的に大きく毀損しました。
対応の遅れが事態を深刻化させる
初動対応が遅れると、次のような二次被害が発生します。
特にGoogle検索結果に表示される「企業名+ブラック」や「企業名+不祥事」といったサジェスト汚染は、長期的に採用や取引に影響を与えるため、早期の対策が求められます。
デジタル時代の炎上リスクに関する実務的な対応策については、内閣府が発行する「リスクコミュニケーションハンドブック」でも取り上げられており、企業の危機管理担当者にとって有用な資料です。
不祥事が発覚したときにやるべきこと
社員による不祥事が発覚した瞬間、企業がとるべき初動対応は、その後の炎上拡大を左右する重大な分岐点となります。
情報が公になる前でも、内部通報やSNSで兆候を察知した段階で、迅速かつ的確に動く体制が不可欠です。
丁寧に事実確認をする
まず重要なのは、憶測や感情ではなく、客観的な事実を整理することです。
- 関与者のヒアリング
- 被害者や第三者からの証言収集
- 関連する証拠(動画・書類・チャットログ等)の確保
調査は社内だけで完結させず、必要に応じて第三者機関や法務部門との連携も検討しましょう。
不十分な事実確認のまま社外へ発信してしまうと、後の訂正や謝罪がさらに企業の信用を下げる結果になりかねません。
社内外への周知を徹底する
社員や関係者に向けた社内周知は、早い段階で誠実に行うことが重要です。
「何が起きたか」「どう対応するか」「再発防止策は何か」を丁寧に説明することで、組織内の混乱を抑えられます。
一方で、社外への発信では次のような配慮が求められます。
- 不必要な個人情報の開示を避ける
- 記者会見や公式コメントでは、感情的な言い訳をせず事実を端的に伝える
- 被害者への配慮や謝罪の姿勢を忘れない
誠実なコミュニケーションを怠ると、炎上が長期化したり、メディアの報道が過熱する恐れがあります。
メディアに対して迅速に対応する
炎上を回避するには、初動72時間以内の対応が重要です。
SNSやWebサイトでの公式発信は、社内調査と並行して進めることが推奨されます。
特にX(旧Twitter)やInstagramなど即時性の高いメディアでは、企業アカウントからの情報発信が沈静化につながるケースもあります。
近年では、AIによるSNS監視ツールや、拡散状況をリアルタイムで把握できる可視化ダッシュボードを導入する企業も増えています。
株式会社ロードマップの「CYBER VALUE」では、WebやSNSの炎上兆候を早期に検知し、事実関係の確認とリスク対応の判断をサポートする体制を整えています。
▼ 詳しくはこちら
危機を最小限に抑えられる社内体制の整備
不祥事の発覚から終息まで、どれだけ早く正確に対応できるかは、企業の組織体制にかかっています。
個人任せではなく、複数部門が一体となって動ける仕組みがなければ、対応の遅れが生まれ、炎上の火種を広げかねません。
法務・人事・広報の連携で動く対応フロー
不祥事対応では、「調査」「判断」「社内外への発信」という3つの軸を同時並行で動かす必要があります。
- 法務部:事実認定と法的リスクの整理
- 人事部:処分内容の検討と労務対応
- 広報部:社外発信と風評被害の防止
この3部門の連携が取れていないと、社内外の混乱に拍車がかかり、炎上が長期化する要因になります。
危機対応マニュアルの整備や、模擬トレーニングを定期的に実施することで、役割分担と迅速な連携が可能になります。
処分判断と組織としての説明責任の考え方
社員への処分は、以下の観点をもとに、慎重かつ公平に判断すべきです。
- 事実確認の正確性
- 社内規定との整合性
- 社外の目線も踏まえた妥当性
処分後の説明責任も欠かせません。「なぜこの対応になったのか」「組織として何を学んだのか」「再発防止策は何か」といった点は、必要に応じて明示すべきです。
日常的なガバナンス強化と透明性の確保
リスク対応の基盤となるのは、日常的なガバナンスです。以下のような仕組みをあらかじめ整備しておきましょう。
土台があることで、突発的な不祥事にも冷静に対応できる組織風土が育まれます。
表面的な対策だけでなく、日々の組織運営のなかに「透明性」「誠実さ」「リスク感度」を根付かせることが重要です。
不祥事を未然に防ぐために見直したい「社内の空気」
社員の不祥事は、本人だけの問題ではなく、職場の風土やマネジメントのあり方が背景にあるケースも少なくありません。
日々の働き方や人間関係の中にある異変の兆しに気づける組織であるかどうかが、リスクの芽を摘めるかを左右します。
働きすぎや不満のサインに気づけていますか?
厚生労働省の調査でも、長時間労働や職場内の孤立が精神的不調や不祥事の引き金になることが指摘されています。以下のような状態は、要注意です。
- 有給休暇の取得率が極端に低い
- 日報や会話に愚痴が増えてきた
- 離職希望者が急増している
日常的なチェックインや面談の中で、こうしたサインをキャッチする仕組みを設けましょう。
(出典:令和5年版 労働経済白書)
社員の声を拾い、現場の変化に敏感になる仕組みづくり
声を拾うことと、それを放置しないことはセットです。
単なるフォーム入力やアンケートではなく、本音が集まる環境を整えることが求められます。
たとえば、Slackの発言を自動で分析したり、匿名相談チャットを常設したりすることで、社員が安心して声を出せる場ができます。
集まった声は「聞きっぱなし」にせず、部署横断で共有し、優先度を判断してアクションへとつなげましょう。
ハラスメント対策や教育制度のアップデートも視野に
コンプライアンス教育や管理職研修は、不祥事の予防に直結します。
eラーニングの導入や、AIによる感情分析を活用した研修も、より実効性のある施策として注目されています。
- ハラスメント相談窓口の整備
- 定期的な研修の実施
- エスカレーションルールの可視化
形式を整えるだけでなく、制度が「機能しているか」を定期的に見直すことが、不祥事を防ぐ企業体質を育てるうえで重要です。
CYBER VALUEは企業リスクを可視化する支援サービス
社員による不祥事を未然に防ぐには、組織内に潜むリスクの兆しをどれだけ早く察知できるかが重要です。
そのためには、表面化しにくい社内の不満や小さなトラブル、従業員の変化を日常的に把握できる仕組みが欠かせません。
社内の不満やトラブルの兆しを早期にキャッチ
多くの不祥事は、社員の不満やストレス、コミュニケーションの断絶といった日常の「ほころび」から始まります。
たとえば、匿名SNSでの不満投稿や、社内チャットでの言動に兆候が表れることもあります。
CYBER VALUEは、WebやSNS上での従業員による投稿や風評をモニタリングし、炎上の火種や内部告発リスクをいち早く発見します。
▼ 詳しくはこちら
行動傾向や職場リスクの見える化で予防策を強化
見過ごされがちな従業員の行動変化や、部門ごとのリスク傾向を数値で可視化できるのも、CYBER VALUEの強みです。
- 過重労働が続いていないか
- ハラスメントや孤立の兆候がないか
- 特定部門に退職希望者が集中していないか
こうした情報をデータで捉えることで、感覚に頼らないリスク管理が可能になります。
▼ 詳しくはこちら
従業員の健全な働き方と、企業の安心経営をサポート
健全な職場づくりには、問題が起きてからの対応だけでなく、「起きないための設計」が必要です。
CYBER VALUEは、風評被害や検索エンジンのサジェスト汚染といった企業イメージへの悪影響にも対応。万が一のときも速やかな信頼回復をサポートし、組織の持続的な成長を後押しします。
また、こうした外部リスク対策と並行して、従業員の心理的安全性を高める取り組みを支援することで、離職率の低下やエンゲージメント向上にもつながります。
▼ 詳しくはこちら
まとめ:予防と初動の両輪で社員の不祥事から企業を守る
SNSで情報が一気に拡散する現代では、社員一人の不祥事が企業全体の信用を揺るがすリスクをはらんでいます。炎上によるブランド毀損、取引停止、人材確保の難化など、その影響は経営にまで及びかねません。
重要なのは、問題が起きる前に「兆し」に気づき、初動で誤らない体制を整えることです。社員の声に耳を傾け、不満や異変を早期に察知すること。発覚後は事実を迅速に確認し、誠実でスピーディな情報発信を行うことが、炎上の長期化を防ぎます。
こうした一連の危機管理体制を支えるには、専門サービスの活用も有効です。
ロードマップ社の「CYBER VALUE」は、Web/SNS監視やサジェスト汚染対策、職場のリスク兆候の見える化を通じて、企業の安心経営を総合的にサポートします。
予防と対応の両輪が回ってこそ、企業は社会的信用を守り続けることができます。社員の一人ひとりが安心して働ける環境づくりが、信頼される企業への第一歩です。
顧客の期待を裏切る前に:風評被害・プライバシー侵害から企業を守る最新リスク対策
現代のデジタル社会において、企業の評判は極めて脆弱なものとなりました。
SNSや検索エンジンを通じて情報は瞬時に拡散し、たった一つの不適切な投稿や情報漏洩が、企業の信頼を根底から揺るがします。
企業経営におけるリスクは多様化・複雑化しており、中小企業庁も「経営に大きな影響を与えるリスクに対し重点的に対策を講じることが重要」と指摘しています。
(参照:「2024年版 中小企業白書」(中小企業庁))
「顧客の期待を裏切るリスク」は、もはや見過ごせない経営課題なのです。
この記事では、企業の信頼を損なう代表的なリスクとその最新対策を、公的機関のデータや実例を交えて解説します。
さらに、それらのリスク対策を支援するCYBER VALUEのサービスについてもご紹介します。
第1章 なぜ顧客の期待を裏切る事態が起きるのか?
1.1 顧客は「期待」を企業に預けている
顧客が商品やサービスを購入する時、その対価は金銭だけではありません。
品質、対応の誠実さ、そして情報管理体制まで、顧客は多くの「期待」を企業に預けています。
この期待を裏切る行為は、単なるクレームにとどまらず、信頼の喪失・ブランドの毀損へと直結します。
1.2 信頼を裏切る典型的なリスク
現代では、SNSの炎上やサイバー攻撃など、新たなリスクが顕在化しています。
顧客の信頼を裏切る典型的なリスクには、以下のようなものがあります。
これらのリスクは相互に関連し合い、気づいた時には手遅れになっているケースも少なくありません。
第2章 顧客の信頼を損なう5つのリスクとその実態
2.1 SNS炎上・Web上の批判の拡散
たった1件の投稿が数時間で拡散し、企業イメージを一気に崩壊させるのがSNS炎上の怖さです。
その火種は、企業アカウントの運用ミスだけでなく、元従業員や顧客による暴露、誤情報の拡散など多岐にわたります。
炎上は1日に3件以上発生するともいわれ、企業にとって日常的なリスクとなっています。
2.2 風評被害の拡大
事実無根の情報が、まとめサイトや口コミであたかも真実のように広がるのが風評被害です。
これは企業の売上やブランド価値に直接的なダメージを与えます。
福島第一原発事故後には、食品や観光業などで深刻な風評被害が発生し、消費者庁も継続的な実態調査を行っています。(参照:「風評被害に関する消費者意識の実態調査について」(消費者庁))
このような風評被害が、企業の経済活動に大きな影響を与えることは明らかです。
2.3 サジェスト汚染
Googleなどで企業名を検索した際、「ブラック」「裁判」といったネガティブな単語が関連候補(サジェスト)として表示される状態です。
この状態は、商品購入を検討する顧客や、就職活動中の学生、取引を検討する企業に深刻な不信感を与え、大きな機会損失につながります。
2.4 プライバシー侵害・内部不正
顧客の個人情報漏洩は、信用の失墜と法的な責任問題を引き起こします。
総務省への相談事例を見ても、名誉毀損やプライバシー侵害に関するものが全体の半数近くを占めており、個人のプライベートな情報がネット上に書き込まれるケースが多く報告されています。(参照:「令和5年版 情報通信白書」(総務省))
個人情報保護委員会が報告義務の対象とする漏えい事例には、外部からの不正アクセスだけでなく、「従業者が顧客の個人データを不正に持ち出して第三者に提供した場合」といった内部不正も含まれています。(参照:「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(個人情報保護委員会))
信頼している従業員による裏切りが、企業の存続を揺るがす事態を招くのです。
2.5 情報漏洩・セキュリティ事故
サイバー攻撃による情報漏洩も深刻なリスクです。
過去には、Webサーバーの初歩的な設定ミスにより、大手企業で数万件規模の個人情報が漏洩する事件も発生しています。(参照:「国民のための情報セキュリティサイト」(総務省))
個人情報保護委員会は、「個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等」が発生した場合、委員会への報告と本人への通知を義務付けています。
ひとたび大規模な情報漏洩が発生すれば、事業停止や多額の損害賠償につながる可能性があります。
第3章 対応が遅れた企業の共通点と失敗事例
リスクへの対応が遅れる企業には共通点があります。
その一つが「備えの欠如」です。
中小企業庁の調査によると、自然災害やサイバー攻撃といった不測の事態に備えるための「事業継続計画(BCP)」を策定している中小企業は約2割にとどまります。(参照:「2024年版 中小企業白書」(中小企業庁))
- リスク兆候をモニタリングしていなかった
- セキュリティ診断を定期的に実施していなかった
- ネガティブ情報に「沈黙」で対応した
- 検索結果・SNSの状況を客観的に把握していなかった
このように「気づいたときには手遅れ」という状況に陥る企業は後を絶ちません。
第4章 顧客の信頼を守るために企業が取るべき対策とは?
4.1 モニタリングと初動対応
Web・SNSを常時監視し、リスクの芽をいち早く検知することが不可欠です。
炎上の兆候を発見した際は、迅速な事実確認と誠実な情報発信が被害を最小限に食い止めます。
4.2 検索リスクへの対応
風評被害やサジェスト汚染に対しては、専門的な対策が有効です。
不正確な情報が掲載されたサイトの検索順位を低下させる「逆SEO対策」や、弁護士と連携した投稿削除依頼などが主な手法となります。
4.3 サイバーリスク対策と調査支援
情報漏洩を防ぐためには、「予防」と「事後対応」の両輪が重要です。
- 予防: 総務省も推奨するように、定期的なセキュリティ診断(脆弱性診断)でシステムの弱点を把握し、対策を講じます。(参照:「国民のための情報セキュリティサイト」(総務省))
- 事後対応: 万が一インシデントが発生した場合は、専門家による「フォレンジック調査」で侵入経路や被害範囲を特定し、再発防止につなげます。
第5章 CYBER VALUEが選ばれる理由
これらの複雑なリスクにワンストップで対応できるのが、株式会社ロードマップが提供する「CYBER VALUE」です。
ネット風評からサイバーリスクまで“全方位対応”
SNS炎上対策、風評被害対策(逆SEO・投稿削除)、サジェスト対策はもちろん、サイバー攻撃に備えるセキュリティ診断や、被害発生時のフォレンジック調査まで、デジタルリスクを包括的に支援します。
豊富な実績と専門家連携
SEO対策で累計200件以上、サイバーリスク対策で400件以上の豊富な実績を誇ります。
弁護士と連携し、削除請求や発信者情報開示請求といった法的なアプローチも迅速に行うことが可能です。
採用や取引のリスクも「見える化」
取引先や採用候補者に関するネット上の情報を調査する「バックグラウンド調査」や「反社チェック」サービスも提供しており、入社後や取引開始後のトラブルを未然に防ぎます。
リスクは可視化し、対策すれば防げます。
CYBER VALUEは、企業の信頼を守るための実践的なソリューションを提供します。
まとめ
企業の信頼は、築くのに時間がかかり、失うのは一瞬です。
顧客の期待を裏切らないために、炎上・風評・情報漏洩・サイバー攻撃への“備え”は、すべての企業にとって不可欠な経営課題です。CYBER VALUEは、リスクの可視化から対策実行まで、一貫して支援する体制を整えています。
顧客の信頼を守る第一歩は、リスクを正しく恐れることから始まります。
悪評の発信源はどこ?元従業員や競合によるSNS中傷が企業に及ぼす被害と法的対処の重要性
企業の評判や信頼を左右する情報発信の場として、SNSはますます重要な存在となっています。しかし、その利便性と拡散力の高さは、同時に根拠のない悪評や中傷が瞬く間に広がるリスクも含んでいるのです。
特に競合他社や不満を持つ元従業員が、事実無根の製品欠陥や企業の不正行為をSNS上で拡散するケースは増加傾向にあり、企業経営に大きなダメージをもたらしかねません。
本記事では、SNS上で広まる根拠なき中傷が企業に及ぼすリスクを解説し、このようなリスクに対して有効な対策とCYBER VALUEサービスの活用方法についてご紹介します。
企業の信頼を守り、風評被害を未然に防ぐための具体的な手法を理解し、万全の危機管理体制を整えましょう。
なぜSNSの根拠なき中傷が企業リスクになるのか?
SNSは現代のコミュニケーションツールとして欠かせない存在ですが、その情報拡散のスピードと影響力は、企業にとって大きなリスクにもなっています。
特に競合他社や不満を抱く元従業員などが、根拠のない製品の欠陥や不正行為に関する噂をSNS上で広めるケースが増えており、企業の評判が瞬時に悪化する恐れがあるのです。
こうした投稿の背景には、元従業員による「退職時の不満」や「待遇への不信感」、競合による「意図的な評判操作」など、感情的・戦略的な動機が潜んでいることも少なくありません。
匿名性の高いSNSでは、そのような暴露的投稿が急速に拡散しやすい傾向にあります。企業側が事実と異なる内容でも、深刻な被害を受けるリスクがあるのです。
このような悪評の拡散は、企業の信用失墜だけでなく、取引停止や株価下落、採用難など、経営に直結する深刻なダメージをもたらすことがあります。また、SNSの匿名性と拡散力により、噂が事実と誤解されやすく、被害が拡大しやすいのも特徴です。
総務省の報告によると、SNS利用者は国内で約8割を超え、情報の伝播速度は年々加速しています。
(参考:総務省PDF「令和5年通信利用動向調査の結果」)
このような背景から、SNSの根拠なき中傷は、企業リスクとして無視できない重要課題となっているのです。
SNS上の根拠なき中傷が引き起こす具体的なリスクとは?
SNSで拡散される根拠のない中傷や悪評は、企業にとって見過ごせない大きなリスクです。影響は一過性ではなく、長期にわたって企業の信頼を傷つけ、経営に深刻なダメージを与えます。
ここでは主に下記の5つのリスクについてわかりやすく解説しますので、ご確認ください。
風評被害(レピュテーションリスク)による経営ダメージ
根拠のない噂やデマが広まることで、企業のブランドイメージは静かに、しかし確実にむしばまれていきます。取引先からの信用低下や顧客離れ、株価の下落、さらには採用難にまでつながることもあり、経営基盤に大きな影響を及ぼすのです。
調査によれば、消費者の約半数が「ネットで悪い評判を見たら商品購入を避ける」と回答しており、風評が実際の購買行動に影響することが明らかとなっています。
(参考:東京電機大学「インターネットによるクチコミ現象の動向」)
SNS誹謗中傷・炎上リスクの特徴と拡大メカニズム
SNSの匿名性や拡散力によって、事実無根の中傷が瞬時に広がりやすいのが特徴です。炎上が発生すると感情的な投稿が増え、企業の信用が急速に失われるリスクが高まります。発信者の特定が難しいため、対応が後手に回ると被害は長期化・拡大しやすくなります。
検索サジェストの汚染がもたらす企業イメージ低下
検索エンジンのサジェスト機能に「企業名 不正」「商品名 欠陥」といったネガティブキーワードが表示されると、新規顧客や求職者に悪い印象を与えかねません。この「サジェスト汚染」は企業の評判を知らず知らずのうちに傷つけるため、専門的な対策が不可欠です。
一部では、競合他社が偽アカウントやボットを用いて、ネガティブワードを意図的に拡散する「攻撃的SEO」の事例も報告されており、検索サジェストやレビュー欄が不当に操作されるケースも見られます。こうした“評判操作”は発見が難しく、企業にとっては静かに信頼を奪われるリスクとなります。
情報セキュリティ面のリスクと信頼低下
根拠なき中傷だけでなく、内部情報の漏洩や不正アクセスも企業にとって大きなリスクです。漏洩した情報がSNSなどで拡散されると、企業の信頼は一気に崩れ、さらに風評被害が拡大します。
研究では、少量のネガティブ情報であっても、消費者心理に与える影響は大きく、売上に直結するというデータが示されているのです。
(参考:J‑STAGE論文「環境物品に対する負の風評の情報量格差」)
風評被害・中傷の実例と企業への影響
SNSやネット上での根拠なき噂や誹謗中傷は、実際に多くの企業に深刻な影響を及ぼしています。ここでは、具体的な事例をもとに被害の実態と企業が直面した課題を解説します。
匿名の噂や誹謗中傷がもたらした企業イメージの悪化
ある製造業の企業では、元従業員とされる匿名アカウントから製品の欠陥を指摘する投稿が広まりました。
実際には誤解や誤った情報であったにもかかわらず、SNSで瞬く間に拡散し、消費者の信頼を失う事態となったのです。この結果、同社は売上減少と取引先からの契約見直しを余儀なくされました。
被害拡大による取引停止や採用難のケース
飲食業界では、不満を持つ元従業員による不正行為の噂がSNSで広がり、求人応募者が激減した例もあります。さらに、取引先企業も安全面の懸念から契約を解除するなど、経営に直結する大きなダメージを受けています。
このような事例からもわかる通り、根拠のない噂や中傷がもたらす被害は企業の信用を大きく損なうだけでなく、具体的な経済的損失へとつながります。
だからこそ、早期発見と迅速な対応が不可欠です。
風評被害や誹謗中傷に対する効果的な対策とは?
SNS上での根拠なき噂や中傷がもたらす経営リスクに対して、企業は「早期発見」と「迅速な対応」が求められます。
ここでは、実効性の高い具体的な対策を4つの視点からご紹介します。
迅速なSNSモニタリングの重要性
SNSは投稿から数時間で数万人に届く情報拡散力を持ちます。そのため、被害を最小限に抑えるためには、投稿の初動での発見が鍵となるのです。
ネガティブなサジェストキーワードの管理と対策
「○○社 不祥事」「○○製品 欠陥」といった検索サジェストの汚染は、ブランドの第一印象を損ないます。
これは風評被害の“拡散装置”として見過ごせないリスクです。
発信源の特定と法的措置の流れ
根拠のない誹謗中傷や虚偽の噂が広まった際、発信者を特定し、証拠を保全した上での法的措置が必要になる場合があります。
発信者情報開示請求の円滑化を目的とした法改正も実施されており、企業も適切な証拠保全によって対応できる環境が整いつつあるのです。
(参考:総務省PDF「プロバイダ責任制限法 逐条解説」)
情報セキュリティ強化でリスクの予防を
SNS中傷の背景には、社内の情報漏洩や内部告発といったセキュリティ面の脆弱性も存在します。
退職者による悪意ある情報拡散を防ぐためにも、社内の情報管理体制を強化する必要があります。
CYBER VALUEが選ばれる理由と提供サービスのご紹介
企業の風評被害・誹謗中傷対策にはスピードと正確性、そして一貫した体制が不可欠です。
その中で「CYBER VALUE」が多くの企業から選ばれているのは、ワンストップ対応の強みと専門性にあります。
ここでは、CYBER VALUEが提供するサービスの内容と特長を4つの柱でご紹介します。
SNS・Webモニタリングで早期発見を実現
CYBER VALUEのWeb/SNSモニタリングは、X(旧Twitter)や2ちゃんねる系掲示板、口コミサイトなど、企業にとってリスクの高い媒体を24時間監視します。
単なるキーワード検出ではなく、「トーン」や「拡散傾向」も含めたリスク分析が可能で、
炎上や風評の芽を早期に察知し、初動対応につなげる体制を整えられます。
発信者特定・証拠保全まで対応するフォレンジック調査
根拠のない誹謗中傷や名誉毀損が発生した際、投稿の発信源を特定するには専門技術が必要です。
CYBER VALUEではフォレンジック調査・対策を通じて、投稿者のIPアドレスやアクセスログの調査、証拠の法的整合性の確保までサポート。
裁判資料として使えるレベルの証拠収集が可能で、法的措置への移行もスムーズに行えます。
サジェスト汚染対策でブランドイメージを守る
GoogleやYahoo!で企業名を検索した際に「○○社 不祥事」「○○製品 トラブル」といった
ネガティブなサジェスト(検索候補)が表示されることは、第一印象の損失に直結します。
CYBER VALUEのサジェスト汚染対策では、問題キーワードの監視から削除交渉、サジェスト表示制御までを一括対応。
検索結果における企業イメージのコントロールをサポートします。
セキュリティ診断・内部統制支援による予防体制の強化
悪評の中には、元従業員が持ち出した情報や社内の不祥事が端緒となるケースもあります。
そのため、そもそものセキュリティホールを塞ぐ「予防」の視点が欠かせません。
CYBER VALUEのセキュリティ診断・対策では、社内システムの脆弱性診断・アクセス権の見直し・監査支援などを実施。
情報漏洩・内部告発リスクを未然に防ぎ、炎上や風評被害の芽を摘み取ります。
まとめ|SNSの根拠なき中傷リスクを放置しないために
競合や元従業員による悪意ある書き込み――。
たったひとつの投稿から企業の信用が揺らぎ、売上や採用、株価にまで影響が及ぶ時代です。
しかも、それらの多くは「事実に基づかない噂」でありながら、SNSによって一気に拡散してしまいます。
今の時代、リスクは“火がついてから”ではなく、“火種の段階”で対処することが求められています。
- ネット上で会社名とともに根拠のない悪評が流れている
- SNSで発信された誤情報が広がりそうだ
- サジェストにネガティブなワードが表示されている
- 元従業員が内部情報を公開しそうで不安だ
このような課題をお持ちでしたら、CYBER VALUEが強力なパートナーになります。
風評被害の早期発見、サジェスト汚染対策、発信者の特定と法的対応、さらにはセキュリティ診断まで、予防から対処、そして再発防止までを一貫して支援。
企業の信頼は、何よりも大切な資産です。
その信頼を守るために、今すぐリスク対策を始めませんか?
Q&Aよくある質問
Q1サジェスト対策はどのくらいで効果が出ますか?
キーワードにもよりますが、早くて2日程度で効果が出ます。
ただし、表示させたくないサイトがSEO対策を実施している場合、対策が長期に及ぶおそれもあります。
Q2一度見えなくなったネガティブなサジェストやサイトが再浮上することはありますか?
再浮上の可能性はあります。
ただ、弊社ではご依頼のキーワードやサイトの動向を毎日チェックしており、
再浮上の前兆がみられた段階で対策を強化し、特定のサジェストやサイトが上位表示されることを防ぎます。
Q3風評被害対策により検索エンジンからペナルティを受ける可能性はありませんか?
弊社の風評被害対策は、検索エンジンのポリシーに則った手法で実施するため、ペナルティの心配はありません。
業者によっては違法な手段で対策をおこなう場合があるため、ご注意ください。
Q4掲示板やSNSのネガティブな投稿を削除依頼しても受理されないのですが、対応可能ですか?
対応可能です。
弁護士との連携により法的な削除要請が可能なほか、投稿者の特定や訴訟もおこなえます。
Q5依頼内容が漏れないか心配です。
秘密保持契約を締結したうえで、ご依頼に関する秘密を厳守いたします。
Q6他社に依頼していたのですが、乗り換えは可能ですか?
可能です。
ご依頼の際は他社さまとどのようなご契約、対応がなされたのかをすべてお伝えください。
Q7セキュリティ事故発生時にはすぐ対応していただけますか?
はい。緊急時には最短即日でフォレンジックを実施いたします。


