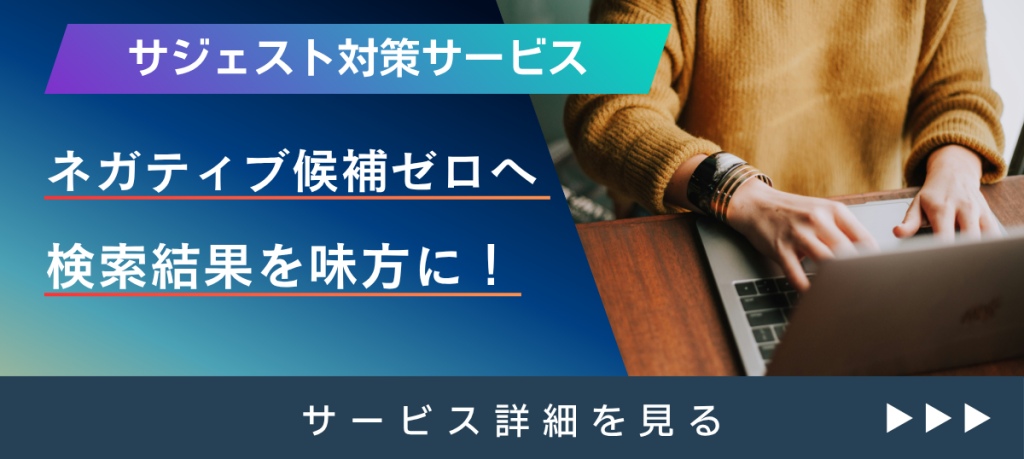ABOUTCYBER VALUEとは
『CYBER VALUE』とは株式会社ロードマップが提供する、
風評被害トラブル発生時の企業イメージ回復、ブランドの価値維持のためのトータルソリューションです。
インターネット掲示板に企業の悪評が流される事例はこれまでもありましたが、近年はSNSの普及で、
より多くの人が気軽に企業やサービスに対する意見や不満を投稿するようになり、
それが発端で炎上が発生することもしばしばあります。
ネット炎上は一日3件以上発生するといわれます。
企業に対する悪評が多くの人の目に入れば、真偽に関わらず企業イメージや売上、信頼の低下につながりかねません。
このようなリスクから企業を守り、運営にのみ注力していただけるよう、私たちが全力でサポートいたします。
REASONCYBER VALUEが
選ばれる理由
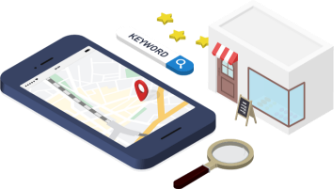
SEO対策の豊富な実績
株式会社ロードマップは2012年の創業以来、長きにわたりSEO対策をメ
イン事業としており、その実績は累計 200件以上。そのノウハウをもとに
したMEO対策や逆SEO、風評被害対策に関しても豊富な実績がありま
す。
長くSEO対策に携わり、つねに最新の情報を学び続けているからこそ、
いまの検索サイトに最適な手法でネガティブな情報が表示されないよう
に施策、ポジティブな情報を上位表示できます。
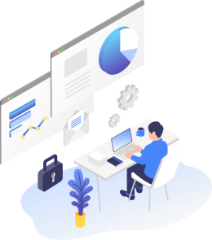
事態収束から回復まで
ワンストップ
株式会社ロードマップには、SEO対策やMEO対策などWebマーケティン
グの幅広いノウハウをもつディレクター、高度な知識と技術が必要なフ
ォレンジック対応・保守管理の可能なセキュリティエンジニアが在籍し
ており、すべて自社で対応できます。
そのため下請けに丸投げせず、お客さまの情報伝達漏れや漏えいといっ
たリスクも削減。よりリーズナブルな料金でサービスの提供を実現しま
した。また、お客さまも複数の業者に依頼する手間が必要ありません。

弁護士との連携による
幅広いサービス
インターネット掲示板やSNSにおける誹謗中傷などの投稿は、運営に削
除依頼を要請できます。しかし「規約違反にあたらない」などの理由で
対応されないケースが非常に多いです。
削除依頼は通常、当事者か弁護士の要請のみ受け付けています。弁護士
であれば仮処分の申し立てにより法的に削除依頼の要請ができるほか、
発信者情報の開示請求により投稿者の個人情報を特定、損害賠償請求も
可能です。

セキュリティ面のリスクも解決
株式会社ロードマップは大手、官公庁サイトを含む脆弱性診断、サイバ
ー攻撃からの復旧であるフォレンジック調査・対応の実績も累計400件以
上あります。
風評被害対策サービスを提供する企業はほかにもありますが、セキュリ
ティ面を含めトータルに企業のブランド維持、リスク回避をおこなえる
企業はありません。
こんなお悩みありませんか?

検索サイトで自社の評判を下げるようなキーワードが出てくる

自社にどのような炎上・風評被害の潜在リスクがあるか整理できていない
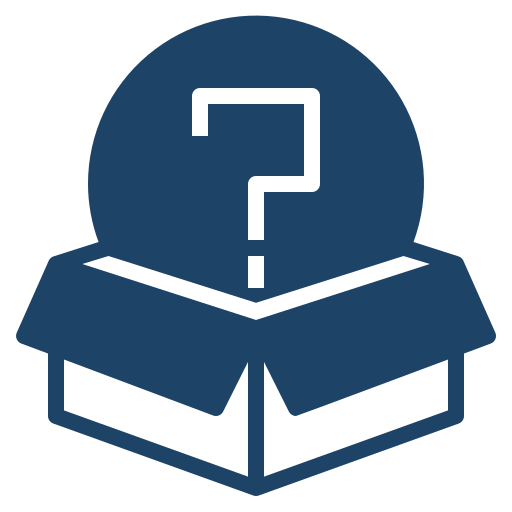
セキュリティ専門家による定期チェックを実施しておらず、課題や必要予算が見えていない
SERVICEサービス内容
企業イメージの
回復・維持を総合サポート

問題の解決
企業イメージに大きく関わる、つぎのような問題をスピード解決いたします。
検索サイトのサジェストにネガティブなキーワードが出るようになってしまった
サジェスト削除(Yahoo!・Google・Bing)
逆SEO
インターネット掲示板やSNSの投稿などで風評被害を受けた
弁護士連携による削除依頼・開示請求
サイバー攻撃を受けてサーバーがダウンした、サイト改ざんを受けてしまった
フォレンジック調査+対応

原因の究明・イメージ回復
風評被害やトラブル発生の原因となったのはなにか、どこが炎上の発生源かを調査し、 イメージ回復のためにもっとも最適な施策を検討、実施します。
企業やサイトの評判を底上げする施策
SEO対策(コンテンツマーケティング)
MEO対策
サジェスト最適化戦略支援
セキュリティ面のリスク調査
ホームページ健康診断

価値の維持
風評被害、サイバー攻撃被害を受けてしまった企業さまに対し、 つぎのような施策で価値の維持までトータルでサポートいたします。
セキュリティ運用
保守管理(月一度の検査ほか)
バックグラウンド調査
リスク対策を多角的にサポート

サイバーチェック
取引先や採用の応募者の素性を調査し、取引・採用前に素行に問題のない 人物であるか確認しておける、現代のネット信用調査サービスです。
反社チェック
ネット記事情報をもとに犯罪・不祥事・反社関連の情報を収集します。 採用・取引の最低限のリスク管理に。
ネットチェック
SNS・掲示板・ブログなどから会社・人に関する情報を収集。 企業体質・人物健全度のリスクを可視化します。
TRUST CHECK
匿名アカウント、ダークWebすべてのサイバー空間を網羅ネットの 深部まで調べあげる、究極のリスク対策支援ツールです。
COLUMNコラム
一覧を見るホットペッパービューティーの口コミは削除できない?削除可能なケースと申請方法
ホットペッパービューティーは、ヘアサロンやエステ、整体などの店舗検索や予約、ユーザーの口コミを閲覧できるサービスです。
しかし、利用者が非常に多いサービスであるため、ここで悪い口コミを投稿されてしまうと集客に悪影響を及ぼすおそれがあります。
今回は、ホットペッパービューティーに悪い口コミを投稿されてしまった場合に削除してもらうことはできるのか、運営による削除が可能なケースと申請する方法をご紹介します。
ホットペッパービューティーとは

ホットペッパービューティーとは、日本最大級のサロン検索・予約サイトです。現在掲載されているサロン数は合計8万件以上、ユーザー数は3,500万人にのぼります。
もとはフリーマガジンとして配布されていた「ホットペッパー」の美容に特化したサービスです。
ヘアサロンやネイルサロン、まつげエクステなどの店舗を探してクーポンで予約したり、ヘアスタイルを探したり、美容に関するさまざまなコンテンツを利用できます。
ユーザーは、日本全国に数多くある店舗からニーズにあう場所を掲載情報、口コミを参考に探せて、またクーポンを利用して安く簡単にネット予約もできる便利なサービスです。
ホットペッパービューティーの口コミ削除が難しい理由
ホットペッパービューティーの口コミは、削除してもらうのが難しいとされています。それは、すべての口コミは運営が審査をおこない、通過したものだけ掲載されるためです。
審査には2~10営業日かかり、基本的には運営側の定める「口コミ投稿の掟」に即した投稿であるかが確認されます。
審査の結果、内容に問題がないと判断されれば掲載、問題があれば非掲載、もしくは一部内容を修正して掲載されます。
このように1件ずつ審査されているため、掲載されたということは、運営側が問題のない内容であると判断されており、削除してもらうのは難しいでしょう。
また、サイト内に削除申請の専用フォームなども用意されていません。
ホットペッパービューティーに掲載されない口コミ内容
運営側の定めている「口コミ投稿の掟」によれば、以下のような内容は不適切な内容として非掲載にするとしています。
引用:口コミの掟 / HOT PEPPER Beauty
- 利用者自身の体験や、HOT PEPPER Beautyを利用しての利用経験に基づいていない内容
- 事実と反する内容・虚偽の内容
- 利用者と掲載施設にまつわる、当事者間の問題とリクルートが判断した内容(当事者間の個別事情による返金・サービスの再提供等の対応を含むが、これらに限らない)を投稿すること
- 投稿者のみならず、他の施設利用者や施設従業員等、個人のプライバシーにかかる事項(利用日・企業団体名・役職名・特徴風貌・行為行動など個人が識別できてしまうような情報を含むが、これらに限らない)
- 誹謗中傷、差別表現、わいせつ、卑猥な表現などの不適切な表現
- 他人を威圧・脅迫する旨が看取される内容
- 粗暴性、残虐性又は犯罪を誘発助長する内容
- 掲載施設や第三者に対する不当な利益誘導、信用毀損にあたる内容
- 以下に該当する表現(または近しい表現)
- 具体的な事象に基づかない記述
- 必要以上に感情的と判断される表現
- 投稿者の勘違いによる内容を含むもの
- 「利用しないほうがいい」「絶対に止めるべき」「最悪」「最低」等の独断的・断定的表現とリクルートが判断したもの
不適切な内容の口コミとして、具体的には次のような内容が挙げられます。
ホットペッパービューティーの口コミ削除が可能なケース
ホットペッパービューティーで口コミ削除が可能なケースとしては、基本的に「運営側の見落とし」と「投稿者の勘違い・間違い」の2パターンです。
具体的にどのようなケースなのかをご紹介いたします。
運営側の見落とし
前述のように、ホットペッパービューティーの口コミはすべて運営側によって審査がおこなわれ、問題のない内容であると判断された場合のみ掲載されます。
しかし、この審査は人力であるため、ごくまれに運営側の見落としによって不適切な内容の投稿が掲載されてしまうことも考えられます。
掲載されているものがあきらかに「口コミの掟」に反する内容である場合、運営側に問い合わせれば削除に応じる可能性が高いでしょう。
投稿者の勘違い・間違い
投稿者の勘違いや間違いとは、たとえば料金や予約時間を誤って認識しており、「予約したときより高かった」「予約時間から1時間待たされた」などと投稿するケースです。
この場合は店側に落ち度はなく、事実に反するため、投稿者が間違いを認めれば削除してもらえる可能性があるでしょう。
口コミ削除の申請方法
掲載された口コミが「口コミの掟」に反する内容と思われる場合など、削除を申請したい場合、お問い合わせフォームからおこないます。

フォームに氏名やメールアドレスなど必要事項を入力し、「お問い合わせ内容のカテゴリ」は「クチコミ・レビューについて」を選択し、「次へ」を押します。

お問い合わせ内容に「削除を希望する口コミを投稿したお客様の予約番号」、「削除したい口コミの投稿日時や内容」を記入します。
また、削除の理由としてホットペッパービューティーの利用規約、口コミの掟を引用し、どの部分に違反する内容か、また法律に反する部分があればそれを指摘して送信します。
- 削除を希望する口コミがどれか、分かるように伝える
- 該当の口コミが規約や法律に反する部分を明確に指摘する
- 「不快な思い」など感情論ではなく、事実を論理的に伝える
口コミを削除できないときは弁護士に相談する
ホットペッパービューティーの口コミは基本的に削除が難しく、申請しても対応してもらえないケースが多いと解説しました。
削除してもらえなかった場合でも、たとえば悪い口コミに対して謝罪やサービスを改善していく旨を返信することで、イメージアップにつなげることは可能です。
また、高評価の口コミが増えていけば、自然とよい口コミのほうが目につきやすくなり、悪い評価が押し下げられていくこともあります。
しかし、店舗のイメージのためにもどうしても削除したい場合、弁護士に相談することで法的な手段により削除を要請することも不可能ではありません。
ただし、弁護士に依頼する場合の相場として、着手金・報酬金ともに約5~10万円、裁判で「仮処分申し立て」をおこなう場合、着手金が約20万円、報酬金は約15万円となります。
弁護士に依頼するか迷っている場合、初回相談は無料という場合が多いためまず相談してから検討するのもよいでしょう。
サジェスト対策とは?必要性やメリット・デメリットを解説
Web集客には、SEOやコンテンツマーケティングなどさまざまな手法がありますが、このうちのひとつにサジェスト対策が挙げられます。
サジェスト対策は、企業や店舗の集客に有効なだけでなく、ブランディングや風評被害対策などにも効果的です。
今回は、サジェスト対策とは具体的にどのようなものか、その必要性や実施するメリット・デメリットについて解説します。
サジェスト対策のメリットとデメリット
サジェスト対策に取り組むメリットと、デメリットといえる部分はなにかご紹介いたします。
サジェスト対策のメリット
まず、サジェスト対策をおこなうメリットについてご紹介します。
ブランディング効果
社名や店名、サービス名などがサジェストで表示されると、ユーザーは「多くの人が検索している有名なもの」というイメージを抱きやすいです。
また、たとえば「(店名) おいしい」というように、あわせてポジティブなキーワードが表示されるだけでも、ユーザーが好印象を抱く可能性があります。
このように、サジェスト対策は単なる集客効果だけでなく、有名である、信頼できるといったイメージの向上、ブランディングにも効果をもたらします。
早く成果が出る
SEO対策やコンテンツマーケティングといったWeb集客は、上位表示を達成して効果が出てくるのに、数ヶ月単位でそれなりに時間がかかります。
その点、サジェスト対策はYahooの場合だと、施策開始から最短即日、多くの場合が1週間以内で表示されるため、早く成果を出すことができます。
費用対効果が高い
前述のように、サジェストは検索するユーザーの目につきやすく、また関連性の高いキーワードのため、クリック率が非常に高いです。
広告出稿の場合、出稿するキーワードによってはかなり高額になりますが、サジェスト対策であれば短期間で一気に大量のアクセスを稼ぐことができるため、費用対効果が高いといえるでしょう。
ペナルティのリスクが低い
SEO対策の場合、短期間で上位表示をさせようと、GoogleやYahoo!のポリシーに反する方法で施策をおこなうと、ペナルティを受けるリスクがあります。
ペナルティを受けてしまうとサイトを上位に上げるどころか、順位が大幅下落、または検索結果に表示されなくなるおそれもあります。
その点、サジェスト対策をおこなうことでのペナルティはなく、順位が下がってしまうといったリスクはありません。
サジェスト対策のデメリット
サジェスト対策には多くのメリットがありますが、「効果測定が困難である」という点がデメリットです。
通常、SEO対策や広告出稿などのWeb集客は、施策開始からのクリック率、コンバージョン率などの効果測定をおこない、施策の見直しや改善などをしていきます。
しかし、サジェスト対策を開始してからのサジェスト経由のアクセス数、集客や売上向上に効果があったのか、細かく計測することは困難です。
これにより、対策は本当に効果があったのか実感しにくい場合もあります。そこで、対策前と後でアクセス数やコンバージョン率を比較し、ある程度の数値を確認することをおすすめします。
サジェスト汚染の対策としても有効
サジェスト汚染は、実際の事故や事件、風評被害などで表示されてしまう場合があるほか、人為的にもできてしまいます。
たとえば、営業妨害の目的で「(社名) 詐欺」などのキーワードで大量に検索したり、SNSに投稿をくり返したりすれば、そのサジェストが表示されやすくなります。
サジェスト対策を実施していれば、ネガティブなキーワードを押し下げることにもつながるため、結果的にサジェスト汚染の対策もできるというメリットがあります。
集客だけでなく、企業や店舗のイメージをクリーンに保つためにも、サジェスト対策は有効な手段です。
Googleの口コミ投稿者を特定する方法!対応が難しい場合の相談先
Googleの口コミは日本を含めた世界各国、数多くのユーザーが閲覧しており、自社や店舗に関する悪い口コミを投稿されると、集客や売上に影響を及ぼしかねません。
このような場合に、口コミの投稿者を特定すれば、本人に直接投稿の削除を請求したり、風評被害の投稿であれば訴訟を起こしたりすることもできます。
今回は、Googleの口コミ投稿者を特定する方法と対応が難しい場合の相談先について解説します。
Googleの口コミ投稿者を特定する方法
Googleの口コミ投稿者を特定するには、まずGoogleにIPアドレスの情報開示を請求し、さらにプロバイダに契約者情報の開示を請求するという2ステップが必要です。
それぞれどのようにおこなうのか、解説します。
Step1. Googleへの情報開示請求
まず、サービスの提供元であるアメリカのGoogle本社に、投稿者のIPアドレスの情報開示請求をおこないます。請求が受理されればIPアドレスを情報開示してもらえます。
しかし、Googleも個人情報の守秘義務があるため、任意で開示に応じる可能性は低いです。請求を拒否された場合、裁判所の仮処分による開示請求が必要になります。
IPアドレスとは、パソコンやスマホなどインターネットに接続する端末に割り当てられる個別番号です。これにより、どのインターネットプロバイダを利用して投稿されたかが分かります。
IPアドレスだけでは本人の特定までできないため、つづいてプロバイダ側にそのアドレスを利用する契約者の情報開示を請求する必要があります。
なお、IPアドレスをはじめとする投稿者に関する情報の保存期間は、多くの場合が3ヶ月程度です。早めに開示請求しないと特定が困難になるため注意してください。
Step2. プロバイダへの情報開示請求
判明したIPアドレスは、「Whois情報検索」など無料でIPアドレスの情報を検索できるサービスを利用して、投稿者が利用していたプロバイダを調べます。
プロバイダが特定できたら、そのプロバイダに対象のIPアドレス情報を提示し、そのアドレスを利用する契約者の情報(氏名、住所、電話番号など)の開示を請求します。
プロバイダはこのような請求があると、口コミを投稿した契約者に対して、情報開示に応じてもよいか意見紹介書で確認をとります。
しかし、大抵は本人がこれを拒否するため、訴訟手続き(発信者情報開示請求訴訟)が必要になるケースが大半です。
訴訟となった場合、勝訴すれば情報開示を受けられますが、契約者情報の調査に時間がかかるようであれば、ログ情報が消去されないよう発信者情報消去禁止の仮処分を申し立てるケースもあります。
アメリカのディスカバリー制度の利用
Googleに対しては「ディスカバリー制度」の利用が可能です。ディスカバリー制度とは、裁判所を通じて相手の有する情報や証拠の開示を求める、アメリカ独自の証拠収集手続きです。
Google本社のあるカリフォルニア州の裁判所で手続きをおこない、投稿者の情報開示を請求します。
ディスカバリー制度は日本からでも利用でき、日本の弁護士に「口コミが違法である」という旨の書類作成と、アメリカの弁護士への送付を依頼してください。
この制度を利用しない場合は、上記のように2ステップの開示請求が必要で、本人の特定には約6〜8ヶ月と長期に及ぶ場合があります。
しかし、ディスカバリー制度ではGoogle本社に対する1回の開示請求で本人が特定できるため、約1〜2ヶ月と比較的早期に問題を解決できます。
Googleが禁止・制限している口コミ
Googleでは「マップユーザーの投稿に関するポリシー」を定めており、このポリシーでは以下の内容を「禁止および制限されているコンテンツ」として削除の対象にしています。
- スパムと虚偽のコンテンツ
- 実体験に基づかない内容の投稿、報酬や無料でサービスや商品の提供を受けるサクラ投稿やそれを促す行為も、スパムや虚偽コンテンツとして禁止されています。
- 関連性のないコンテンツ
- 企業や店舗の口コミとは関係のない、別店舗の口コミや嫌がらせ、個人的な主張などを投稿した場合はこれにあたります。
- 危険なコンテンツおよび中傷的なコンテンツ
- 店員や店舗に危害を加えるといった、攻撃的な内容や差別的な内容は危険なコンテンツとみなされます。
- 不適切なコンテンツ・露骨な性的表現を含むコンテンツ
- 侮辱などの不適切な表現やわいせつな表現、画像などを含むコンテンツもポリシー違反です。
- なりすまし
- 特定の個人や組織など権限のある者であると騙ったり、芸能人であるなど他者になりすまして投稿する行為も禁止されています。
- 利害に関する問題
- 自分の所属する企業や店舗への投稿や、競合他社が相手の評判を下げる目的で投稿したコンテンツがこれにあたります。
投稿された口コミがこのいずれかに当てはまる場合、Googleに通報をおこなうことで削除してもらえる可能性があります。
個人での対応が難しい場合の相談先
前述のように、Google本社への情報開示の請求は個人でもおこなえますが、請求に応じてもらえる可能性は低いといわれています。
そのため、個人での対応が難しい場合は、弁護士や風評被害に関する専門業者といった専門家に相談するのが確実かつスピーディです。
弁護士に相談する
弁護士は法律の専門家であるため、情報開示の請求に関しても法的に説得力のある理由を提示して申請してもらえるほか、裁判所の仮処分により確実に開示請求が可能です。
また、弁護士であればディスカバリー制度での情報開示申請も利用できるため、この方法であればさらに早期に問題が解決できるでしょう。
ただし、弁護士によってITの知識に明るくない場合もあるため、実際に話を聞いてGoogleの口コミについて知識があるか、対応事例があるか確認することをおすすめします。
専門業者に相談する
Googleの口コミをはじめ、インターネット上で風評被害を受けた場合の対処を代行する、風評対策の専門業者というものもあります。
専門業者に相談すれば、悪い口コミに対するフォローやイメージアップなどのノウハウがあり、弁護士に依頼するよりもリーズナブルに問題を解決できる可能性があります。
ただし、口コミの削除依頼を代行したり、投稿者を特定したりはできないため、弁護士を利用するのはハードルが高いという場合に適しています。
まとめ
Googleの口コミ投稿者を特定するには、次のような方法があると解説いたしました。
- GoogleにIPアドレスの開示請求→プロバイダに契約者の情報開示を請求
- 弁護士経由でディスカバリー制度を利用し、Google本社に開示請求
前述のように、個人で請求することもできますが、請求に応じてもらえる可能性は低く、また6~8ヶ月と解決に時間がかかってしまいがちです。
投稿者の情報を確実に開示してもらいたい、早期に解決したい場合は、ディスカバリー制度の利用や専門業者への依頼をおこなったほうがよいでしょう。
Q&Aよくある質問
Q1サジェスト対策はどのくらいで効果が出ますか?
キーワードにもよりますが、早くて2日程度で効果が出ます。
ただし、表示させたくないサイトがSEO対策を実施している場合、対策が長期に及ぶおそれもあります。
Q2一度見えなくなったネガティブなサジェストやサイトが再浮上することはありますか?
再浮上の可能性はあります。
ただ、弊社ではご依頼のキーワードやサイトの動向を毎日チェックしており、
再浮上の前兆がみられた段階で対策を強化し、特定のサジェストやサイトが上位表示されることを防ぎます。
Q3風評被害対策により検索エンジンからペナルティを受ける可能性はありませんか?
弊社の風評被害対策は、検索エンジンのポリシーに則った手法で実施するため、ペナルティの心配はありません。
業者によっては違法な手段で対策をおこなう場合があるため、ご注意ください。
Q4掲示板やSNSのネガティブな投稿を削除依頼しても受理されないのですが、対応可能ですか?
対応可能です。
弁護士との連携により法的な削除要請が可能なほか、投稿者の特定や訴訟もおこなえます。
Q5依頼内容が漏れないか心配です。
秘密保持契約を締結したうえで、ご依頼に関する秘密を厳守いたします。
Q6他社に依頼していたのですが、乗り換えは可能ですか?
可能です。
ご依頼の際は他社さまとどのようなご契約、対応がなされたのかをすべてお伝えください。
Q7セキュリティ事故発生時にはすぐ対応していただけますか?
はい。緊急時には最短即日でフォレンジックを実施いたします。