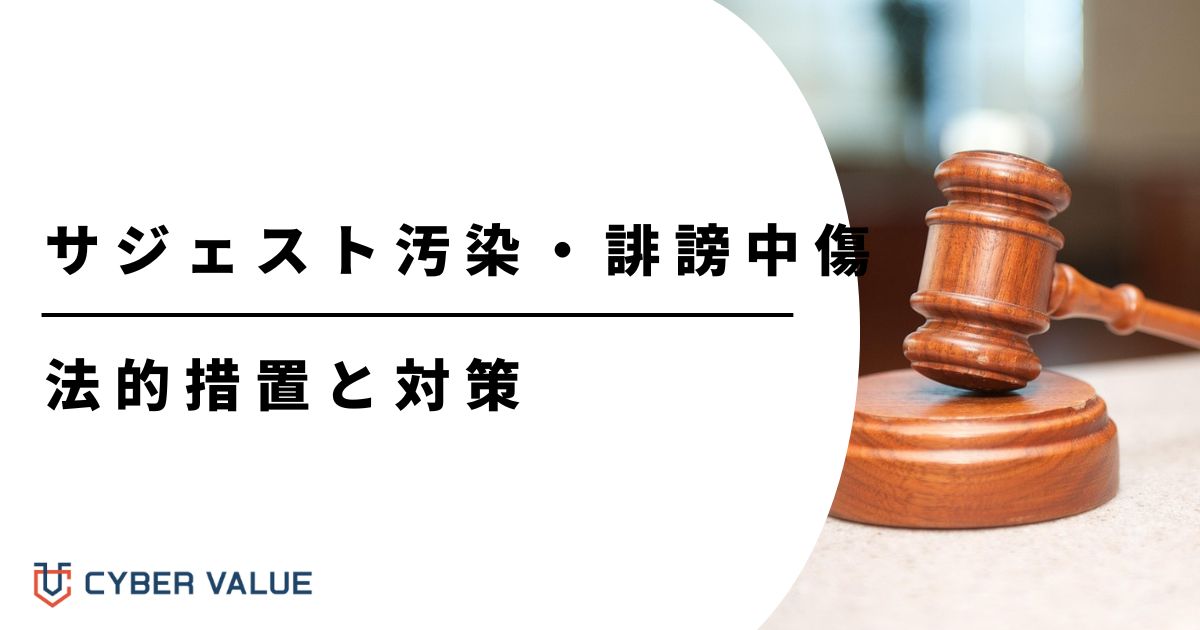「うちの会社が…?」サジェスト汚染・誹謗中傷が引き起こす法的措置と今すぐできる対策
よって、一瞬にしてその価値を失う危険性を孕んでいます。
一度ネガティブな情報がインターネット上に拡散されると、それは検索エンジンやSNSを通じて誰もが容易にアクセスできる“公知の事実”として扱われ、企業の社会的信用を大きく損ないます。さらに、こうした事態は単なるイメージダウンにとどまらず、名誉毀損罪や信用毀損罪といった刑事罰、あるいは民事上の損害賠償請求といった法的措置に発展する事例も決して珍しくありません。
この記事では、「知らないうちに自社のブランドが傷つけられていた」という最悪の事態を未然に防ぐため、企業が直面する具体的なデジタルリスクとその法的問題を深掘りします。そして、今すぐ着手できる実践的な対策とともに、デジタルリスク対策の専門集団であるCYBER VALUEが提供する包括的な支援策について、詳細にご紹介します。
第1章 公知化する企業リスクとその法的意味合い
1.1 サジェスト汚染・SNS炎上の深刻な実態
企業が直面する評判リスクの中でも、特に警戒すべきが「サジェスト汚染」と「SNSでの炎上」です。
サジェスト汚染とは、Googleなどの検索エンジンで企業名を入力した際に、検索候補(サジェスト)として「〇〇株式会社 ブラック」「〇〇商事 倒産」「〇〇クリニック 医療ミス」といった、ネガティブな印象を与えるキーワードが自動的に表示されてしまう現象を指します。これは、多くのユーザーがその組み合わせで検索していることを反映した結果ですが、たとえ事実無根であっても、検索した第三者に対して強烈な先入観を与え、企業活動における深刻な障壁となります。
一方、SNSでの炎上は、たった一つの不適切な投稿や顧客からのクレームが、X(旧Twitter)やInstagramなどのプラットフォーム上で爆発的に拡散し、数時間のうちに収集のつかない事態へと発展する現象です。その火種は、従業員の不注意な投稿、サービスの不備、内部告発など多岐にわたりますが、一度炎上すると、事実関係の真偽にかかわらず、企業の社会的信用は大きく毀損されます。
1.2 「公知化」が引き起こす法的措置の具体的内容
ネット上に拡散された誹謗中傷やネガティブな情報が放置された場合、企業は深刻な法的リスクに直面します。主に問題となるのは、刑法上の「名誉毀損罪」「信用毀損罪」、そして民法上の「プライバシー侵害」です。
名誉毀損罪(刑法第230条)
これは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立する犯罪です。ポイントは、記載された内容が事実か嘘かに関わらず成立し得るという点です。「A社は過去に法令違反で行政指導を受けた」という内容が事実であっても、それを不特定多数が見られるネット上に書き込む行為は、企業の社会的評価を低下させるため、名誉毀損に該当する可能性があります。
信用毀損罪(刑法第233条)
こちらは、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損」した場合に成立します。名誉毀損罪と異なり、嘘の情報であることが成立要件です。「B社は倒産寸前だ」といった虚偽の情報を流布し、企業の経済的な支払い能力や製品・サービスの品質に対する信頼を傷つける行為がこれにあたります。サジェスト汚染が原因で取引が停止された場合などは、この罪が問われる可能性があります。
プライバシー侵害(民法709条:不法行為責任)
こちらは刑事罰ではなく、民事上の損害賠償責任を問うものです。「公開されたくない私生活上の事実」が本人の許可なく公開され、精神的苦痛を受けた場合に成立します。企業でいえば、未公開の内部情報や従業員の個人情報などがこれに該当し、漏洩させた相手に対して損害賠償を請求することが可能です。
これらの法的措置を取るためには、まず誹謗中傷を行った「発信者」を特定する必要があります。そのための手続きが発信者情報開示請求であり、プロバイダ責任制限法に基づいて行われます。この請求件数は年々増加しており、総務省のデータによれば、2022年度には約3,300件に上るなど、企業や個人がネット上の権利侵害に対して積極的に法的手段を講じる傾向が強まっています。
第2章 “情報拡散”から“法的トラブル”へ発展した事例シナリオ
ネット上の小さな火種が、いかにして企業の存続を揺るがす大きな法的トラブルへと発展するのか。ここでは、具体的なシナリオを通じてそのプロセスと二次被害の深刻さを解説します。
2.1 不祥事の炎上が「デジタルタトゥー」となり、経営を蝕む二次被害
ある地方の中堅建設会社で、一人の現場監督による下請け業者へのパワーハラスメントが、音声データと共に匿名でSNSに投稿されました。投稿は瞬く間に拡散し、「#〇〇建設ハラスメント」というハッシュタグと共に大手メディアもこの問題を取り上げ、大規模な炎上へと発展しました。
同社はすぐに謝罪声明を発表し、当該社員を懲戒解雇処分としましたが、問題はこれで終わりませんでした。
- サジェスト汚染による採用活動の停滞: Googleで社名を検索すると、サジェストに「ハラスメント」「ブラック」といった単語が表示されるようになりました。その結果、新卒採用の応募者数は前年の3分の1に激減し、内定を出した優秀な学生からも複数名辞退される事態となりました。
- 取引への悪影響: 炎上とサジェスト汚染を問題視した主要な取引先から、コンプライアンス体制の見直しを求められ、一部の新規契約が見送られました。金融機関からも融資条件の厳格化を示唆されるなど、事業運営に直接的な影響が出始めました。
- 株主からの追及: 上場企業ではなかったものの、出資者である地域の有力者たちから経営責任を厳しく追及され、経営陣の退任を求める声も上がりました。
一度ネットに刻まれた不祥事の情報は「デジタルタトゥー」として残り続け、鎮火したはずの炎上が、採用、取引、資金調達といった経営の根幹を、長期にわたって静かに蝕んでいくのです。
2.2 内部からの情報漏洩が、顧客と元従業員からのダブル訴訟に発展
あるITベンチャー企業で、待遇に不満を持っていた退職間近のエンジニアが、顧客管理システムの脆弱性を利用して数千件の顧客情報を不正に取得。その一部を匿名掲示板に暴露しました。
この「内部不正による情報漏洩」が公知となったことで、同社は二つの側面から法的措置を取られることになります。
- 顧客からの集団損害賠償請求: 情報を漏洩させられた顧客たちは、プライバシー侵害とセキュリティ管理の杜撰さを理由に、弁護団を結成。同社に対して民法709条の不法行為に基づく損害賠償を求める集団訴訟を提起しました。
- 元従業員との労務訴訟: 会社は情報漏洩を行った元エンジニアに対し、信用毀損と損害賠償を求めて提訴。しかし、元エンジニア側も「不当な労働環境が不正行為の原因だった」として、未払い残業代の支払いやパワーハラスメントに対する慰謝料を求める反訴を提起。事態は泥沼の労務訴訟へと発展しました。
この事例のように、内部の問題が外部に漏洩することで、顧客と元従業員という二つの方向から法的責任を追及される「ダブルパンチ」のリスクが存在します。企業規模の大小にかかわらず、内部統制の不備が外部の法的トラブルに直結する危険性は、すべての企業が認識すべきです。
第3章 なぜ“ネットの火種”は見過ごされてしまうのか?
多くの企業が、なぜネット上のリスクが深刻化するまで気づけないのでしょうか。そこには、特に中小企業が陥りやすい構造的な課題と、デジタル情報特有の性質が存在します。
3.1 「対岸の火事」と考える中小企業のモニタリング体制の不備
「炎上やサイバー攻撃なんて、有名な大企業の話だろう」という思い込みは、中小企業の経営者に根強く存在します。広報や法務の専門部署を持たない企業が多く、日々の業務に追われる中で、ネット上の評判を定常的に監視するリソースも意識も不足しがちです。
しかし、リスクの火種はX(旧Twitter)やニュースサイトのコメント欄だけにあるわけではありません。
- 匿名掲示板(5ちゃんねる等): 社員や元社員による内部情報の書き込みが最も多い場所の一つ。
- 転職口コミサイト: 企業の労働環境に関するリアル(時に不正確)な情報が蓄積されている。
- Q&Aサイト(Yahoo!知恵袋等): 製品やサービスに対する不満が、具体的な質問の形で投稿されている。
これらのプラットフォームは、一般的な検索では表面化しにくいため、企業が気づかないうちにネガティブな情報が大量に蓄積されているケースが多々あります。こうした“見えない場所”でくすぶる炎を放置している企業ほど、いざ火の手が上がった際の対応が遅れ、被害が深刻化するのです。
3.2 一度刻まれたデジタルタトゥーは自然には消えない
アナログの世界での噂話は時間と共に風化しますが、デジタル情報はそうはいきません。Googleなどの検索エンジンは、ユーザーにとって有益と判断した情報をインデックスし、半永久的に保存し続けます。サジェスト機能も、一度ネガティブなキーワードが定着すると、それが検索され続ける限り表示され続けます。
つまり、数年前に解決したはずの不祥事や、たった一度の炎上が、企業のブランドイメージを現在進行形で妨げ続けるという事態が発生するのです。これを自然に消えるのを待つのは、顔についた消えないインクを放置するようなものです。積極的な対策を講じない限り、デジタルタトゥーは企業の未来を縛り続ける足枷となります。
第4章 今すぐ始めたい!炎上・サジェスト汚染・情報漏洩の「予防」と「対策」
デジタルリスクは、もはや避けて通れない経営課題です。重要なのは、問題が発生してから慌てて対応するのではなく、日常的に「予防」し、万が一の際には迅速に「対策」できる体制を構築することです。ここでは、CYBER VALUEが提供する具体的なソリューションをご紹介します。
4.1 CYBER VALUEができること①:Web/SNSモニタリングによる「火種の早期発見」
すべての対策の第一歩は、リスクの兆候をいち早く察知することです。
Web/SNSモニタリングは、SNS、ブログ、匿名掲示板、ニュースサイトのコメント欄など、インターネット上の膨大な情報を24時間365日体制で監視し、事前に設定したキーワード(会社名、商品名、役員名など)に関連する投稿をリアルタイムで収集・分析するサービスです8。
- 早期発見: 「製品に欠陥がある」「従業員の態度が悪い」といったネガティブな書き込みや、炎上の兆候を発生初期の段階で検知します。
- 迅速な初動対応: 危険度が高い投稿が検知されると、即座にアラートで担当者に通知。これにより、事実確認や公式声明の発表といった初動対応の遅れを防ぎ、被害の拡大を最小限に抑えることが可能です。
- 客観的な状況把握: 自社がネット上でどのように語られているかを客観的なデータで把握し、経営判断の材料とすることができます。
4.2 CYBER VALUEができること②:サジェスト汚染・風評被害対策による「ブランドイメージの回復」
すでにネガティブな情報が拡散してしまっている場合には、専門的なアプローチによるイメージ回復が必要です。
サジェスト汚染対策では、まずネガティブなサジェストが表示される原因を調査します。その上で、ポジティブな情報を発信するなどして検索行動を健全な方向へ誘導する逆SEOの手法を用い、ネガティブなキーワードの表示順位を押し下げ、最終的に非表示にすることを目指します。
風評被害対策では、ネット上に拡散された事実無根の悪質な記事や投稿に対し、正当なプロセスに則ったアプローチを行います。サイト運営者への削除依頼はもちろん、それが受け入れられない場合には、提携する弁護士を通じて裁判所に削除を求める仮処分申し立てを行うなど、法的な手段も視野に入れた対応が可能です。
4.3 CYBER VALUEができること③:フォレンジック調査・セキュリティ対策による「証拠保全と再発防止」
情報漏洩や社内不正、サイバー攻撃といったインシデントが発生した際には、原因究明と証拠保全が極めて重要になります。
デジタル・フォレンジック調査とは、PCやサーバー、ネットワーク機器などに残されたデジタルデータを収集・分析し、不正アクセスの経路や情報漏洩の範囲、犯人の行動などを法的な証拠として明らかにする科学的な調査手法です。CYBER VALUEでは、この調査を通じて、法的措置の準備を整えるとともに、インシデントの根本原因を特定し、実効性のある再発防止策の構築までを支援します7。
また、インシデントを未然に防ぐ「予防」の観点から、セキュリティ診断(脆弱性診断)も提供しています。専門家が企業のWebサイトや社内ネットワークを擬似的に攻撃し、セキュリティ上の弱点(脆弱性)を洗い出します。これにより、潜在的なリスクを可視化し、攻撃を受ける前に対策を講じることが可能になります。
まとめ:企業の名誉と信頼を守るのは、初動対応と“情報の可視化”
炎上、サジェスト汚染、情報漏洩といった企業の信頼を根底から揺るがすデジタルリスクは、その多くが経営者の“見えない場所”で静かに進行しています。そして、それらの火種が「検索」や「SNS」を通じて、誰もがアクセスできる公知情報へと変わった瞬間、名誉毀損や信用毀損といった法的措置に発展するリスクは一気に高まります。
企業の名誉とブランド価値を守るために最も重要なのは、第一に「見えにくいリスクを可視化する」ための常時監視体制、そして第二に、万が一問題が発生した際に被害を最小限に食い止めるための「迅速な初動対応」です。
CYBER VALUEは、リスクの早期発見から、拡散された情報の削除、法的手続きの支援、さらにはインシデントの根本原因を究明するフォレンジック調査まで、企業が直面するあらゆるデジタルリスクに対して予防・対処・回復を一貫してサポートできる専門体制を整えています。