
ABOUTCYBER VALUEとは
『CYBER VALUE』とは株式会社ロードマップが提供する、
風評被害トラブル発生時の企業イメージ回復、ブランドの価値維持のためのトータルソリューションです。
インターネット掲示板に企業の悪評が流される事例はこれまでもありましたが、近年はSNSの普及で、
より多くの人が気軽に企業やサービスに対する意見や不満を投稿するようになり、
それが発端で炎上が発生することもしばしばあります。
ネット炎上は一日3件以上発生するといわれます。
企業に対する悪評が多くの人の目に入れば、真偽に関わらず企業イメージや売上、信頼の低下につながりかねません。
このようなリスクから企業を守り、運営にのみ注力していただけるよう、私たちが全力でサポートいたします。
REASONCYBER VALUEが
選ばれる理由
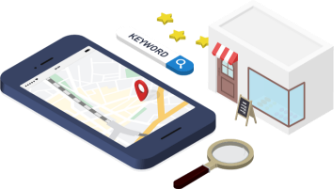
SEO対策の豊富な実績
株式会社ロードマップは2012年の創業以来、長きにわたりSEO対策をメ
イン事業としており、その実績は累計 200件以上。そのノウハウをもとに
したMEO対策や逆SEO、風評被害対策に関しても豊富な実績がありま
す。
長くSEO対策に携わり、つねに最新の情報を学び続けているからこそ、
いまの検索サイトに最適な手法でネガティブな情報が表示されないよう
に施策、ポジティブな情報を上位表示できます。
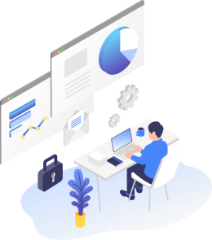
事態収束から回復まで
ワンストップ
株式会社ロードマップには、SEO対策やMEO対策などWebマーケティン
グの幅広いノウハウをもつディレクター、高度な知識と技術が必要なフ
ォレンジック対応・保守管理の可能なセキュリティエンジニアが在籍し
ており、すべて自社で対応できます。
そのため下請けに丸投げせず、お客さまの情報伝達漏れや漏えいといっ
たリスクも削減。よりリーズナブルな料金でサービスの提供を実現しま
した。また、お客さまも複数の業者に依頼する手間が必要ありません。

弁護士との連携による
幅広いサービス
インターネット掲示板やSNSにおける誹謗中傷などの投稿は、運営に削
除依頼を要請できます。しかし「規約違反にあたらない」などの理由で
対応されないケースが非常に多いです。
削除依頼は通常、当事者か弁護士の要請のみ受け付けています。弁護士
であれば仮処分の申し立てにより法的に削除依頼の要請ができるほか、
発信者情報の開示請求により投稿者の個人情報を特定、損害賠償請求も
可能です。

セキュリティ面のリスクも解決
株式会社ロードマップは大手、官公庁サイトを含む脆弱性診断、サイバ
ー攻撃からの復旧であるフォレンジック調査・対応の実績も累計400件以
上あります。
風評被害対策サービスを提供する企業はほかにもありますが、セキュリ
ティ面を含めトータルに企業のブランド維持、リスク回避をおこなえる
企業はありません。
こんなお悩みありませんか?

検索サイトで自社の評判を下げるようなキーワードが出てくる

自社にどのような炎上・風評被害の潜在リスクがあるか整理できていない
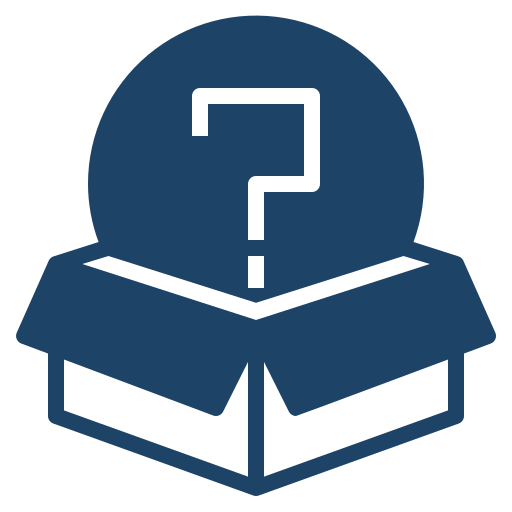
セキュリティ専門家による定期チェックを実施しておらず、課題や必要予算が見えていない
SERVICEサービス内容
企業イメージの
回復・維持を総合サポート

問題の解決
企業イメージに大きく関わる、つぎのような問題をスピード解決いたします。
検索サイトのサジェストにネガティブなキーワードが出るようになってしまった
サジェスト削除(Yahoo!・Google・Bing)
逆SEO
インターネット掲示板やSNSの投稿などで風評被害を受けた
弁護士連携による削除依頼・開示請求
サイバー攻撃を受けてサーバーがダウンした、サイト改ざんを受けてしまった
フォレンジック調査+対応

原因の究明・イメージ回復
風評被害やトラブル発生の原因となったのはなにか、どこが炎上の発生源かを調査し、 イメージ回復のためにもっとも最適な施策を検討、実施します。
企業やサイトの評判を底上げする施策
SEO対策(コンテンツマーケティング)
MEO対策
サジェスト最適化戦略支援
セキュリティ面のリスク調査
ホームページ健康診断

価値の維持
風評被害、サイバー攻撃被害を受けてしまった企業さまに対し、 つぎのような施策で価値の維持までトータルでサポートいたします。
セキュリティ運用
保守管理(月一度の検査ほか)
バックグラウンド調査
リスク対策を多角的にサポート

サイバーチェック
取引先や採用の応募者の素性を調査し、取引・採用前に素行に問題のない 人物であるか確認しておける、現代のネット信用調査サービスです。
反社チェック
ネット記事情報をもとに犯罪・不祥事・反社関連の情報を収集します。 採用・取引の最低限のリスク管理に。
ネットチェック
SNS・掲示板・ブログなどから会社・人に関する情報を収集。 企業体質・人物健全度のリスクを可視化します。
TRUST CHECK
匿名アカウント、ダークWebすべてのサイバー空間を網羅ネットの 深部まで調べあげる、究極のリスク対策支援ツールです。
COLUMNコラム
一覧を見るSNS炎上・ネガティブレビューが止まらない…品質問題が招く風評被害の実態と対策とは?
なぜ今、「品質」が悪いとSNS炎上や風評被害につながるのでしょうか?
日本ではSNS炎上が年間1,000件以上発生し、特に2020年は前年比+200件と急増しています 。
(出典:データで見る「ネット炎上」 炎上事案はどれだけ増えたか?メディア側の変化も影響)
品質不良によるクレームが拡散されると、ブランドのイメージや信頼が低下し、顧客離れに直結します。
また、製品不良が社会問題化すると、個人の投稿が所属企業まで巻き込むケースも増えており、「企業に迫るSNS炎上の実態と事例」がまさに当てはまります。
(参照:『売上げアップ』『採用力強化』したい方へ 口コミ・評判チェックの重要性)
実際にあった!SNS炎上のリアルな事例とその対応の良し悪し
事例① 迅速な対応の失敗と拡散
ある大手飲食品会社で異物混入が発覚しSNSで拡散されました。対応が遅れた結果、謝罪後も拡散が止まらず、2週間後もバズ継続状態に陥りました 。
事例② 初動ミスと拡散誘発
投稿削除や謝罪タイミングの誤りにより、炎上が“再燃”した例もあり、「対応が遅くなる」そして「再び炎上」が典型的なリスクとなっています。
風評被害・炎上が引き起こすリスクとは?
•ネガティブレビューが売上に直撃
誹謗中傷による信用失墜が、経済的損失につながる可能性を88%の企業が経験しており、その継続期間は平均約2.8か月になります。
(参照:【2020年下半期】SNS炎上最新企業事例まとめ 拡大の流れと対策)
(参照:Amazonレビューが売上に与える影響を徹底解説 売上との相関・年収別レビュー信用度など)
•顧客離れ・信頼低下
ブランド毀損は売上減・退職率の増加・株価暴落などに直結します。品質問題が表面化すると、ネガティブレビューにより顧客が離れ、一度失った信頼の回復には数年を要するケースもあります。
例えば、2021年の調査では、消費者の70%以上が「レビューが悪ければ購入しない」と回答しており、ブランド毀損による売上影響は看過できません(参照:日本消費者協会データ)。
さらに、従業員や株主にまで不安が広がり、離職率・株価低下といった波及的経営リスクも発生します。
•法的トラブル(PL法・製品事故)
品質不良が原因の事故が発生すると、メーカーは製造物責任法(PL法)に基づき多額の損害賠償責任を負う恐れがあります。
実際、過去国内では○○社が異物混入による健康被害をJPO(日本製造物責任機構)に訴えられ、数億円規模の支払いが命じられた事例があります。(参照:製造物責任(PL)法のQ&A(消費者庁))
このように法的対応を迫られる事案では、企業の信用喪失だけでなく、財務基盤への深刻な影響も懸念されます。
•情報漏洩との連動リスク
品質トラブルが広がる過程で、内部調整メールや顧客情報などが紛れて漏洩してしまう事例もあります。
SNSなどで内部文書が流出すれば、二次被害として風評被害がさらに拡大する恐れに晒されます。また、個人情報保護法や不正競争防止法違反に問われるリスクがあり、
実際、弊社では品質不良対応資料の誤報から、顧客情報の取り扱いに関する問い合わせが多数発生しています。(例:実際の食品異物混入事例(報道))
企業が今からできる!炎上・風評被害を防ぐ7つの実践策
1.SNS運用ルールの策定
公式アカウントは必ず「複数名でレビューし投稿する体制」を整備し、私用端末からの混同を防止する仕組みが必要です。
企業における誤爆投稿の多くは、「担当者が個人アカウントで誤送信」「緊急対応時に手順無視」などが原因で、可視化されたマニュアル運用で80%が防げます。(参照:総務省「ネット炎上と対策に関する調査報告」)
これらにより初動ミスによる炎上を未然に抑え、ブランド回復のコストを削減できます。
2.ソーシャルメディア研修の実施
従業員に対して定期的なSNSリスク研修を導入し、「炎上の兆候を察知する力」を醸成することが重要です。
総務省の報告によると、国内企業の約60%はSNS炎上経験があり、中でも「早期発見できなかった」が70%を占めるため、研修による意識改革は急務と言えるでしょう。(参照:総務省「ネット炎上と対策に関する調査報告」)
また、実例ベースのワークショップで学ぶことで、「何を見落としやすいか」「どのように対応すべきか」が体感レベルで理解できます。
3.モニタリング体制の強化
炎上兆候を逃さないために、SNS・レビュー・掲示板を横断的に監視できるツールの採用が有効です。
CYBER VALUEのWeb/SNSモニタリングでは、指定キーワードを含む投稿をリアルタイムで検知し、重大度に応じてアラート発信が可能です。
これにより「批判・クレーム投稿」を即時把握し、初動対応までの時間短縮に直結する運用が可能になります。
4.プライベート投稿誤操作の抑止
企業公式アカウントと私用アカウントの切替ミスを防ぐには、端末を物理的に分離したり、公式アカウントにアイコン・バッジ付与する対応が有効で「誤爆率」が改善される
要因になります。
こうした運用設計は、人的ミスから炎上を回避する“最後の砦”となります。
5.危機管理体制・マニュアル整備
品質トラブル対策の第一歩は、体制整備とマニュアルの整備から始まります。
「何を」「誰が」「どの順で」「どのように」伝えるかが定められたマニュアルは、平時の準備として非常に重要です。
CYBER VALUEでは、クライシス発生時対応フローの策定支援を行い、多くの導入企業で「初動5分以内」の対応体制を実現しています。
6.初動対応の明文化
「誰が」「どう判断して」「どう対応するか」を事前に定義しないと、初動対応の遅れが致命的になります。
例えば「投稿検知から2分以内に広報ステークホルダーへの報告」「5分以内に公式コメント案作成」など、定量的な目標が有効です。
こうした対応ルールを明文化し、社内標準化することで、再炎上抑止効果も期待できます。
7.フォローアップと再発防止策
炎上収束後には、必ず「再発原因の分析」「社内共有」「手順見直し」を実施します。
これにより、対応プロセスの改善がPDCAで循環し、次回以降のリスクレベルを継続的に下げることが可能です。
CYBER VALUE提供の定期セッションでは、各社のケースに基づいた継続改善支援も提供されています。
それでも炎上してしまったら?企業の正しい初動対応とは
初動は10分以内
事実確認と論調把握が重要です。投稿検知後、関係者への情報共有と初期判断は10分以内が理想。これ以上遅延すると炎上が拡大しやすくなります。
誤投稿の削除はタイミングがカギ
早すぎても批判対象になりえます。検知後即削除では逆に「隠ぺい」と疑われるため、謝罪コメントを添えてから削除、または一定時間掲示後対応が推奨されます。
レピュテーション回復
謝罪・再発防止策を明示して信頼回復を謀ります。 誠実な謝罪文と再発防止策を公開することで、信頼回復につながり、消費者から「対応誠実な企業」と評価されるケースもあります(参照:誹謗中傷対策センター)
モニタリング継続
「炎上の火種に早期に気づく」重要性があります。一度収束しても、その後に類似風評や再炎上が起こるケースがあるため、アフターフォローを含めた継続的監視が必要です。
CYBER VALUEが解決できること:風評・炎上・セキュリティリスクをワンストップで対策
現代の企業は、SNSやオンラインメディアを通じた否定的な情報の拡散リスクに常に晒されています。
CYBER VALUEはこうした多様なリスクに対し、総合的かつ先進的なソリューションを提供し、企業の信用失墜を防ぎ、早期の問題発見から対応、再発防止まで一気通貫で支援します。
Web/SNSモニタリングで早期発見とリアルタイム対応
CYBER VALUEの中心サービスであるWeb/SNSモニタリングは、膨大なネット情報から企業に関わるネガティブ投稿や批判的な書き込みを自動的に検知。炎上の火種を早期に察知し、迅速な対応を可能にします。
このモニタリングにより、SNSの投稿やニュース記事、口コミサイトまで幅広く監視。リスクが顕在化する前に情報を把握できるため、被害の拡大を防ぎ、適切な危機管理が実現します。
フォレンジック調査・対策で原因究明と証拠保全を支援
不祥事やハラスメント問題など、発生したトラブルの原因調査や証拠の収集を専門的にサポート。原因分析を通じて再発防止策を提案し、企業のコンプライアンス強化を後押しします。
調査結果は内部報告だけでなく、法的対応や対外説明の根拠としても活用可能であり、透明性の高い対応を実現します。
風評被害対策・サジェスト汚染対策で企業イメージを回復
風評被害対策では、ネット上に拡散した誤情報や悪質な口コミの抑制・訂正を行い、企業の評判を守ります。加えて、検索エンジンのサジェスト欄に表示されるネガティブキーワードをクリーンアップし、検索結果の印象改善を実現します。
これにより、取引先や消費者、求職者に対する企業イメージの回復を図り、長期的なブランド価値の維持を支援します。
迅速かつ的確なマスコミ対応支援で炎上の拡大を防止
CYBER VALUEは、報道直後の混乱を最小限に抑えるためのマスコミ対応支援も提供。状況を正確に把握した上で、適切なコミュニケーション戦略を策定し、炎上の拡大防止とブランド毀損リスクの軽減をサポートします。
トータルなリスクマネジメントで企業の安心を実現
これらのサービスを組み合わせることで、CYBER VALUEは単なるモニタリングツールに留まらず、発見から対応、再発防止まで一貫したリスクマネジメントを実現。企業の信頼を守り抜くパートナーとして、高い評価を得ています。
•Web/SNSモニタリングでリアルタイム監視📈
•セキュリティ診断・フォレンジック調査で炎上時の情報漏洩も対応
•導入実績1,000社以上のノウハウあり(安心感を訴求)
•相談体制充実:資料請求・お問い合わせリンク設置
まとめ
製品・サービスの品質対策は、リスクマネジメントの第一歩です。
製品やサービスの品質を見直し、炎上の火種を防ぎ、初動対応の準備が整った企業だけが、炎上しても回復できる時代です。
CYBER VALUEと一緒に、”品質品質だけじゃない、安心のSaaS体制”を整備しましょう。
内部犯行による情報漏洩が企業を破滅させる前に|技術的にできる再発防止策とは?
企業内部からの情報漏洩は、「偶発的なミス」ではなく「意図的な不祥事」です。
顧客情報や機密資料の外部持ち出しは法的制裁やブランド毀損へ直結します。
本記事では、技術+運用の両面から再発防止の具体策と導入事例、Cyber Valueによる支援内容を紹介します。
1. 内部不正がもたらす“企業破滅”のリスクとは?
某大手保険会社では、元社員がUSBで顧客データを持ち出し、数千件の個人情報が流出しました。 (参照:元社員、退職時の誓約守らず他社に顧客リスト979名分流出)
金融庁から行政処分を受け、株価は10%以上下落、取引停止の影響も出ました。
このように信頼を失うと回復に数年、数十億円単位のコストが必要になります。
2. なぜ漏洩は起きるか?── “不正のトライアングル”+組織の甘さ
IPAの内部不正調査によれば、「動機」「機会」「正当化」に加えて、スキルや組織の脆弱さも加わると不正が起こりやすくなります。
特にログ管理や監視が不足している環境では「見えない」ことが最大のリスクになります。
企業は不正構造を理解し、「不正予防型」の仕組みを整えることが不可欠です。
3. 漏洩発覚後に企業にふりかかるリスクとは?
このようなリスクが発生した場合、企業炎上の初動対応の遅れによるものとされています。 (参照:SNS炎上の対応マニュアル|企業ブランドを守るためには)
漏洩がニュースやSNSに拡散されると、株価の急落や顧客離れ、行政処分が連鎖的に発生します。
適切な初期対応ができなければ、謝罪や補償も信頼を回復できず、被害は拡大してしまいます。
4. 再発防止の第一歩=“可視化と証拠保全”
フォレンジック調査とは、電子証拠を適切に収集・分析し、漏洩の原因や経路を解明する技術です。
IPAでも、ログの詳細記録と証拠保全体制の整備が推奨されており、これが再発防止の土台となります。
適切な証拠の蓄積があれば、再発時の対応もスムーズに進められます。
5. 実例①:システム管理者による長期不正送金
大手証券では、委託先エンジニアが2年以上にわたり不正送金を実行していました。
監視ログが未整備だったため発覚が遅れ、数億円規模の被害に発展しました。
後日、フォレンジック調査で全容が明らかになりましたが、可視化の甘さが甚大な損害を招いた典型例です。
6. 実例②:通信子会社による顧客情報流出
某通信子会社で、元派遣社員が約900万件のテレマーケ情報を持ち出した事件。
ログ監視の欠如で発覚に10年以上を要し、ブランド責任と損害賠償問題が浮上しました。
委託先の管理不備を放置した企業責任の重さを示す事例です。
(参照:NTTビジネスソリューションズに派遣された元派遣社員によるお客さま情報の不正流出について)
7. 実例③:中小製造業におけるPCウイルス感染漏洩
IPA事例では、不正USB使用によりウイルスが感染し取引先にメールで拡散。
ウイルス対策ソフト未更新と持ち込み規制の欠如が原因で、数千万円の業務停止損失が発生しました。
小規模組織でも多層防御と管理体制がキーとなります。
(参照:USBメモリ経由のウイルス感染に注意呼びかけ – IPA)
8. 再発防止策まとめ:可視化+教育+運用体制
1. ログ分析:接続・操作履歴の詳細取得と異常検知
2. フォレンジック:証拠保全と不正経路の解明
3. 内部通報制度:通報を活用した早期発見
4. 定期教育:セキュリティ意識の継続的向上
これらを組み合わせることで、内部犯行に対して「見える・対処できる」体制が構築されます。
9. Cyber Valueで構築する“再発防止”体制
・フォレンジック調査:発覚時に即対応し、電子証拠を確保
・セキュリティ診断:システム・ログ・運用面の弱点を洗い出し改善
・Web/SNSモニタリング:漏えい情報や炎上兆候をリアルタイムで追跡
・風評被害・ネガティブレビュー対策:ブランド毀損への早期介入と回復支援
Cyber Valueは、単なる技術支援にとどまらず、相談体制や支援実績(1,000社以上)も含めた総合ソリューションを提供します。
10. 【まとめ】
内部犯行リスクに対抗するための鍵は「可視化」「即対応」「教育の仕組み化」です。
CYBER VALUEの支援を通じて、見える安全体制を今すぐ整備し、ブランドと信頼を守りましょう。
あなたの会社も標的に?口コミ・レビューによる風評被害と対策法
「この商品、本当に良いのかな?」「このお店、信頼できる?」 現代の消費者が購買を決定する際、その背中を押す最後のひと押しとなるのが、インターネット上の「口コミ」や「レビュー」です。Googleマップの星評価、ECサイトのカスタマーレビュー、グルメサイトの感想、そしてSNSでのリアルな評判。これらは、消費者にとって極めて信頼性の高い情報源であり、企業にとっては自社の製品やサービスの価値を伝えるための強力なマーケティング要素の一つとなっています。
しかし、その影響力の強さは、諸刃の剣でもあります。一度、事実と異なるネガティブな内容や、悪意に満ちた投稿が拡散されてしまえば、それは瞬く間に企業のブランドイメージを傷つけ、売上に深刻なダメージを与える無視できない経営リスクへと変貌します。たった一つの悪評が、長年かけて築き上げた信頼を一夜にして崩壊させることすらあるのです。
本記事では、この避けては通れないネット上の口コミ・レビューによる風評被害の実態を多角的に分析し、その脅威から企業の大切な評判と未来を守るための具体的な対策方法を、専門家の視点から徹底的に解説します。
1. ネット上の口コミ・レビューが企業にもたらす絶大な影響
1.1 企業活動の生命線を握る口コミの影響力
もはや、口コミやレビューを単なる「お客様の声」として軽視できる時代ではありません。総務省が公表した「令和4年版 情報通信白書」によれば、消費者の約8割が「商品・サービスの購入を検討する際に、インターネット上の口コミやレビューを参考にしている」と回答しています。(出典:総務省 情報通信白書)このデータは、口コミが消費者の購買行動に決定的な影響を与えているという紛れもない事実を示しています。
ポジティブな口コミは、広告費をかけずとも新規顧客を呼び込み、売上を押し上げる強力な追い風となります。「このレストランは雰囲気が最高だった」「この製品は期待以上の性能だった」といった具体的な高評価は、他のどんなマーケティング手法よりも雄弁に商品の魅力を伝えてくれます。
その一方で、ネガティブな口コミは、見込み顧客を容赦なく遠ざける分厚い壁となります。「接客態度が最悪だった」「商品がすぐに壊れた」といった厳しい評価を目にした消費者は、たとえその商品に興味があったとしても、購入をためらうか、あるいは競合他社の製品へと流れてしまうでしょう。たった一つの悪い口コミが、何十人、何百人もの潜在顧客を失わせる可能性があるのです。
1.2 ネガティブレビューが引き起こすレピュテーションリスク
ネガティブなレビューがもたらす脅威は、単なる売上の減少に留まりません。特に、事実に基づかない誹謗中傷や、感情的な批判、あるいは意図的に企業の評判を貶めようとする悪質な投稿が拡散された場合、それは「炎上」状態へと発展し、企業の社会的信用そのものを揺るがす深刻なレピュテーションリスク(評判リスク)となります。
SNSの拡散力は凄まじく、たった一つの投稿がインフルエンサーなどに取り上げられることで、数時間のうちに数十万、数百万の人々の目に触れるケースも珍しくありません。一度炎上してしまうと、企業は「顧客対応が悪い会社」「品質管理ができていない会社」といった不名誉なレッテルを貼られ、ブランドイメージは大きく毀損されます。このダメージは、採用活動の難化、取引先からの信用失墜、株価の下落など、事業のあらゆる側面に波及していくのです。
2. よくある口コミ・レビュー被害の深刻なパターン
口コミやレビューによる風評被害は、様々な形で企業を襲います。ここでは、特に頻繁に見られる3つの典型的な被害パターンを、具体的な事例と共に解説します。
2.1 実在する顧客による不満・クレーム投稿
最も一般的なのが、実際に商品やサービスを利用した顧客による、不満やクレームの投稿です。例えば、以下のようなケースが挙げられます。
- 飲食店でのケース: 「予約したのに30分も待たされた」「店員の接客態度が非常に悪く、不快な思いをした」といった投稿が、グルメサイトやGoogleマップに書き込まれる。
- ECサイトでのケース: 「届いた商品が写真と全く違った」「不良品だったのに、問い合わせても対応が遅い」といったレビューが、商品ページに掲載される。
- サービス業でのケース: 「説明された内容と実際のサービスが異なっていた」「解約手続きが非常に煩雑で、なかなか解約させてもらえない」といった不満が、SNSや口コミサイトで拡散される。
これらの投稿内容が事実であったとしても、顧客の一方的な視点から書かれているため、企業側の事情が全く考慮されず、文脈を無視した形で批判だけが独り歩きしてしまう危険性があります。企業側が誠実に対応しようとしている最中であっても、投稿された情報だけを見た第三者には「不誠実な会社」という印象を与えかねません。
2.2 競合他社や悪意ある第三者によるネガティブキャンペーン
企業の評判を意図的に貶めることを目的とした、悪質な投稿も後を絶ちません。これは、健全な市場競争を歪める許されざる行為です。
- 競合他社による妨害: 競合企業の評判を落とすために、あたかも一般の顧客になりすまして「あそこの製品はすぐに壊れる」「あの店は衛生管理がなっていない」といった虚偽の悪評を、複数の口コミサイトに執拗に投稿する。
- 個人的な恨みを持つ第三者による嫌がらせ: 企業や特定の従業員に対して個人的な恨みを持つ人物が、腹いせに事実無根の誹謗中傷を匿名で書き込む。
- 金銭目的の攻撃: 企業に金銭を要求する目的で、ネガティブな口コミを投稿し、「お金を払えば消してやる」と脅迫するような悪質なケースも存在します。
これらの投稿は、事実に基づかないため極めて悪質であり、放置すれば企業の評判に深刻かつ回復困難なダメージを与えます。
2.3 元従業員による告発・内部情報の漏洩
企業にとって特に深刻な脅威となるのが、退職した元従業員による内部告発や不満の投稿です。内部の事情を知る人物からの情報は、信憑性が高いと受け取られやすく、炎上につながる可能性が非常に高いからです。
- 労働環境への不満: 「月100時間を超えるサービス残業が常態化していた」「上司によるパワハラが横行していたが、会社は見て見ぬふりをしていた」といった労働環境に関する生々しい告発が、転職口コミサイトやSNSに投稿される。
- 社内の不正行為の暴露: 「会社ぐるみで顧客を騙すような営業が行われていた」「衛生管理基準が守られていない実態」など、コンプライアンス違反に関する情報がリークされる。
こうした内部からの告発は、「ブラック企業」というレッテルを貼られる直接的な原因となり、企業の社会的信用を根底から揺るがすだけでなく、行政からの調査や法的責任の追及に発展する可能性も秘めています。
3. 口コミ・レビューのモニタリング体制を整えよう
これらの多様なリスクから企業を守るための第一歩は、敵の姿を正確に知ること、つまり**「自社に関するネット上の投稿を常時監視(モニタリング)する体制」**を構築することです。
3.1 SNS・レビューサイトを定期的にチェックする重要性
問題が炎上し、メディアで報じられるような大事になってから対応を始めても、時すでに遅しです。被害を最小限に抑えるためには、ネガティブな投稿や炎上の兆候を可能な限り早い段階で発見し、迅速かつ適切な初動対応を行うことが絶対不可欠です。
そのためには、Googleマップ、各種グルメサイト、ECサイト、転職口コミサイト、そしてX(旧Twitter)やInstagramといった主要なSNSなどを定期的に巡回し、自社名や商品名、役員名などがどのように語られているかを常に把握しておく必要があります。この地道な監視活動こそが、リスク管理の基礎となるのです。
3.2 Web/SNSモニタリングツールの活用
しかし、インターネット上の膨大な情報を、人間の手だけで24時間365日監視し続けるのは現実的ではありません。そこで有効となるのが、専門的なWeb/SNSモニタリングツールの活用です。
株式会社ロードマップが提供する**【Web/SNSモニタリング】**(詳細はこちら)は、主要なSNS、匿名掲示板、レビューサイトなどをシステムが常時巡回監視し、あらかじめ設定したキーワード(例:「自社名+不満」「商品名+最悪」など)を含む投稿を検知すると、即座にアラートで通知するサービスです。
このツールを活用することで、危機の兆候をリアルタイムで察知し、対応が手遅れになる前に迅速なアクションを起こすことが可能になります。深夜や休日に発生した炎上の火種も見逃さず、企業の評判を守るための強力な「目」となるのです。
4. ネガティブ投稿が見つかったときの対応ステップ
モニタリングによってネガティブな投稿を発見した場合、その後の対応が企業の命運を分けます。パニックにならず、冷静かつ戦略的に行動することが重要です。
4.1 初動対応の重要性
ネガティブな投稿に対して、感情的に反論したり、あるいは「どうせ個人の感想だろう」と無視したりするのは、最も危険な対応です。感情的な反論はさらなる炎上を招き、無視は「企業として無責任だ」という新たな批判を生むだけです。
まず行うべきは、以下のステップです。
- 状況の把握: 投稿内容を正確に読み解き、いつ、どこで、誰が、何について不満を述べているのかを客観的に把握する。
- 事実確認: 投稿内容が事実に基づいているのか、社内で迅速に調査を行う。顧客からのクレームであれば、購買履歴や対応記録を確認する。
- 情報共有: 把握した内容を、あらかじめ定めておいた報告ルートに従い、速やかに関係部署(広報、法務、顧客対応など)および経営層に共有し、対応方針を決定する。
この初動の速さと的確さが、その後の被害の大きさを決定づけます。
4.2 削除依頼と法的対応の判断軸
対応方針を検討する上で重要なのが、「投稿の削除を求めるか」「法的な対応に踏み切るか」という判断です。
- プラットフォームへの削除申請: 口コミの内容が、明らかに事実無根の誹謗中傷であったり、個人情報を含んでいたり、あるいは各プラットフォーム(Googleマップ、食べログ、Amazonなど)の利用規約に違反している場合は、運営者に対して削除を申請することが可能です。
- 法的措置の検討: 投稿内容が悪質で、名誉毀損や信用毀損、業務妨害といった不法行為に該当する可能性がある場合は、弁護士に相談の上、投稿者の特定(発信者情報開示請求)や、損害賠償請求、刑事告訴といった法的措置を検討する必要があります。
これらの判断には、法的な知識と専門的なノウハウが求められます。
4.3 CYBER VALUEの【風評被害対策】による総合支援
CYBER VALUEが提供する**【風評被害対策】**(詳しくはこちら)は、こうした複雑な対応をワンストップで支援するサービスです。
専門のコンサルタントが、投稿内容の分析から、プラットフォームへの削除申請代行、提携弁護士と連携した法的対応のサポート、そして同様のリスクが再発しないための社内体制構築のアドバイスまで、一貫してサポートします。自社だけで抱え込まず、専門家の力を借りることが、問題を迅速かつ適切に解決するための最善の道です。
5. 検索被害(二次被害)にも要注意
口コミによる炎上が鎮火した後も、安心はできません。多くの場合、より根深く、長期的な二次被害が発生します。その代表例がサジェスト汚染です。
5.1 「企業名+やばい」などのサジェスト汚染
一度炎上が起こると、多くのネットユーザーが「〇〇社+炎上」「〇〇社+やばい」といったキーワードで検索するため、Googleなどの検索エンジンがこれらの組み合わせを「人気の検索ワード」として学習してしまいます。その結果、検索窓に社名を入力しただけで、ネガティブな言葉が検索候補(サジェスト)として表示される「サジェスト汚染」が発生します。
この状態は、企業の評判に継続的なダメージを与え、採用活動や新規取引の大きな障害となります。炎上の記憶が薄れた後も、この「デジタルタトゥー」だけが残り続け、企業の未来を蝕んでいくのです。
5.2 CYBER VALUEの【サジェスト汚染対策】でできること
CYBER VALUEの【サジェスト汚染対策】(詳しくはこちら)は、この深刻な二次被害に対応する専門サービスです。
専門家が検索エンジンのアルゴリズムを分析し、ネガティブなキーワードの表示順位を押し下げるための戦略的な対策(逆SEOなど)を実施します。これにより、検索結果の印象を改善し、汚染されてしまったブランドイメージの回復を強力にサポートします。
6. 被害が深刻化する前に取るべき対策とは?
これまで見てきたように、口コミ・レビューによる風評被害は、一度発生するとその対応に多大な労力とコストを要します。最も重要なのは、問題が発生する前の「予防」です。
6.1 日常的な情報監視体制の確立
すべての基本は、繰り返しになりますが、継続的なモニタリング体制を確立することです。社内に広報やマーケティング部門の担当者を置き、日常的に自社の評判をチェックする、あるいはCYBER VALUEのような信頼できる外部の専門業者と契約し、リスクの兆候を常に見守ることが不可欠です。
6.2 専門業者と連携したリスク対応の必要性
口コミ・レビューによる炎上は、予測不能なスピードと規模で広がります。その猛威に自社だけで立ち向かうのは困難を極めます。問題が深刻化する前に、迅速かつ効果的に対処するには、豊富な知識と経験を持つ専門家の支援が不可欠です。
CYBER VALUEでは、Web/SNSモニタリングによるリスクの早期発見、風評被害対策による発生後の迅速な鎮火、そしてサジェスト汚染対策による二次被害の回復まで、企業のレピュテーション(評判)をあらゆる角度から守るための包括的なソリューションを提供しています。
まとめ
- 現代において、ネット上の口コミ・レビューは、企業の売上やブランドイメージを左右する極めて重要な要素です。それは、強力なマーケティング資産であると同時に、深刻な風評リスクの火種にもなり得ます。
- 自社だけで対応するのが困難な場合は、専門家の力を借りることが賢明な判断です。CYBER VALUEは、ネット炎上や口コミリスクに対する包括的な対策を提供し、貴社の大切な信頼と未来を守るための最適なパートナーです。
Q&Aよくある質問
Q1サジェスト対策はどのくらいで効果が出ますか?
キーワードにもよりますが、早くて2日程度で効果が出ます。
ただし、表示させたくないサイトがSEO対策を実施している場合、対策が長期に及ぶおそれもあります。
Q2一度見えなくなったネガティブなサジェストやサイトが再浮上することはありますか?
再浮上の可能性はあります。
ただ、弊社ではご依頼のキーワードやサイトの動向を毎日チェックしており、
再浮上の前兆がみられた段階で対策を強化し、特定のサジェストやサイトが上位表示されることを防ぎます。
Q3風評被害対策により検索エンジンからペナルティを受ける可能性はありませんか?
弊社の風評被害対策は、検索エンジンのポリシーに則った手法で実施するため、ペナルティの心配はありません。
業者によっては違法な手段で対策をおこなう場合があるため、ご注意ください。
Q4掲示板やSNSのネガティブな投稿を削除依頼しても受理されないのですが、対応可能ですか?
対応可能です。
弁護士との連携により法的な削除要請が可能なほか、投稿者の特定や訴訟もおこなえます。
Q5依頼内容が漏れないか心配です。
秘密保持契約を締結したうえで、ご依頼に関する秘密を厳守いたします。
Q6他社に依頼していたのですが、乗り換えは可能ですか?
可能です。
ご依頼の際は他社さまとどのようなご契約、対応がなされたのかをすべてお伝えください。
Q7セキュリティ事故発生時にはすぐ対応していただけますか?
はい。緊急時には最短即日でフォレンジックを実施いたします。


