
ABOUTCYBER VALUEとは
『CYBER VALUE』とは株式会社ロードマップが提供する、
風評被害トラブル発生時の企業イメージ回復、ブランドの価値維持のためのトータルソリューションです。
インターネット掲示板に企業の悪評が流される事例はこれまでもありましたが、近年はSNSの普及で、
より多くの人が気軽に企業やサービスに対する意見や不満を投稿するようになり、
それが発端で炎上が発生することもしばしばあります。
ネット炎上は一日3件以上発生するといわれます。
企業に対する悪評が多くの人の目に入れば、真偽に関わらず企業イメージや売上、信頼の低下につながりかねません。
このようなリスクから企業を守り、運営にのみ注力していただけるよう、私たちが全力でサポートいたします。
REASONCYBER VALUEが
選ばれる理由
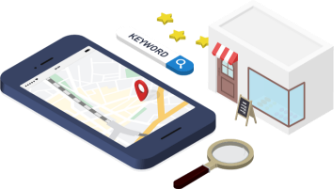
SEO対策の豊富な実績
株式会社ロードマップは2012年の創業以来、長きにわたりSEO対策をメ
イン事業としており、その実績は累計 200件以上。そのノウハウをもとに
したMEO対策や逆SEO、風評被害対策に関しても豊富な実績がありま
す。
長くSEO対策に携わり、つねに最新の情報を学び続けているからこそ、
いまの検索サイトに最適な手法でネガティブな情報が表示されないよう
に施策、ポジティブな情報を上位表示できます。
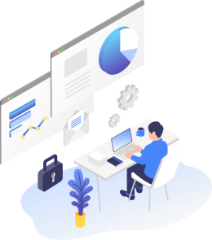
事態収束から回復まで
ワンストップ
株式会社ロードマップには、SEO対策やMEO対策などWebマーケティン
グの幅広いノウハウをもつディレクター、高度な知識と技術が必要なフ
ォレンジック対応・保守管理の可能なセキュリティエンジニアが在籍し
ており、すべて自社で対応できます。
そのため下請けに丸投げせず、お客さまの情報伝達漏れや漏えいといっ
たリスクも削減。よりリーズナブルな料金でサービスの提供を実現しま
した。また、お客さまも複数の業者に依頼する手間が必要ありません。

弁護士との連携による
幅広いサービス
インターネット掲示板やSNSにおける誹謗中傷などの投稿は、運営に削
除依頼を要請できます。しかし「規約違反にあたらない」などの理由で
対応されないケースが非常に多いです。
削除依頼は通常、当事者か弁護士の要請のみ受け付けています。弁護士
であれば仮処分の申し立てにより法的に削除依頼の要請ができるほか、
発信者情報の開示請求により投稿者の個人情報を特定、損害賠償請求も
可能です。

セキュリティ面のリスクも解決
株式会社ロードマップは大手、官公庁サイトを含む脆弱性診断、サイバ
ー攻撃からの復旧であるフォレンジック調査・対応の実績も累計400件以
上あります。
風評被害対策サービスを提供する企業はほかにもありますが、セキュリ
ティ面を含めトータルに企業のブランド維持、リスク回避をおこなえる
企業はありません。
こんなお悩みありませんか?

検索サイトで自社の評判を下げるようなキーワードが出てくる

自社にどのような炎上・風評被害の潜在リスクがあるか整理できていない
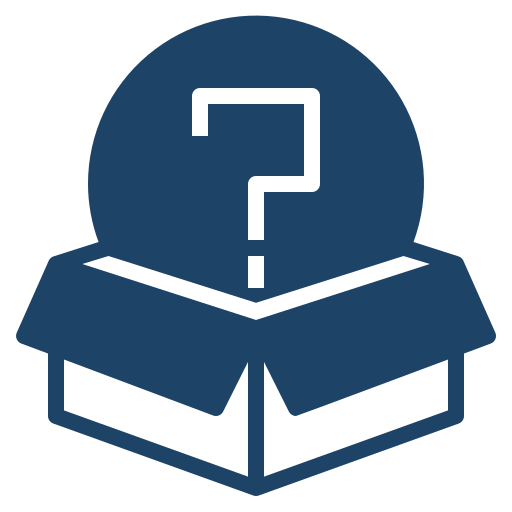
セキュリティ専門家による定期チェックを実施しておらず、課題や必要予算が見えていない
SERVICEサービス内容
企業イメージの
回復・維持を総合サポート

問題の解決
企業イメージに大きく関わる、つぎのような問題をスピード解決いたします。
検索サイトのサジェストにネガティブなキーワードが出るようになってしまった
サジェスト削除(Yahoo!・Google・Bing)
逆SEO
インターネット掲示板やSNSの投稿などで風評被害を受けた
弁護士連携による削除依頼・開示請求
サイバー攻撃を受けてサーバーがダウンした、サイト改ざんを受けてしまった
フォレンジック調査+対応

原因の究明・イメージ回復
風評被害やトラブル発生の原因となったのはなにか、どこが炎上の発生源かを調査し、 イメージ回復のためにもっとも最適な施策を検討、実施します。
企業やサイトの評判を底上げする施策
SEO対策(コンテンツマーケティング)
MEO対策
サジェスト最適化戦略支援
セキュリティ面のリスク調査
ホームページ健康診断

価値の維持
風評被害、サイバー攻撃被害を受けてしまった企業さまに対し、 つぎのような施策で価値の維持までトータルでサポートいたします。
セキュリティ運用
保守管理(月一度の検査ほか)
バックグラウンド調査
リスク対策を多角的にサポート

サイバーチェック
取引先や採用の応募者の素性を調査し、取引・採用前に素行に問題のない 人物であるか確認しておける、現代のネット信用調査サービスです。
反社チェック
ネット記事情報をもとに犯罪・不祥事・反社関連の情報を収集します。 採用・取引の最低限のリスク管理に。
ネットチェック
SNS・掲示板・ブログなどから会社・人に関する情報を収集。 企業体質・人物健全度のリスクを可視化します。
TRUST CHECK
匿名アカウント、ダークWebすべてのサイバー空間を網羅ネットの 深部まで調べあげる、究極のリスク対策支援ツールです。
COLUMNコラム
一覧を見るコンプライアンス違反が発覚したとき、企業がまずやるべき内部調査と証拠保全とは?
企業の“命運”は、コンプライアンス違反の発覚、「その瞬間」にかかっています。
不正や違反の放置は、ブランド毀損、採用・売上・株価に直結し、「隠蔽体質」と見なされれば評価は瞬時に失墜します。
本記事では、発覚時の初動対応・内部調査・証拠保全の具体手順と、ロードマップ社Cyber Valueの支援策を詳述します。
① コンプライアンス違反とは?企業を揺るがす重大リスク
コンプライアンス違反は以下の3タイプに分類されます。
- 法令違反:贈収賄、労働法違反など
- 社内規程違反:就業規則無視、情報セキュリティ不履行
- 倫理違反:セクハラ・パワハラ・横領など
特に従業員や役員による違反は、取締役会・株主・取引先への説明責任を負わせ、企業価値に甚大な影響をもたらします。
IPAによると、内部不正防止策を主管する責任部門が企業内に明確化されている比率は
約40%に留まり、多くの企業が体制整備途上にあります。
(参照:職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度厚生労働省委託事業))
また、違反者の約6割は“うっかり”行ったと回答しており、明文化された仕組みと教育の不足が顕在化しています。
(参照:「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査」)。
② 初動対応を誤ると“炎上リスク”と“調査妨害”が加速
初動対応が遅れると、SNS・報道では企業への「隠蔽」の印象が強く残ります。またこの様なマイナスのイメージは企業の信頼が急速に毀損され特に、以下の点は見逃せません。
- 対応フロー未整備:証拠収集が後手に回り、証拠の改ざん・消失リスク
- 情報漏洩:内部関係者やSNSを通じた未承認情報の拡散
- 調査着手の遅れ:当事者へのヒアリング開始前に状況把握が困難に
この初動段階において、Cyber Valueのセキュリティ診断・調査支援は体制構築、タイムリーな対応フロー設計・実行を支援します。
③ フォレンジック調査が違反対応の“第一歩”
フォレンジック調査は、ログ・メール・ファイル操作などのデジタル証拠の可視化・保全を目的とした専門手法です。
活用用途
- システムログ分析による不正アクセスの特定
- メール・チャットログ解析による不正の因果関係把握
- ファイル操作証跡の解析による改ざん・情報持ち出しの検証
IPAの「内部不正防止ガイドライン」は、テレワーク下でも即時に証拠を取得できる体制が必要だと明示しています。
(参照:組織における内部不正防止ガイドライン)
Cyber Valueのフォレンジック調査サービスでは、24時間以内の対応体制と証拠保全・分析サービスを提供し、迅速な調査開始が可能です。
④ 内部調査の進め方:社内調整と外部支援の併用が鉄則
本格的な内部調査では、社内対応と外部連携をバランスよく組み合わせることが重要です。
● 社内対応
1. 経営層による明確な調査方針の掲示
2. 通報窓口(ホットラインなど)の整備・管理
3. 関係者へのヒアリングと一次証拠の提示
● 外部連携
1.法務・労務・情報セキュリティの専門家による調査参加
2.客観性・公正性の担保
3.Cyber Valueは中立的第三者機関として証拠を保全し、法的手続きにも対応可能
これにより、「社内の調査では信頼できない」といった取引先・株主・規制当局の疑念を払拭できます。
⑤ 調査結果より先に“世論”が動く?風評リスクにも備えを
調査開始前に「会社名+違反」「ブラック企業」といった検索ワードが生み出され、サジェストが汚染されるのはよくあるパターン。
中小企業実態調査の報告では、約50%が「風評被害への懸念」を示しており、経営に直接響くリスクは明白であることが分かります。
(参照:令和3年度中⼩企業実態調査)
実例①:ペヤングの異物混入事件では「ペヤング ゴキブリ」のサジェストが発生
2015年にペヤング焼きそばからゴキブリが混入されていたことが報じられた。ブランド毀損の象徴に陥り、発売中止から再販売までに数か月を要し、対応の遅れがSNS炎上と業績に影響しました。
参考:([日本経済新聞]「ペヤング」事件に学ぶ SNS対策、初動が肝心)
実例②:大手企業「三菱電機」では、2021年に複数の不正検査問題が発覚
2021年に複数の不正検査があることが発覚し、報道直後に「三菱電機 ブラック」「不正 検査」といったネガティブサジェストが生成されました。
その後、就職人気ランキングも急落する事態に陥り、「隠蔽体質」との批判が殺到しました。
この件は調査よりも世論形成が先行し、株価・企業イメージに大きな影響を与えた。
(参照:三菱電機の品質不正はなぜ起こったのか)
Cyber Valueのサジェスト対策・風評モニタリングでは、ネガティブキーワードの即時検知と対処が可能で、炎上初期段階での拡散抑制に有効です。
⑥ 再発防止策は「教育×運用×システム」の3点セット
一度の違反を今後の教訓に変えるには、次の3つの取り組みが鍵となります。
1. 社員教育の定期化:ルール理解の徹底と意識の定着
2. 明文化と運用監査:ポリシー整備と実効性ある管理体制
3. システム監視の実装(ログ管理・EDR等):リアルタイム検知と技術的防御
IPAの調査でも、中小企業における情報資産管理体制は依然として整備不足であることが判明しています 。
Cyber Valueは「セキュリティ診断・内部通報制度の支援」で、再発抑止のための体制設計から運用定着まで一貫支援します。
まとめ:信頼回復には「技術と客観性」が不可欠
昨今において不祥事は隠せない時代になっています。初動対応の透明性と迅速性が企業命運を分けます。
1.証拠の可視化にはフォレンジック調査、世論対策にはモニタリングとサジェスト改善が不可欠です。
2.Cyber Valueは「内部調査」「証拠保全」「風評対策」をワンストップで提供する信頼のパートナーです。
従業員の不祥事が引き起こす顧客トラブルに備える!信用を守る企業の初動対応と外部支援マニュアル
従業員の言動が、SNSや口コミで一気に拡散される時代。
たった一人の対応が、企業全体の信用を揺るがす事態に発展することも珍しくありません。
実際、従業員の不適切な発言や顧客への態度が火種となり、炎上や風評被害に発展するケースが相次いでいます。初動対応を誤ると、企業イメージの回復に多大なコストと時間がかかる恐れもあります。
そこで本記事では、従業員による不祥事が発覚した際に企業が取るべき初動対応のポイントと、信頼を守るための外部支援の活用方法を解説します。
この記事を読むことで、トラブルが起きた際にどう動けばよいのか、実践的な対応手順と社内では対応しきれない場合のプロの頼り方が理解できます。
もしもの事態に備え、ぜひ最後までご覧ください。
従業員の行動が引き起こす顧客トラブルとは
従業員の何気ない一言や行動が、顧客とのトラブルを招き、企業の信用問題に発展するケースが増えています。
近年はSNSや口コミサイトを通じて情報が瞬時に拡散されるため、企業としては些細な対応ミスも見逃せません。
ここでは、どのような言動が不祥事につながるのか、そしてなぜ個人の行動が企業ブランド全体を揺るがすのかを解説します。
どんな行動が不祥事に発展するのか
従業員が顧客とのあいだで以下のような行動を取ると、企業全体のリスクにつながる場合があります。
- 高圧的・不誠実な接客態度
- 差別的または侮辱的な言動
- SNS等における、顧客情報や会話内容の投稿
- 無断で顧客を撮影・録音・拡散する行為
- 顧客情報の盗難・無断閲覧・第三者提供
- 顧客からのクレームを軽視・嘲笑する態度
- ハラスメント行為(パワハラ・セクハラ・カスタマーハラスメント)
厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間に「顧客等からの著しい迷惑行為」の相談があった企業は27.9%にのぼり、パワハラ(64.2%)、セクハラ(39.5%)に次ぐ高い割合となっています。
なぜ個人の問題が企業全体の信用を揺るがすのか
従業員は「企業の顔」であり、個人の言動が企業の評価に直結します。
SNSや口コミが瞬時に拡散される現代では、たった一つの事案が企業ブランド全体の信頼を一気に揺るがします。
たとえば、顧客がSNSに投稿することで、企業の信用はまたたく間に毀損され、炎上へと発展するリスクがあります。
このように、個人の問題を「小さなミス」と見逃すことは、企業全体のリスク管理における大きな落とし穴となるのです。
従業員のトラブル発覚後、顧客に対して企業が行うこと
従業員による不適切な言動や不祥事が発覚した場合、企業に求められるのは「迅速な初動対応」と「誠実な顧客対応」です。
問題が拡大する前に正しい対応を取れるかどうかが、企業の信頼を守る分岐点となります。ここでは、実務で押さえるべき初動のポイントから、顧客への説明、法的対応までを解説します。
初動対応のポイントと社内体制の整え方
従業員のトラブルが発覚した際、最初に求められるのは迅速な事実確認です。関係者への聞き取り、業務ログの調査、該当端末の使用履歴の確認などを通じて、事実を正確に把握します。
IPA(情報処理推進機構)のインシデント対応ガイドラインでは、初動対応として「検知・隔離・記録・連絡」が重要とされており、責任者への報告ルートや情報保全の体制が必要です。
顧客への説明と信頼回復の進め方
トラブルの当事者である顧客には、早期に連絡を取り、経緯と対応方針を明確に伝える必要があります。説明が遅れたり不十分だったりすると、二次的な不信感を招き、企業全体の信用失墜につながります。
経済産業省の中小企業向け対策では、適切なタイミングで「事実」「謝罪」「再発防止策」をセットで伝えることが重要とされています。
参考資料:中小企業向け情報漏洩対応の手引き
法的責任と情報漏洩のリスク管理
トラブルが顧客の個人情報に関わる場合、企業には法的な説明責任が生じます。個人情報保護法では、漏洩が発生した際には「本人への通知」と「個人情報保護委員会への報告」が求められるケースがあります。
IPAの「情報漏えい発生時の対応ポイント集」によれば、漏洩の種類・範囲を把握し、対象者や関係機関へ速やかに対応することが推奨されています。
外部の力で顧客トラブルを解決する方法
従業員と顧客の間で起きた問題が、企業全体の信用やブランドに影響を及ぼすケースは少なくありません。特に、SNSや検索エンジンでの拡散、情報漏洩、証拠の不在といった問題は、社内のリソースだけでは対応しきれないことがあります。
こうした局面では、専門性と即応性を備えた外部パートナーとの連携が、企業の信頼維持と再発防止において重要となります。
本章では、外部パートナーの必要性と、実際に活用できるサービス例について紹介します。
社内対応の限界と外部パートナーの必要性
従業員と顧客の間で発生したトラブルは、社内で対処できる範囲を超えることがあります。
たとえば、SNS上での情報拡散、風評による検索結果の悪化、顧客情報の漏洩といった事態においては、迅速かつ専門的な対応が求められます。
中小企業庁の調査でも、トラブル発生時の課題として「社内に専門人材がいない」「対応が遅れた」といった声が多く挙げられています。
こうした状況では、初動対応のスピードと精度を両立できる外部パートナーの存在が、信頼維持の分かれ目になります。
CYBER VALUEが提供する支援サービス
従業員の不祥事が顧客トラブルに発展した場合、企業内だけでの対応には限界があります。SNS上での拡散や検索汚染、証拠の保全など、外部の専門的なサポートが欠かせません。
CYBER VALUEでは、以下のような支援を実施しています。
| サービス名 | 概要 |
|---|---|
| Web/SNSモニタリング | ネット上の炎上や拡散リスクをリアルタイムで監視 |
| フォレンジック調査・対策 | 不正の証拠や漏洩ルートの特定・技術調査を実施 |
| 風評被害対策 | 拡散したネガティブ情報の印象をコントロール |
| サジェスト汚染対策 | 検索候補のネガティブな語句を除去・修正 |
CYBER VALUEの支援を活用することで、早期対応と信頼回復、そして再発防止まで一貫したリスク対策が可能になります。
外部パートナーを活用して顧客トラブルを未然に防ごう
従業員が、顧客トラブルを引き起こすリスクに対して、社内の初動対応だけでなく、法的責任や情報漏洩への備えも含めた総合的な対策が不可欠です。
SNSでの炎上や検索結果の風評被害といった問題には、社内対応だけでは限界があり、外部の専門パートナーの力を借りることが有効です。
CYBER VALUEでは、こうした事態に対応するためのモニタリングや風評対策、フォレンジック調査などを一貫して支援しています。
自社の信頼を守るためにも、早めの備えと専門的なサポートの導入をぜひご検討ください。
【2025年最新】情報漏洩の原因TOP5と事例。不正アクセス・内部不正から会社を守る対策とは?
今情報漏洩対策が重要なのか、その原因と具体的な対策、そして自社だけでは気づけないリスクにどう対処すべきかが明確になります。
1. なぜ今、情報漏洩対策が「経営課題」なのか?
情報漏洩が発生すると、企業は単に「情報を失う」だけでは済みません。事業の根幹を揺るがすほどの深刻なダメージを受ける可能性があります。
そのダメージは、大きく2種類に分けられます。
直接的損害:事業継続を脅かす金銭的損失
情報漏洩が起きた場合、企業は多額の金銭的負担を強いられます。
- 損害賠償: 漏洩した個人情報の持ち主である顧客や従業員から、損害賠償請求訴訟を起こされるケースがあります。過去の事例では、一人あたり数千円から数万円の賠償が命じられています。これが数万件規模になれば、賠償額は億単位に膨れ上がります。(参考事例:Yahoo! BB顧客情報漏洩事件)
- 事業停止による損失: ランサムウェア攻撃などにより基幹システムが停止した場合、生産やサービスの提供ができなくなり、復旧までの間、売上がゼロになる可能性があります。
- 調査・復旧コスト: 漏洩原因を特定するためのフォレンジック調査費用や、システムの復旧、再発防止策の導入にも多額のコストがかかります。
間接的損害:回復が困難な信用の失墜
金銭的なダメージ以上に深刻なのが、企業の「信用」の失墜です。
一度「あの会社は情報をきちんと管理できない」という評判が広まると、顧客は離れ、取引先からは契約を打ち切られるかもしれません。このような風評被害やブランドイメージの毀損は、回復に長い時間と多大な努力を要します。
法律が求める企業の「安全管理措置」
さらに、2022年に改正された「個人情報保護法」では、企業に対して個人データを安全に管理するための措置(安全管理措置)を講じることを義務付けています。
この義務を怠り、重大な情報漏洩が発生した場合には、国から改善命令が出され、従わない場合は1億円以下の罰金が科される可能性もあります。もはや「知らなかった」では済まされないのです。
2. 【2025年最新データ】情報漏洩の原因ランキングTOP5と手口
では、実際に情報漏洩はどのような原因で発生しているのでしょうか。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査などを基にした、最新の原因ランキングを見ていきましょう。
【1位】外部からの攻撃(不正アクセス・サイバー攻撃)
最も深刻な被害をもたらすのが、悪意ある第三者による外部からの攻撃です。
- 手口:
- ランサムウェア: PCやサーバー内のデータを勝手に暗号化し、元に戻すことと引き換えに高額な身代金を要求するウイルス。警察庁によると、2023年に報告された被害件数のうち、中小企業の被害件数は約37%増加しています。対策が比較的手薄な中小企業の被害増加につながっていると考えられます。(出典:警察庁「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」)
- マルウェア(ウイルス)感染: メールの添付ファイルや不正なWebサイトを介してウイルスに感染させ、情報を盗み出します。
- 標的型攻撃: 取引先や関係者を装った巧妙なメールを送りつけ、ウイルスに感染させたり、IDやパスワードを盗んだりします。
- 事例: 2024年6月、大手出版社KADOKAWAがランサムウェア攻撃を受け、ニコニコ動画を含む多くのサービスが停止。顧客や取引先の情報流出の可能性が発表され、事業に甚大な影響が出ました。(参考:KADOKAWAランサムウェア攻撃による情報漏洩に関するお知らせ)
【2位】内部不正(退職者による情報持ち出しなど)
外部からの攻撃だけでなく、「内部」からの情報漏洩も後を絶ちません。
- 手口:
- 退職者による情報持ち出し: 転職先での利用などを目的に、在職中にアクセスできた顧客情報や営業秘密を不正に持ち出すケース。
- 現職従業員による不正: 処遇への不満などから、情報を外部に売却するケース。
- 事例: 大手通信教育企業のベネッセで、業務委託先の元社員が約3,500万件もの顧客情報を不正に持ち出し、名簿業者に売却。社会問題にまで発展しました。(参考:ベネッセホールディングス発表資料)
【3位】ヒューマンエラー(メール誤送信・設定ミス)
悪意がなくても、ほんの少しの不注意が重大な情報漏洩につながります。これを「自分は大丈夫」と思い込んでしまうのが「正常性バイアス」の怖いところです。
- 手口:
- メール誤送信: 個人情報を含むファイルを、誤って関係のない宛先に送ってしまう。
- 設定ミス: クラウドストレージなどのアクセス権限の設定を誤り、誰でも閲覧できる状態にしてしまう。
- 事例: ある地方自治体で、幼稚園に補助金の案内メールを送る際、誤って全園児約2,000人分の個人情報を含むファイルを添付してしまい、各園にデータの削除を依頼する事態となりました。(参考:町田市発表資料)
【4位】物理的な紛失・盗難
リモートワークの普及に伴い、物理的な管理の重要性も増しています。
- 手口:
- 業務用のPCや、データを保存したUSBメモリの紛失・置き忘れ。
- カフェや電車内での盗難、車上荒らしなど。
- 事例: 従業員がリモートワーク中に業務用PCを紛失し、保存されていた顧客情報が流出する可能性が発覚。会社の信用問題に発展するケースは少なくありません。
【5位】管理体制の不備・ルールの形骸化
技術的な対策以前に、社内の管理体制やルールに不備があるケースです。
- 手口:
- 重要な情報が保存されているサーバーに、誰でもアクセスできる状態になっている。
- 情報機器の持ち出しに関するルールがなく、野放しになっている。
- 退職した従業員のアカウントが削除されず、アクセス可能なままになっている。
- 事例: 元職員が、元同僚のID、パスワードを使い退職後に営業秘密にアクセスし転職先に持ち出したとして逮捕された事例があります。(参考:日本経済新聞)
3. 今すぐ始めるべき情報漏洩への3つの対策
これらの多様な脅威に対し、企業はどう立ち向かえば良いのでしょうか。対策の基本は「組織」「人」「技術」の3つの観点から、多層的に防御することです。
組織的対策:セキュリティの土台となるルールを作る
まず、会社全体で情報セキュリティに取り組むための土台作りが必要です。
- 社内規定の策定: 「情報セキュリティポリシー」を策定し、情報の取り扱いに関する基本方針を明確にします。
- 体制構築: 情報セキュリティに関する責任者を任命し、インシデント発生時の報告・連絡体制を整備します。
- アクセス管理: 誰が・どの情報にアクセスできるのかを明確に定義し、権限を最小限に設定します。
- 認証取得の検討: ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)やプライバシーマークといった第三者認証の取得は、体制構築と対外的な信用の証明に繋がります。
人的対策:従業員一人ひとりの意識を変える
どんなに優れたシステムを導入しても、それを使う「人」の意識が低ければ意味がありません。
- 従業員教育の実施: 全従業員を対象に、情報セキュリティの重要性や社内ルールに関する研修を定期的に実施します。
- 標的型攻撃メール訓練: 疑似的な攻撃メールを送信し、従業員が開いてしまわないか、適切に報告できるかを訓練します。
- パスワード管理の徹底:推測されにくい複雑なパスワードの設定と、定期的な変更をルール化します。
技術的対策:システムで外部と内部の脅威を防ぐ
ルールや人の意識を補強し、脅威を物理的にブロックするのが技術的対策です。
- UTM/ファイアウォール: 社内ネットワークの入口で、不正な通信やサイバー攻撃をブロックします。
- EDR/ウイルス対策ソフト: PCやサーバーがウイルスに感染するのを防ぎ、万が一感染した場合も検知・対応します。
- VPN: リモートワーク時に、安全な通信経路を確保し、盗聴を防ぎます。
- データの暗号化: 万が一データが盗まれても、中身を読み取れないようにします。
4. 自社だけでは困難?潜在的なリスクを見つけ出すには
ここまで対策を読んで、「やるべきことが多すぎる」「自社のやり方が本当に正しいのかわからない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
まさにその点が、多くの企業が抱える課題です。
対策を講じたつもりでも、攻撃者の目線でなければ見つけられない「穴」が残っている可能性があります。形骸化したルール、従業員の慣れによる気の緩み、最新のサイバー攻撃への知識不足など、自社だけでは気づけない「潜在的な危険」が潜んでいるのです。
そこで重要になるのが、専門家による客観的な「脆弱性診断(セキュリティ診断)」です。
プロの視点で企業のネットワークやWebサイトを調査し、セキュリティ上の弱点を特定することで、本当に効果のある対策を、優先順位をつけて実行できるようになります。
5. 【PR】専門家による包括的なセキュリティ支援なら「CYBER VALUE」
ロードマップが提供する「CYBER VALUE」は、ここまで解説してきた情報漏洩に関するあらゆる課題を、ワンストップで解決する専門サービスです。
こんなお悩みはありませんか?
- 何から対策すればいいかわからない
- 社内にITやセキュリティの専門家がいない
- 従業員のセキュリティ意識が低く、ルールが守られているか不安
- 過去にヒヤリとした経験があり、本格的な対策を検討している
- 万が一、情報漏洩が起きた時の対応が不安だ
一つでも当てはまったら、ぜひ私たちにご相談ください。「cyber value」は、貴社の状況に合わせて最適なソリューションをご提供します。
- セキュリティ診断・対策 セキュリティ対策の第一歩として、専門家が貴社のホームページ上の隠れたリスクを発見し、対策プランをご提案します。
- フォレンジック調査・対策 万が一のインシデント発生時も安心。迅速な原因究明と、被害を最小限に抑える初動対応、そして再発防止策までを徹底的に支援します。
- Web/SNSモニタリング・風評被害対策 情報漏洩が引き起こす、企業の信用失墜やネット炎上といった二次被害から貴社を守ります。システム的にとらえられないソーシャルメディアのハイコンテキストで難しいニュアンスにも目視で確認します。
まとめ
情報漏洩は、今や企業の規模を問わず、すべての組織にとって避けては通れない経営リスクです。
その原因は、外部からの巧妙なサイバー攻撃から、社内の悪意なきヒューマンエラーまで多岐にわたります。そして一度発生すれば、金銭的損失はもちろん、長年かけて築き上げた「信用」という最も大切な資産を、一瞬で失いかねません。
対策の基本は、「組織」「人」「技術」の三位一体で、多層的な防御壁を築くこと。そして、自社の対策に少しでも不安があれば、迷わず専門家の力を借りることが、未来のリスクから会社を守る最善の選択肢です。
この記事が、貴社の貴重な情報資産と未来を守る一助となれば幸いです。
Q&Aよくある質問
Q1サジェスト対策はどのくらいで効果が出ますか?
キーワードにもよりますが、早くて2日程度で効果が出ます。
ただし、表示させたくないサイトがSEO対策を実施している場合、対策が長期に及ぶおそれもあります。
Q2一度見えなくなったネガティブなサジェストやサイトが再浮上することはありますか?
再浮上の可能性はあります。
ただ、弊社ではご依頼のキーワードやサイトの動向を毎日チェックしており、
再浮上の前兆がみられた段階で対策を強化し、特定のサジェストやサイトが上位表示されることを防ぎます。
Q3風評被害対策により検索エンジンからペナルティを受ける可能性はありませんか?
弊社の風評被害対策は、検索エンジンのポリシーに則った手法で実施するため、ペナルティの心配はありません。
業者によっては違法な手段で対策をおこなう場合があるため、ご注意ください。
Q4掲示板やSNSのネガティブな投稿を削除依頼しても受理されないのですが、対応可能ですか?
対応可能です。
弁護士との連携により法的な削除要請が可能なほか、投稿者の特定や訴訟もおこなえます。
Q5依頼内容が漏れないか心配です。
秘密保持契約を締結したうえで、ご依頼に関する秘密を厳守いたします。
Q6他社に依頼していたのですが、乗り換えは可能ですか?
可能です。
ご依頼の際は他社さまとどのようなご契約、対応がなされたのかをすべてお伝えください。
Q7セキュリティ事故発生時にはすぐ対応していただけますか?
はい。緊急時には最短即日でフォレンジックを実施いたします。


