
ABOUTCYBER VALUEとは
『CYBER VALUE』とは株式会社ロードマップが提供する、
風評被害トラブル発生時の企業イメージ回復、ブランドの価値維持のためのトータルソリューションです。
インターネット掲示板に企業の悪評が流される事例はこれまでもありましたが、近年はSNSの普及で、
より多くの人が気軽に企業やサービスに対する意見や不満を投稿するようになり、
それが発端で炎上が発生することもしばしばあります。
ネット炎上は一日3件以上発生するといわれます。
企業に対する悪評が多くの人の目に入れば、真偽に関わらず企業イメージや売上、信頼の低下につながりかねません。
このようなリスクから企業を守り、運営にのみ注力していただけるよう、私たちが全力でサポートいたします。
REASONCYBER VALUEが
選ばれる理由
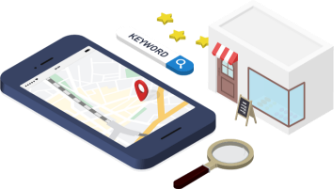
SEO対策の豊富な実績
株式会社ロードマップは2012年の創業以来、長きにわたりSEO対策をメ
イン事業としており、その実績は累計 200件以上。そのノウハウをもとに
したMEO対策や逆SEO、風評被害対策に関しても豊富な実績がありま
す。
長くSEO対策に携わり、つねに最新の情報を学び続けているからこそ、
いまの検索サイトに最適な手法でネガティブな情報が表示されないよう
に施策、ポジティブな情報を上位表示できます。
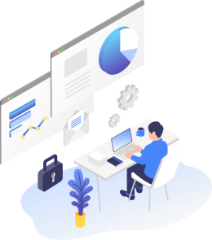
事態収束から回復まで
ワンストップ
株式会社ロードマップには、SEO対策やMEO対策などWebマーケティン
グの幅広いノウハウをもつディレクター、高度な知識と技術が必要なフ
ォレンジック対応・保守管理の可能なセキュリティエンジニアが在籍し
ており、すべて自社で対応できます。
そのため下請けに丸投げせず、お客さまの情報伝達漏れや漏えいといっ
たリスクも削減。よりリーズナブルな料金でサービスの提供を実現しま
した。また、お客さまも複数の業者に依頼する手間が必要ありません。

弁護士との連携による
幅広いサービス
インターネット掲示板やSNSにおける誹謗中傷などの投稿は、運営に削
除依頼を要請できます。しかし「規約違反にあたらない」などの理由で
対応されないケースが非常に多いです。
削除依頼は通常、当事者か弁護士の要請のみ受け付けています。弁護士
であれば仮処分の申し立てにより法的に削除依頼の要請ができるほか、
発信者情報の開示請求により投稿者の個人情報を特定、損害賠償請求も
可能です。

セキュリティ面のリスクも解決
株式会社ロードマップは大手、官公庁サイトを含む脆弱性診断、サイバ
ー攻撃からの復旧であるフォレンジック調査・対応の実績も累計400件以
上あります。
風評被害対策サービスを提供する企業はほかにもありますが、セキュリ
ティ面を含めトータルに企業のブランド維持、リスク回避をおこなえる
企業はありません。
こんなお悩みありませんか?

検索サイトで自社の評判を下げるようなキーワードが出てくる

自社にどのような炎上・風評被害の潜在リスクがあるか整理できていない
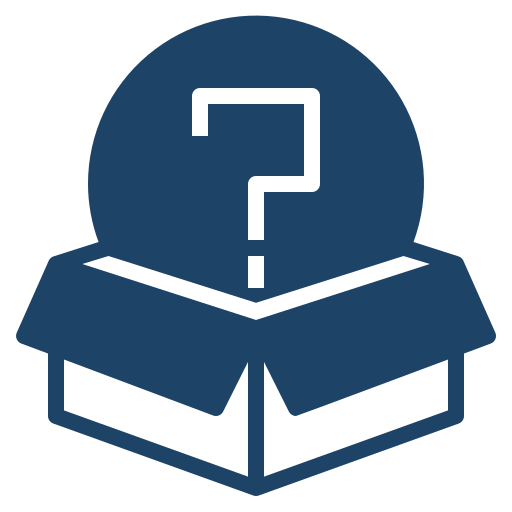
セキュリティ専門家による定期チェックを実施しておらず、課題や必要予算が見えていない
SERVICEサービス内容
企業イメージの
回復・維持を総合サポート

問題の解決
企業イメージに大きく関わる、つぎのような問題をスピード解決いたします。
検索サイトのサジェストにネガティブなキーワードが出るようになってしまった
サジェスト削除(Yahoo!・Google・Bing)
逆SEO
インターネット掲示板やSNSの投稿などで風評被害を受けた
弁護士連携による削除依頼・開示請求
サイバー攻撃を受けてサーバーがダウンした、サイト改ざんを受けてしまった
フォレンジック調査+対応

原因の究明・イメージ回復
風評被害やトラブル発生の原因となったのはなにか、どこが炎上の発生源かを調査し、 イメージ回復のためにもっとも最適な施策を検討、実施します。
企業やサイトの評判を底上げする施策
SEO対策(コンテンツマーケティング)
MEO対策
サジェスト最適化戦略支援
セキュリティ面のリスク調査
ホームページ健康診断

価値の維持
風評被害、サイバー攻撃被害を受けてしまった企業さまに対し、 つぎのような施策で価値の維持までトータルでサポートいたします。
セキュリティ運用
保守管理(月一度の検査ほか)
バックグラウンド調査
リスク対策を多角的にサポート

サイバーチェック
取引先や採用の応募者の素性を調査し、取引・採用前に素行に問題のない 人物であるか確認しておける、現代のネット信用調査サービスです。
反社チェック
ネット記事情報をもとに犯罪・不祥事・反社関連の情報を収集します。 採用・取引の最低限のリスク管理に。
ネットチェック
SNS・掲示板・ブログなどから会社・人に関する情報を収集。 企業体質・人物健全度のリスクを可視化します。
TRUST CHECK
匿名アカウント、ダークWebすべてのサイバー空間を網羅ネットの 深部まで調べあげる、究極のリスク対策支援ツールです。
COLUMNコラム
一覧を見る【事例で解説】取引先の不祥事で炎上!自社ブランドを守るために取るべき3つの対策
ある日突然、主要サプライヤーがSNSのトレンドに。「品質データ改ざん」「劣悪な労働環境」。
自社への直接的な言及はまだなくても、背筋が凍るような感覚に襲われるかもしれません。
パートナーやサプライヤーの不祥事は、もはや「他人事」ではありません。
それはサプライチェーンで繋がった自社のブランド価値や売上を直接脅かす、重大な経営リスクです。「うちは関係ない」「まさか自社にまで影響は…」という思い込みこそが、最も危険なのです。
この記事では、なぜ自社にまで評判の火の粉が飛んでくるのか、そのメカニズムを実際の事例やデータを交えて解説し、企業が取るべき具体的な「3つの対策」を提案します。
なぜ取引先の不祥事が自社に「飛び火」するのか?4つの炎上シナリオ
サプライチェーンで強固に結びついている以上、消費者や取引先、株主といったステークホルダーからは、良くも悪くも「一蓮托生」と見なされます。
特にネガティブな情報が駆け巡る現代において、一社の不祥事はまたたく間に「レピュテーションの延焼」を引き起こし、自社は「もらい事故」のような形で炎上に巻き込まれてしまうのです。
ここでは、実際に起こりうる4つのリスクシナリオを、データや実例とともに解説します。
シナリオ1:製品事故・リコール
自動車メーカーの認証不正問題では、部品供給元であるグループ企業の不正が発端となり、最終的に多くの完成車メーカーが出荷停止に追い込まれる事態に発展しました。
これは、一社の品質問題がサプライチェーン全体を揺るがし、最終製品のブランドイメージを大きく損なうことを示す典型的な例です。
参照:自動車メーカーなど5社の認証不正 “安全性の検証終えるまで出荷停止” 国交省
【あなたの会社で起こるとしたら…】 部品メーカーA社が、耐久性に関する品質データを偽装。その部品を使用したあなたの会社の主力製品に不具合が多発し、SNSでは「〇〇(あなたの会社名)の製品は危険だ」という投稿が急増。
結果、製品の信頼性は失墜し、ブランドイメージは大きく低下。大規模リコールによる直接的な費用負担も発生します。
シナリオ2:知的財産権侵害
下請事業者との取引において、発注側が下請事業者の知的財産(ノウハウ、データ等)を不当に利用するケースは、下請法で問題視されています。
これが公になれば、発注側のコンプライアンス意識が厳しく問われます。
参照:知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形 | 中小企業庁
【あなたの会社で起こるとしたら…】 共同開発パートナーであるB社が、開発プロセスにおいて他社の特許技術を無断で流用していたことが発覚し、ニュースで報道される。
結果、「コンプライアンス意識が低い企業と取引している会社」というレッテルを貼られ、特にBtoB取引における信用が失墜。最悪の場合、製品の販売停止に追い込まれるリスクも抱えます。
シナリオ3:環境・人権問題(ESGリスク)
近年、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みは、投資家や消費者にとって重要な判断基準となっています。
サプライヤーの非倫理的な労働実態が告発され、そのサプライヤーから調達していた大手アパレル企業が厳しい批判にさらされ、不買運動にまで発展した事例は世界的に知られています。
※編集注:特定企業の事例への直接リンクは避けますが、新疆ウイグル自治区における人権問題を巡るアパレル業界の動向は、このリスクの代表例として広く報道されています。
【あなたの会社で起こるとしたら…】 原材料の供給元である海外のC工場で、環境汚染や人権侵害が国際的なNGOから告発される。SNSでは「#〇〇(あなたの会社名)ボイコット」といったハッシュタグがトレンド入り。
結果、ESG評価は急落し、投資家は離れ、倫理観を重視する消費者からも見放されてしまいます。長年かけて築き上げた企業の社会的責任(CSR)への取り組みも、一瞬にして信頼を失います。
シナリオ4:プライバシー侵害(情報漏洩)
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表した「情報セキュリティ10大脅威 2024」では、「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」が組織向け脅威で第2位にランクインしています。
委託先がサイバー攻撃の踏み台にされ、そこから自社の機密情報や顧客情報が漏洩するケースは、もはや他人事ではありません。
参照:情報セキュリティ10大脅威 2024 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
【あなたの会社で起こるとしたら…】 顧客管理システムの運用を委託していたD社がランサムウェアに感染。あなたの会社が預かっていた数万件の顧客情報も漏洩した可能性が浮上。
結果、顧客からの信頼は完全に失墜。監督官庁への報告義務や賠償問題に発展するだけでなく、自社の杜撰なセキュリティ体制そのものが厳しく糾弾されることになります。
自社ブランドを守るために今すぐ取るべき3つの対策
では、こうした「もらい事故」から自社を守るためには、具体的に何をすべきなのでしょうか。
パニックにならず、冷静に対処するための3つのアクションプランを提案します。
【対策1:検知】ネガティブ情報の迅速な検知と状況把握
WHAT(何をすべきか): 炎上の初期段階で、火種がどこで、どのように、どれくらいの規模で広がっているかを、リアルタイムかつ正確に把握することが何よりも重要です。
WHY(なぜ必要か): 対応の遅れは憶測やデマを拡散させ、被害を致命的に拡大させます。問題覚知から数時間の初動の速さが、その後の明暗を分けます。
HOW(どうやって解決するか):
【cyber valueができること】 24時間365日、人の目でSNSや掲示板を監視し続けるのは不可能です。
ロードマップ社の**「Web/SNSモニタリング」**サービスを活用すれば、指定したキーワード(例:取引先名、自社製品名)を含む投稿をシステムがリアルタイムで検知します。システムだけでは捉えきれない、ソーシャルメディアのハイコンテキストで難しいニュアンスにも人力で対応。言葉のニュアンスにより炎上を事前に検知し、炎上の予兆やネガティブな兆候をいち早く掴み、迅速な初期対応を可能にします。
【対策2:対応】正確な情報発信と延焼の防止
WHAT(何をすべきか): 把握した事実に基づき、自社のウェブサイトやプレスリリースで公式見解を迅速に発表します。同時に、事実無根のデマや悪質な誹謗中傷に対しては、ネガティブワードを含む風評サイト(悪質なサイト)を検索順位から押し下げる対応をする必要があります。
WHY(なぜ必要か): 検索結果にネガティブなキーワードが表示されてしまうと、それだけでユーザーは悪い印象を受け、ビジネスに大きな悪影響を与えかねません。ネガティブワードを含むサイトの検索順位を下げることで、ステークホルダーからの信頼失墜を最小限に食い止めます。
HOW(どうやって解決するか):
【cyber valueができること】 CYBER VALUEでは過去10年間、SEO対策をメイン事業とし、検索エンジンのアルゴリズムや関連キーワード・サジェストの仕組み などを熟知しております。
自社で保有しているサイトや、当社で新規作成したサイトを上位表示させることで、ネガティブワードを含む風評サイト(悪質なサイト)を検索順位から押し下げる逆SEO対策を実施します。
【対策3:予防】自社とサプライチェーンの再評価と体制強化
WHAT(何をすべきか): 今回の事態を教訓に、他の取引先の評判やリスクに問題はないか、そして何より、自社のセキュリティ体制に穴はないかを徹底的に見直します。
WHY(なぜ必要か): 一時的な対応だけで終わらせては、必ず同じ過ちが繰り返されます。未来の同様のリスクを未然に防ぎ、継続的に事業を守る「しなやかで強い体制」を構築することが不可欠です。
HOW(どうやって解決するか):
【cyber valueができること】大きな予算は割けないが、基礎的なセキュリティ対策から始めたい、そういう企業さまにセキュリティ対策の第一歩という位置づけで、対象となるホームページの脆弱性を診断します。
「セキュリティ診断・対策」で自社のホームページに潜む脆弱性を洗い出し、万が一、情報漏洩の疑いがある場合は「フォレンジック調査・対策」で被害範囲や原因を特定。技術的な側面から、再発防止策を徹底的にサポートします。
→ セキュリティ診断・対策の詳細はこちら → フォレンジック調査・対策の詳細はこちら
まとめ
本記事で解説したように、グローバルにサプライチェーンが広がる現代において、パートナーやサプライヤーの不祥事は、決して他人事ではありません。
重要なのは、それがいつ起きても対応できるよう、
- 検知:リスクの予兆をいち早く掴む
- 対応:被害を最小化する手を打つ
- 予防:未来のリスクに備える
という3つのサイクルを、平時から意識し、回し続けることです。
問題が起きてから慌てるのではなく、事前に備えておくことこそが、変化の激しい時代に自社のブランドと未来を守る、最善の策と言えるでしょう。
サプライチェーンの風評リスク対策は、専門家にご相談ください
自社の状況に少しでも不安を感じた方、具体的な対策について相談したい方は、お気軽にお問い合わせください。
「何から手をつければ良いかわからない」という、漠然としたお悩みの段階でも構いません。専門家が状況を整理し、最適な解決策をご提案します。
口コミ削除はできる?ネガティブなレビューが企業に与える影響と正しい対処法
Googleマップやレビューサイトに書かれた口コミは、企業の信用に大きく関わります。
体験談ベースの悪評はたった1件でも検索上位に表示され、ビジネスに深刻な影響を与える可能性があります。
しかし、すべての口コミが削除できるわけではなく、誤った対応をすると炎上や信頼低下につながるおそれもあります。
そこで本記事では、口コミ削除の可否や企業がとるべき対応策について詳しく解説します。
記事を読むことで、悪質な口コミから企業を守るために必要な考え方と具体的な対処法がわかります。
ぜひ最後までご覧いただき、貴社のリスク管理にお役立てください。
口コミのレビューが企業にもたらす深刻なリスク
インターネット上の口コミは、企業の信用や売上に直結する時代です。
体験談に基づいた否定的な口コミは、閲覧者に強い印象を与え、購買行動に大きく影響します。
実際、総務省の調査によると、約60%の消費者がネットの口コミを購買判断の材料にしていると報告されています。
たった一件のレビューでも、「信頼性のある実体験」として広がり、以下のような事態に発展する恐れがあります。
- 新規顧客の離脱(レビュー閲覧後に問い合わせや来店を断念)
- 検索結果上にネガティブ情報が残り、企業ブランドの毀損
- SNSやまとめサイトで拡散し、風評被害に発展
こうしたリスクを未然に防ぐには、口コミを「監視し、削除し、対応する」という3つの視点が必要です。
口コミは削除できる?基本の判断基準
Googleマップやレビューサイトに投稿された体験談は、検索結果で上位に表示されることもあります。
ネガティブな口コミを放置していると、ビジネスに大きなダメージを与える可能性があります。
「悪い口コミを削除したい」と考える企業は多いものの、実際には削除できるものとできないものが明確に分かれています。
ここでは、Googleや主要なレビューサイトの削除ルール、そして削除が認められる悪質な口コミの具体例を紹介します。
Googleやレビューサイトの削除ルールとは
Googleマップの口コミ削除の可否は、Googleの「投稿コンテンツに関するポリシー」に沿って判断されます。
削除の対象となるのは、主に以下のような内容です。
これらの違反が確認できれば、Googleの管理画面から「不適切な口コミを報告」することで、削除対応が検討されます。
ただし、「接客態度が気に入らなかった」「料理が口に合わなかった」といった体験に基づく主観的な意見は、たとえ企業側が不当と感じても削除対象にはならないことが多い点に注意が必要です。
たとえ企業側が不当だと感じても、ユーザーが実際にサービスを利用したうえでの意見であれば、削除のハードルは高いのが現実です。
「削除できる」悪質口コミの具体例
虚偽情報や誹謗中傷、スパム行為などの「ルール違反」が明確であれば、削除される可能性はあります。
以下に、実際に削除対象となる可能性が高い口コミの例を挙げます。
例1:第三者による誹謗中傷
「この店は最低。オーナーの○○ってやつ、犯罪者かと思った。」
他人の人格を否定したり、名誉を傷つけるような表現は、人身攻撃・名誉毀損としてポリシー違反に該当する可能性があります。
例2:競合店によるなりすまし投稿
「商品が全部偽物だった。対応も最悪。」
実際には来店していない人物による投稿や、意図的に企業イメージを貶める虚偽内容は、報告・削除の対象となり得ます。
例3:同一人物による連投スパム
「もう2度と行かない!」「最悪!接客がひどい!」(※数分おきに複数回投稿)
同一人物が短時間に何度も投稿している場合、スパム投稿とみなされる可能性があります。GoogleはAIと人力審査の両方でスパム検知を行っています。
例4:レビューと関係ない投稿
「この近くの道路は渋滞がひどくて最悪」
店舗・サービスとは関係のない話題は、レビューの本来の趣旨に反しており、削除申請が通る可能性があります。
ただし、これらの投稿が削除されるかどうかは、投稿の文面・背景・証拠資料の有無によって変わるため、確実な削除を求める場合は、専門家のサポートが不可欠です。
削除依頼の判断を誤ると、かえって投稿者とのトラブルやSNSでの逆炎上に発展する恐れもあります。
削除の判断に迷った際は、まずガイドラインを熟読したうえで、外部の専門業者に相談するのが賢明です。
出典:デジタル庁|「インターネット上の誹謗中傷に関する制作パッケージ」に基づく取り組み
口コミ削除だけで解決しない?放置NGな3つの理由
口コミの削除は確かに有効な対策ですが、それだけでは根本的な解決にならない可能性もあります。
まずは、ネガティブな口コミを放置するリスクを理解することが重要です。
1. 拡散スピードが早すぎる
SNSやネット掲示板では、ネガティブな口コミがまたたく間に拡散される傾向があります。
体験談ベースの投稿は「リアルな証言」として受け取られやすく、共感を呼び、リポストや引用の連鎖で一気に広がっていきます。
たとえ投稿が削除されたとしても、炎上が始まった後では、まとめサイトやSNS投稿で二次拡散が進行してしまい、情報の回収が困難になるリスクがあります。
2. サジェストや検索結果に悪影響が出る
ネガティブな口コミが長期間ネット上に残ると、Google検索のサジェスト(関連検索ワード)や検索結果に悪影響を与えます。
たとえば、「会社名 詐欺」や「店舗名 ひどい」といったキーワードがサジェストに表示されると、悪評に注目が集まる構造が生まれます。
3. 顧客・取引先からの信頼低下につながる
悪質な口コミは、消費者だけでなく、取引先や求職者の印象にも影響します。
企業名で検索したときに悪評が出てくると、会社の信頼を疑われ、商談や提携の見送りにつながることもあります。
採用面でも、職場の評判を見た応募者が離脱するケースは少なくありません。ネット上の印象が、信用や人材確保に直結する時代です。
口コミ削除だけではない!企業の正しい対応とは?
悪質な口コミや風評被害に対しては、削除対応だけでなく、事前の監視と継続的な対策が重要です。
ここでは、当社が提供するCyber Valueの具体的なサポート内容をご紹介します。
1. Web・SNSモニタリングで早期発見
ネット上の口コミやSNSの投稿は、拡散する前の早期対応が重要です。
Cyber Valueでは、WebメディアやSNSを24時間体制でモニタリングし、問題の兆候をリアルタイムで検知します。
不満や批判が表面化した直後に動くことで、後手に回る炎上リスクや、長期的な風評被害を最小限に抑えることができます。
出典:Web/SNSモニタリング|Cyber Value(ロードマップ社)
2. 風評被害対策と検索結果クリーンアップ
当社では、検索環境全体を分析し、ネガティブなコンテンツが目立たない構成へと整える施策を実施しています。
企業にとって好ましい情報を適切に発信・強化することで、検索結果のバランスを取り戻します。
また、検索サジェストに表示される「企業名+詐欺」「店舗名+トラブル」といったキーワードが自然と消えていくよう、検索エンジンの仕組みに即したサジェスト対策も行っています。
風評の火種を見逃さず、検索画面全体を健全な状態に保つことで、ブランドの信頼性を長期的に守ることが可能です。
出典:風評被害対策|Cyber Value(ロードマップ社)
出典:サジェスト汚染対策|Cyber Value(ロードマップ社)
3. 投稿者・関係者との対話や法的対応支援
口コミの中には、誹謗中傷や虚偽の内容を含んだ悪質な投稿が見られることがあります。なかには、同業他社によるなりすましや、明らかに悪意をもった書き込みも存在します。
このようなケースでは、単に削除依頼をするだけでは不十分であり、投稿者の特定や法的措置を検討する必要があります。
当社では、Cyber Valueを通じて弁護士と連携し、発信者情報の開示請求、証拠保全、削除請求など、法的プロセスに基づいた対応を支援しています。
対応の遅れがさらなる風評被害や信用毀損につながる前に、専門的な対処を講じることで、企業のリスクを最小限に抑えることが可能です。
出典:フォレンジック調査・対策|Cyber Value(ロードマップ社)
出典:セキュリティ診断・対策|Cyber Value(ロードマップ社)
口コミ対策は「削除」だけで終わらせない
体験談ベースの口コミは、たった1件でも企業の信用や売上に大きな影響を与える時代です。
確かに、悪質な口コミは削除できる場合がありますが、それだけでは根本的なリスク解消にはつながりません。
放置による風評被害、検索サジェストの汚染、取引先や求職者からの信頼低下など、二次的な被害が連鎖する恐れもあります。
こうしたリスクに対応するには、削除対応に加えて複合的な対策が必要です。
- ネット上の情報を監視する体制
- 検索環境の健全化
- 必要に応じた法的支援
当社が提供するCyber Valueでは、これらの課題に対応するためのサービスを一貫してご提供しています。
悪評に振り回されないためにも、まずは現状のリスクを把握することから始めませんか?
無料相談・資料請求を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
「うちの会社が…?」サジェスト汚染・誹謗中傷が引き起こす法的措置と今すぐできる対策
よって、一瞬にしてその価値を失う危険性を孕んでいます。
一度ネガティブな情報がインターネット上に拡散されると、それは検索エンジンやSNSを通じて誰もが容易にアクセスできる“公知の事実”として扱われ、企業の社会的信用を大きく損ないます。さらに、こうした事態は単なるイメージダウンにとどまらず、名誉毀損罪や信用毀損罪といった刑事罰、あるいは民事上の損害賠償請求といった法的措置に発展する事例も決して珍しくありません。
この記事では、「知らないうちに自社のブランドが傷つけられていた」という最悪の事態を未然に防ぐため、企業が直面する具体的なデジタルリスクとその法的問題を深掘りします。そして、今すぐ着手できる実践的な対策とともに、デジタルリスク対策の専門集団であるCYBER VALUEが提供する包括的な支援策について、詳細にご紹介します。
第1章 公知化する企業リスクとその法的意味合い
1.1 サジェスト汚染・SNS炎上の深刻な実態
企業が直面する評判リスクの中でも、特に警戒すべきが「サジェスト汚染」と「SNSでの炎上」です。
サジェスト汚染とは、Googleなどの検索エンジンで企業名を入力した際に、検索候補(サジェスト)として「〇〇株式会社 ブラック」「〇〇商事 倒産」「〇〇クリニック 医療ミス」といった、ネガティブな印象を与えるキーワードが自動的に表示されてしまう現象を指します。これは、多くのユーザーがその組み合わせで検索していることを反映した結果ですが、たとえ事実無根であっても、検索した第三者に対して強烈な先入観を与え、企業活動における深刻な障壁となります。
一方、SNSでの炎上は、たった一つの不適切な投稿や顧客からのクレームが、X(旧Twitter)やInstagramなどのプラットフォーム上で爆発的に拡散し、数時間のうちに収集のつかない事態へと発展する現象です。その火種は、従業員の不注意な投稿、サービスの不備、内部告発など多岐にわたりますが、一度炎上すると、事実関係の真偽にかかわらず、企業の社会的信用は大きく毀損されます。
1.2 「公知化」が引き起こす法的措置の具体的内容
ネット上に拡散された誹謗中傷やネガティブな情報が放置された場合、企業は深刻な法的リスクに直面します。主に問題となるのは、刑法上の「名誉毀損罪」「信用毀損罪」、そして民法上の「プライバシー侵害」です。
名誉毀損罪(刑法第230条)
これは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立する犯罪です。ポイントは、記載された内容が事実か嘘かに関わらず成立し得るという点です。「A社は過去に法令違反で行政指導を受けた」という内容が事実であっても、それを不特定多数が見られるネット上に書き込む行為は、企業の社会的評価を低下させるため、名誉毀損に該当する可能性があります。
信用毀損罪(刑法第233条)
こちらは、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損」した場合に成立します。名誉毀損罪と異なり、嘘の情報であることが成立要件です。「B社は倒産寸前だ」といった虚偽の情報を流布し、企業の経済的な支払い能力や製品・サービスの品質に対する信頼を傷つける行為がこれにあたります。サジェスト汚染が原因で取引が停止された場合などは、この罪が問われる可能性があります。
プライバシー侵害(民法709条:不法行為責任)
こちらは刑事罰ではなく、民事上の損害賠償責任を問うものです。「公開されたくない私生活上の事実」が本人の許可なく公開され、精神的苦痛を受けた場合に成立します。企業でいえば、未公開の内部情報や従業員の個人情報などがこれに該当し、漏洩させた相手に対して損害賠償を請求することが可能です。
これらの法的措置を取るためには、まず誹謗中傷を行った「発信者」を特定する必要があります。そのための手続きが発信者情報開示請求であり、プロバイダ責任制限法に基づいて行われます。この請求件数は年々増加しており、総務省のデータによれば、2022年度には約3,300件に上るなど、企業や個人がネット上の権利侵害に対して積極的に法的手段を講じる傾向が強まっています。
第2章 “情報拡散”から“法的トラブル”へ発展した事例シナリオ
ネット上の小さな火種が、いかにして企業の存続を揺るがす大きな法的トラブルへと発展するのか。ここでは、具体的なシナリオを通じてそのプロセスと二次被害の深刻さを解説します。
2.1 不祥事の炎上が「デジタルタトゥー」となり、経営を蝕む二次被害
ある地方の中堅建設会社で、一人の現場監督による下請け業者へのパワーハラスメントが、音声データと共に匿名でSNSに投稿されました。投稿は瞬く間に拡散し、「#〇〇建設ハラスメント」というハッシュタグと共に大手メディアもこの問題を取り上げ、大規模な炎上へと発展しました。
同社はすぐに謝罪声明を発表し、当該社員を懲戒解雇処分としましたが、問題はこれで終わりませんでした。
- サジェスト汚染による採用活動の停滞: Googleで社名を検索すると、サジェストに「ハラスメント」「ブラック」といった単語が表示されるようになりました。その結果、新卒採用の応募者数は前年の3分の1に激減し、内定を出した優秀な学生からも複数名辞退される事態となりました。
- 取引への悪影響: 炎上とサジェスト汚染を問題視した主要な取引先から、コンプライアンス体制の見直しを求められ、一部の新規契約が見送られました。金融機関からも融資条件の厳格化を示唆されるなど、事業運営に直接的な影響が出始めました。
- 株主からの追及: 上場企業ではなかったものの、出資者である地域の有力者たちから経営責任を厳しく追及され、経営陣の退任を求める声も上がりました。
一度ネットに刻まれた不祥事の情報は「デジタルタトゥー」として残り続け、鎮火したはずの炎上が、採用、取引、資金調達といった経営の根幹を、長期にわたって静かに蝕んでいくのです。
2.2 内部からの情報漏洩が、顧客と元従業員からのダブル訴訟に発展
あるITベンチャー企業で、待遇に不満を持っていた退職間近のエンジニアが、顧客管理システムの脆弱性を利用して数千件の顧客情報を不正に取得。その一部を匿名掲示板に暴露しました。
この「内部不正による情報漏洩」が公知となったことで、同社は二つの側面から法的措置を取られることになります。
- 顧客からの集団損害賠償請求: 情報を漏洩させられた顧客たちは、プライバシー侵害とセキュリティ管理の杜撰さを理由に、弁護団を結成。同社に対して民法709条の不法行為に基づく損害賠償を求める集団訴訟を提起しました。
- 元従業員との労務訴訟: 会社は情報漏洩を行った元エンジニアに対し、信用毀損と損害賠償を求めて提訴。しかし、元エンジニア側も「不当な労働環境が不正行為の原因だった」として、未払い残業代の支払いやパワーハラスメントに対する慰謝料を求める反訴を提起。事態は泥沼の労務訴訟へと発展しました。
この事例のように、内部の問題が外部に漏洩することで、顧客と元従業員という二つの方向から法的責任を追及される「ダブルパンチ」のリスクが存在します。企業規模の大小にかかわらず、内部統制の不備が外部の法的トラブルに直結する危険性は、すべての企業が認識すべきです。
第3章 なぜ“ネットの火種”は見過ごされてしまうのか?
多くの企業が、なぜネット上のリスクが深刻化するまで気づけないのでしょうか。そこには、特に中小企業が陥りやすい構造的な課題と、デジタル情報特有の性質が存在します。
3.1 「対岸の火事」と考える中小企業のモニタリング体制の不備
「炎上やサイバー攻撃なんて、有名な大企業の話だろう」という思い込みは、中小企業の経営者に根強く存在します。広報や法務の専門部署を持たない企業が多く、日々の業務に追われる中で、ネット上の評判を定常的に監視するリソースも意識も不足しがちです。
しかし、リスクの火種はX(旧Twitter)やニュースサイトのコメント欄だけにあるわけではありません。
- 匿名掲示板(5ちゃんねる等): 社員や元社員による内部情報の書き込みが最も多い場所の一つ。
- 転職口コミサイト: 企業の労働環境に関するリアル(時に不正確)な情報が蓄積されている。
- Q&Aサイト(Yahoo!知恵袋等): 製品やサービスに対する不満が、具体的な質問の形で投稿されている。
これらのプラットフォームは、一般的な検索では表面化しにくいため、企業が気づかないうちにネガティブな情報が大量に蓄積されているケースが多々あります。こうした“見えない場所”でくすぶる炎を放置している企業ほど、いざ火の手が上がった際の対応が遅れ、被害が深刻化するのです。
3.2 一度刻まれたデジタルタトゥーは自然には消えない
アナログの世界での噂話は時間と共に風化しますが、デジタル情報はそうはいきません。Googleなどの検索エンジンは、ユーザーにとって有益と判断した情報をインデックスし、半永久的に保存し続けます。サジェスト機能も、一度ネガティブなキーワードが定着すると、それが検索され続ける限り表示され続けます。
つまり、数年前に解決したはずの不祥事や、たった一度の炎上が、企業のブランドイメージを現在進行形で妨げ続けるという事態が発生するのです。これを自然に消えるのを待つのは、顔についた消えないインクを放置するようなものです。積極的な対策を講じない限り、デジタルタトゥーは企業の未来を縛り続ける足枷となります。
第4章 今すぐ始めたい!炎上・サジェスト汚染・情報漏洩の「予防」と「対策」
デジタルリスクは、もはや避けて通れない経営課題です。重要なのは、問題が発生してから慌てて対応するのではなく、日常的に「予防」し、万が一の際には迅速に「対策」できる体制を構築することです。ここでは、CYBER VALUEが提供する具体的なソリューションをご紹介します。
4.1 CYBER VALUEができること①:Web/SNSモニタリングによる「火種の早期発見」
すべての対策の第一歩は、リスクの兆候をいち早く察知することです。
Web/SNSモニタリングは、SNS、ブログ、匿名掲示板、ニュースサイトのコメント欄など、インターネット上の膨大な情報を24時間365日体制で監視し、事前に設定したキーワード(会社名、商品名、役員名など)に関連する投稿をリアルタイムで収集・分析するサービスです8。
- 早期発見: 「製品に欠陥がある」「従業員の態度が悪い」といったネガティブな書き込みや、炎上の兆候を発生初期の段階で検知します。
- 迅速な初動対応: 危険度が高い投稿が検知されると、即座にアラートで担当者に通知。これにより、事実確認や公式声明の発表といった初動対応の遅れを防ぎ、被害の拡大を最小限に抑えることが可能です。
- 客観的な状況把握: 自社がネット上でどのように語られているかを客観的なデータで把握し、経営判断の材料とすることができます。
4.2 CYBER VALUEができること②:サジェスト汚染・風評被害対策による「ブランドイメージの回復」
すでにネガティブな情報が拡散してしまっている場合には、専門的なアプローチによるイメージ回復が必要です。
サジェスト汚染対策では、まずネガティブなサジェストが表示される原因を調査します。その上で、ポジティブな情報を発信するなどして検索行動を健全な方向へ誘導する逆SEOの手法を用い、ネガティブなキーワードの表示順位を押し下げ、最終的に非表示にすることを目指します。
風評被害対策では、ネット上に拡散された事実無根の悪質な記事や投稿に対し、正当なプロセスに則ったアプローチを行います。サイト運営者への削除依頼はもちろん、それが受け入れられない場合には、提携する弁護士を通じて裁判所に削除を求める仮処分申し立てを行うなど、法的な手段も視野に入れた対応が可能です。
4.3 CYBER VALUEができること③:フォレンジック調査・セキュリティ対策による「証拠保全と再発防止」
情報漏洩や社内不正、サイバー攻撃といったインシデントが発生した際には、原因究明と証拠保全が極めて重要になります。
デジタル・フォレンジック調査とは、PCやサーバー、ネットワーク機器などに残されたデジタルデータを収集・分析し、不正アクセスの経路や情報漏洩の範囲、犯人の行動などを法的な証拠として明らかにする科学的な調査手法です。CYBER VALUEでは、この調査を通じて、法的措置の準備を整えるとともに、インシデントの根本原因を特定し、実効性のある再発防止策の構築までを支援します7。
また、インシデントを未然に防ぐ「予防」の観点から、セキュリティ診断(脆弱性診断)も提供しています。専門家が企業のWebサイトや社内ネットワークを擬似的に攻撃し、セキュリティ上の弱点(脆弱性)を洗い出します。これにより、潜在的なリスクを可視化し、攻撃を受ける前に対策を講じることが可能になります。
まとめ:企業の名誉と信頼を守るのは、初動対応と“情報の可視化”
炎上、サジェスト汚染、情報漏洩といった企業の信頼を根底から揺るがすデジタルリスクは、その多くが経営者の“見えない場所”で静かに進行しています。そして、それらの火種が「検索」や「SNS」を通じて、誰もがアクセスできる公知情報へと変わった瞬間、名誉毀損や信用毀損といった法的措置に発展するリスクは一気に高まります。
企業の名誉とブランド価値を守るために最も重要なのは、第一に「見えにくいリスクを可視化する」ための常時監視体制、そして第二に、万が一問題が発生した際に被害を最小限に食い止めるための「迅速な初動対応」です。
CYBER VALUEは、リスクの早期発見から、拡散された情報の削除、法的手続きの支援、さらにはインシデントの根本原因を究明するフォレンジック調査まで、企業が直面するあらゆるデジタルリスクに対して予防・対処・回復を一貫してサポートできる専門体制を整えています。
Q&Aよくある質問
Q1サジェスト対策はどのくらいで効果が出ますか?
キーワードにもよりますが、早くて2日程度で効果が出ます。
ただし、表示させたくないサイトがSEO対策を実施している場合、対策が長期に及ぶおそれもあります。
Q2一度見えなくなったネガティブなサジェストやサイトが再浮上することはありますか?
再浮上の可能性はあります。
ただ、弊社ではご依頼のキーワードやサイトの動向を毎日チェックしており、
再浮上の前兆がみられた段階で対策を強化し、特定のサジェストやサイトが上位表示されることを防ぎます。
Q3風評被害対策により検索エンジンからペナルティを受ける可能性はありませんか?
弊社の風評被害対策は、検索エンジンのポリシーに則った手法で実施するため、ペナルティの心配はありません。
業者によっては違法な手段で対策をおこなう場合があるため、ご注意ください。
Q4掲示板やSNSのネガティブな投稿を削除依頼しても受理されないのですが、対応可能ですか?
対応可能です。
弁護士との連携により法的な削除要請が可能なほか、投稿者の特定や訴訟もおこなえます。
Q5依頼内容が漏れないか心配です。
秘密保持契約を締結したうえで、ご依頼に関する秘密を厳守いたします。
Q6他社に依頼していたのですが、乗り換えは可能ですか?
可能です。
ご依頼の際は他社さまとどのようなご契約、対応がなされたのかをすべてお伝えください。
Q7セキュリティ事故発生時にはすぐ対応していただけますか?
はい。緊急時には最短即日でフォレンジックを実施いたします。


