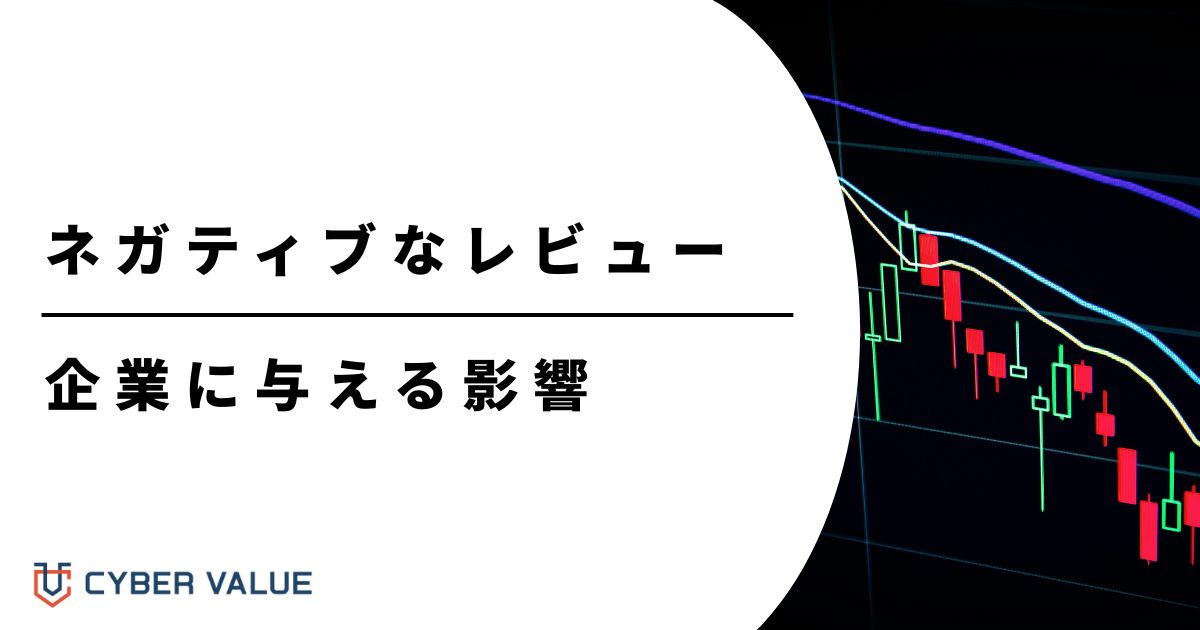口コミ削除はできる?ネガティブなレビューが企業に与える影響と正しい対処法
Googleマップやレビューサイトに書かれた口コミは、企業の信用に大きく関わります。
体験談ベースの悪評はたった1件でも検索上位に表示され、ビジネスに深刻な影響を与える可能性があります。
しかし、すべての口コミが削除できるわけではなく、誤った対応をすると炎上や信頼低下につながるおそれもあります。
そこで本記事では、口コミ削除の可否や企業がとるべき対応策について詳しく解説します。
記事を読むことで、悪質な口コミから企業を守るために必要な考え方と具体的な対処法がわかります。
ぜひ最後までご覧いただき、貴社のリスク管理にお役立てください。
口コミのレビューが企業にもたらす深刻なリスク
インターネット上の口コミは、企業の信用や売上に直結する時代です。
体験談に基づいた否定的な口コミは、閲覧者に強い印象を与え、購買行動に大きく影響します。
実際、総務省の調査によると、約60%の消費者がネットの口コミを購買判断の材料にしていると報告されています。
たった一件のレビューでも、「信頼性のある実体験」として広がり、以下のような事態に発展する恐れがあります。
- 新規顧客の離脱(レビュー閲覧後に問い合わせや来店を断念)
- 検索結果上にネガティブ情報が残り、企業ブランドの毀損
- SNSやまとめサイトで拡散し、風評被害に発展
こうしたリスクを未然に防ぐには、口コミを「監視し、削除し、対応する」という3つの視点が必要です。
口コミは削除できる?基本の判断基準
Googleマップやレビューサイトに投稿された体験談は、検索結果で上位に表示されることもあります。
ネガティブな口コミを放置していると、ビジネスに大きなダメージを与える可能性があります。
「悪い口コミを削除したい」と考える企業は多いものの、実際には削除できるものとできないものが明確に分かれています。
ここでは、Googleや主要なレビューサイトの削除ルール、そして削除が認められる悪質な口コミの具体例を紹介します。
Googleやレビューサイトの削除ルールとは
Googleマップの口コミ削除の可否は、Googleの「投稿コンテンツに関するポリシー」に沿って判断されます。
削除の対象となるのは、主に以下のような内容です。
これらの違反が確認できれば、Googleの管理画面から「不適切な口コミを報告」することで、削除対応が検討されます。
ただし、「接客態度が気に入らなかった」「料理が口に合わなかった」といった体験に基づく主観的な意見は、たとえ企業側が不当と感じても削除対象にはならないことが多い点に注意が必要です。
たとえ企業側が不当だと感じても、ユーザーが実際にサービスを利用したうえでの意見であれば、削除のハードルは高いのが現実です。
「削除できる」悪質口コミの具体例
虚偽情報や誹謗中傷、スパム行為などの「ルール違反」が明確であれば、削除される可能性はあります。
以下に、実際に削除対象となる可能性が高い口コミの例を挙げます。
例1:第三者による誹謗中傷
「この店は最低。オーナーの○○ってやつ、犯罪者かと思った。」
他人の人格を否定したり、名誉を傷つけるような表現は、人身攻撃・名誉毀損としてポリシー違反に該当する可能性があります。
例2:競合店によるなりすまし投稿
「商品が全部偽物だった。対応も最悪。」
実際には来店していない人物による投稿や、意図的に企業イメージを貶める虚偽内容は、報告・削除の対象となり得ます。
例3:同一人物による連投スパム
「もう2度と行かない!」「最悪!接客がひどい!」(※数分おきに複数回投稿)
同一人物が短時間に何度も投稿している場合、スパム投稿とみなされる可能性があります。GoogleはAIと人力審査の両方でスパム検知を行っています。
例4:レビューと関係ない投稿
「この近くの道路は渋滞がひどくて最悪」
店舗・サービスとは関係のない話題は、レビューの本来の趣旨に反しており、削除申請が通る可能性があります。
ただし、これらの投稿が削除されるかどうかは、投稿の文面・背景・証拠資料の有無によって変わるため、確実な削除を求める場合は、専門家のサポートが不可欠です。
削除依頼の判断を誤ると、かえって投稿者とのトラブルやSNSでの逆炎上に発展する恐れもあります。
削除の判断に迷った際は、まずガイドラインを熟読したうえで、外部の専門業者に相談するのが賢明です。
出典:デジタル庁|「インターネット上の誹謗中傷に関する制作パッケージ」に基づく取り組み
口コミ削除だけで解決しない?放置NGな3つの理由
口コミの削除は確かに有効な対策ですが、それだけでは根本的な解決にならない可能性もあります。
まずは、ネガティブな口コミを放置するリスクを理解することが重要です。
1. 拡散スピードが早すぎる
SNSやネット掲示板では、ネガティブな口コミがまたたく間に拡散される傾向があります。
体験談ベースの投稿は「リアルな証言」として受け取られやすく、共感を呼び、リポストや引用の連鎖で一気に広がっていきます。
たとえ投稿が削除されたとしても、炎上が始まった後では、まとめサイトやSNS投稿で二次拡散が進行してしまい、情報の回収が困難になるリスクがあります。
2. サジェストや検索結果に悪影響が出る
ネガティブな口コミが長期間ネット上に残ると、Google検索のサジェスト(関連検索ワード)や検索結果に悪影響を与えます。
たとえば、「会社名 詐欺」や「店舗名 ひどい」といったキーワードがサジェストに表示されると、悪評に注目が集まる構造が生まれます。
3. 顧客・取引先からの信頼低下につながる
悪質な口コミは、消費者だけでなく、取引先や求職者の印象にも影響します。
企業名で検索したときに悪評が出てくると、会社の信頼を疑われ、商談や提携の見送りにつながることもあります。
採用面でも、職場の評判を見た応募者が離脱するケースは少なくありません。ネット上の印象が、信用や人材確保に直結する時代です。
口コミ削除だけではない!企業の正しい対応とは?
悪質な口コミや風評被害に対しては、削除対応だけでなく、事前の監視と継続的な対策が重要です。
ここでは、当社が提供するCyber Valueの具体的なサポート内容をご紹介します。
1. Web・SNSモニタリングで早期発見
ネット上の口コミやSNSの投稿は、拡散する前の早期対応が重要です。
Cyber Valueでは、WebメディアやSNSを24時間体制でモニタリングし、問題の兆候をリアルタイムで検知します。
不満や批判が表面化した直後に動くことで、後手に回る炎上リスクや、長期的な風評被害を最小限に抑えることができます。
出典:Web/SNSモニタリング|Cyber Value(ロードマップ社)
2. 風評被害対策と検索結果クリーンアップ
当社では、検索環境全体を分析し、ネガティブなコンテンツが目立たない構成へと整える施策を実施しています。
企業にとって好ましい情報を適切に発信・強化することで、検索結果のバランスを取り戻します。
また、検索サジェストに表示される「企業名+詐欺」「店舗名+トラブル」といったキーワードが自然と消えていくよう、検索エンジンの仕組みに即したサジェスト対策も行っています。
風評の火種を見逃さず、検索画面全体を健全な状態に保つことで、ブランドの信頼性を長期的に守ることが可能です。
出典:風評被害対策|Cyber Value(ロードマップ社)
出典:サジェスト汚染対策|Cyber Value(ロードマップ社)
3. 投稿者・関係者との対話や法的対応支援
口コミの中には、誹謗中傷や虚偽の内容を含んだ悪質な投稿が見られることがあります。なかには、同業他社によるなりすましや、明らかに悪意をもった書き込みも存在します。
このようなケースでは、単に削除依頼をするだけでは不十分であり、投稿者の特定や法的措置を検討する必要があります。
当社では、Cyber Valueを通じて弁護士と連携し、発信者情報の開示請求、証拠保全、削除請求など、法的プロセスに基づいた対応を支援しています。
対応の遅れがさらなる風評被害や信用毀損につながる前に、専門的な対処を講じることで、企業のリスクを最小限に抑えることが可能です。
出典:フォレンジック調査・対策|Cyber Value(ロードマップ社)
出典:セキュリティ診断・対策|Cyber Value(ロードマップ社)
口コミ対策は「削除」だけで終わらせない
体験談ベースの口コミは、たった1件でも企業の信用や売上に大きな影響を与える時代です。
確かに、悪質な口コミは削除できる場合がありますが、それだけでは根本的なリスク解消にはつながりません。
放置による風評被害、検索サジェストの汚染、取引先や求職者からの信頼低下など、二次的な被害が連鎖する恐れもあります。
こうしたリスクに対応するには、削除対応に加えて複合的な対策が必要です。
- ネット上の情報を監視する体制
- 検索環境の健全化
- 必要に応じた法的支援
当社が提供するCyber Valueでは、これらの課題に対応するためのサービスを一貫してご提供しています。
悪評に振り回されないためにも、まずは現状のリスクを把握することから始めませんか?
無料相談・資料請求を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。