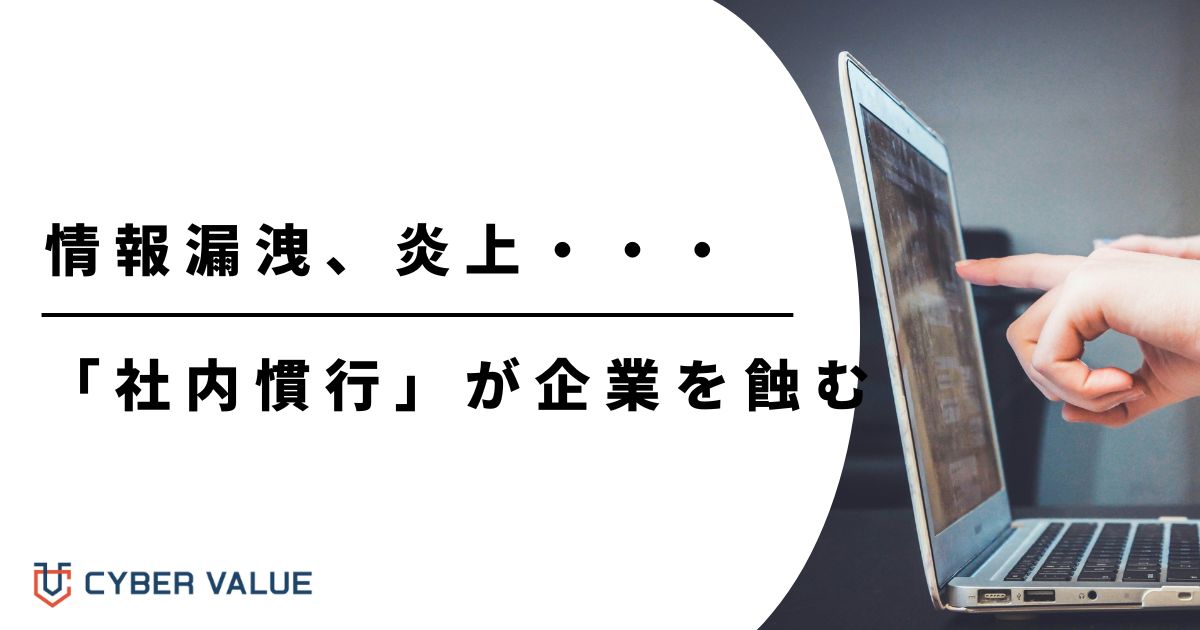【自社の盲点】情報漏洩、炎上、サイバー攻撃…見過ごしてきた「社内慣行」が企業を蝕む
「情報漏洩?」「炎上?」「サイバー攻撃?」—これらは、大企業やIT企業だけが直面する他人事だと思っていませんか?
実は、多くの企業が気づかないうちに、「自社の行動や慣行」の中に深刻なリスクの種を抱えています。 外部からの攻撃だけでなく、自らの手で生み出した「見えない盲点」が、事業継続を脅かし、ブランドイメージを破壊する原因になっているのです。
本記事では、このような自社起因の重大なリスクについて、具体的なデータや事例を交えて解説します。これらのリスクがあなたの企業にもたらす深刻な影響を理解し、手遅れになる前に適切な対策を講じる重要性をお伝えします。
なぜ「自社の慣行」がリスクになるのか?:知られざる内部要因
企業を取り巻くリスクは多岐にわたりますが、特に「自社の直接的な行動や会社の慣行」が原因となるケースは少なくありません。
例えば、情報・技術関連のリスクであれば、システムの脆弱性だけでなく、社員のセキュリティ意識の低さやデータ管理のずさんさが、情報漏洩やサイバー攻撃の足がかりとなることがあります。
「これは昔からこうだから」「まさかウチの会社は」といった見過ごされた慣行が、いかに深刻な事態を招くか、具体的なデータと事例で見ていきましょう。
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査によると、内部不正経験者の約6割が「うっかり違反した」「ルールを知らずに違反した」と回答しており、故意ではない「うっかり」による情報セキュリティインシデントが多いことが分かっています。
参照:IPA「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査」報告書
- 企業におけるソーシャルメディアリスクには、「風評リスク」と「情報漏えいリスク」があり、社内関係者の発言が原因となる情報漏えいリスクが、風評リスクに繋がる事例も多く見られます。
参照:企業におけるソーシャルメディアリスク管理 – 野村総合研究所「知的資産創造」
簡潔な実例:
- 事例1:安易なSNS投稿が招いた炎上
飲食店従業員による、不適切な行為を撮影した動画のSNS投稿が発端となり、企業イメージが損なわれ、多額の損失が発生した事例が報告されています。これは「社員が勝手にやったこと」では済まされない、SNS利用に関する社内ルールや教育の不足が招いた事態です。
参照:第6回:SNSリスク対策編 | 中小タスクが行く! – J-Net21
- 事例2:ずさんなデータ管理による情報流出
ある公的機関では、元従業員による情報持ち出しの可能性が発表されています。これは、従業員のシステムアクセス権限の適切な管理が、いかに重要であるかを示す事例です。
参照:「中小企業等事業再構築促進事業」における採択者情報の不正持出の疑いについて
- 事例3:古いシステムが招いたサイバー攻撃 2003年に発生した「SQLスラマー」ワームは、マイクロソフト社のSQLサーバーの脆弱性を狙ったものです。発生後わずか数分で数万台のコンピューターに感染が広がり、大規模なトラフィック障害をもたらしました。これは、ソフトウェアの脆弱性を放置し、最新のパッチ適用を怠ったことなど、セキュリティ対策の軽視が招いた結果です。
参照:サイバー攻撃の歴史 過去どのような攻撃がおこなわれたのか【連載 第2回(全4回)】 – ESET
これらの事例は、決して特別なことではありません。あなたの会社にも、潜在的なリスクとして潜んでいる可能性はないでしょうか?
【タイプ別解説】あなたの企業を蝕む「社内慣行」由来のリスク
企業の評判を揺るがす「評判・コンプライアンス関連リスク」
不祥事と風評被害
不祥事の発覚は、企業の株価を大きく下落させ、顧客離れによる売上減など、事業に致命的な影響を与えます。金融庁の調査では、企業が不祥事を自らアナウンスした場合、市場がその行動を評価するという分析もありますが、不祥事そのものの影響は避けられません。
参照:金融不祥事と市場の反応 ―上場保険会社に関するイベントスタディー―1 – 金融庁
自社慣行との関連: 不祥事の背景には、ハラスメントを放置する社風、内部告発制度の不備、あるいは利益至上主義による倫理観の欠如といった、長年にわたる社内慣行や隠蔽体質が潜んでいることが少なくありません。
情報漏洩・プライバシー侵害
顧客情報や企業秘密の漏洩は、企業に甚大な損害をもたらします。IPAの調査では、中小企業における過去3期内のサイバーインシデントによる被害額の平均は73万円ですが、ウェブサイトからの個人情報漏洩では平均2,955万円(クレジットカード情報含む場合は3,843万円)に上るという報告もあります。
参照:2024年度 中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査 – IPA
自社慣行との関連: 社員のセキュリティ意識の低さ、退職者のアカウントを放置するずさんな管理体制、あるいは許可されていないソフトウェアを使用するシャドーITの横行などが、情報漏洩の温床となります。
SNS炎上・マスコミ対応の失敗
SNSでの批判や中傷は瞬く間に拡散され、企業のブランドイメージを著しく毀損します。広報対応の遅れや不適切さは、火に油を注ぎ、取り返しのつかない結果を招くこともあります。ある回転寿司チェーン店での従業員による不適切動画の投稿では、およそ30億円もの被害損失が生じたと言われています。
参照:従業員によるSNS上の不適切発言問題で会社ができる3つのこと – 企業法務弁護士ナビ
自社慣行との関連: SNSガイドラインの不在、危機管理広報体制の未整備、社員へのメディアリテラシー教育不足など、社内の意識のズレが炎上リスクを高めます。
事業継続を脅かす「情報・技術関連リスク」
データの消滅・紛失・逸失
重要なデータが失われることは、事業運営の停止を意味します。IPAの調査では、中小企業におけるサイバーインシデント発生時の復旧までに要した期間の平均は5.8日であり、最悪の場合、事業の継続が困難になることもあります。
参照:「2024年度中小企業等実態調査結果」速報版を公開 | プレスリリース – IPA
自社慣行との関連: データ管理ルールの不在、バックアップ体制の不備、そして社員のITリテラシー不足による誤操作などが、このリスクを増大させます。
「自社の甘さ」につけ込まれるサイバー攻撃
外部からのサイバー攻撃も、その多くは企業のセキュリティ体制の脆弱性や管理の甘さにつけ込まれています。セキュリティ投資の軽視、最新のパッチ適用遅れ、社員へのセキュリティ教育不足、安易なパスワード管理などが、攻撃者にとっての「入り口」となります。
IPAの調査によると、サイバーインシデントが発生した企業における被害額の平均は73万円ですが、ランサムウェア感染の場合の被害額平均は2,386万円と報告されており、被害の規模は甚大です。また、サイバー攻撃を受けた企業の約7割が取引先にも影響が及んだと回答しており、「サイバードミノ」の危険性も指摘されています。
参照:「2024年度中小企業等実態調査結果」速報版を公開 | プレスリリース – IPA 参照:事務局説明資料 第10回 産業サイバーセキュリティ研究会 ワーキンググループ2(経営・人材・ – 経済産業省
手遅れになる前に!「見えないリスク」を洗い出す方法と対策
ここまで見てきたように、あなたの企業を蝕むリスクの多くは、外敵によるものだけでなく、自社の行動や長年の慣行の中に潜んでいる可能性があります。「何から始めればいいか分からない」と感じるかもしれません。
しかし、これらの「見えないリスク」を特定し、適切な対策を講じることが、企業を守る第一歩です。
ロードマップのCYBER VALUEは、まさにこのような「自社起因のリスク」の診断と対策を支援します。
- Web/SNSモニタリング、風評被害対策、サジェスト汚染対策: 不祥事の兆候やSNS炎上、風評被害を早期に発見し、迅速な対応を可能にします。社員の不適切投稿なども監視し、社内教育の強化にも繋がります。
- セキュリティ診断・対策: セキュリティ対策の第一歩という位置づけで、ホームページの脆弱性を認識していただき、セキュリティ対策方針の検討材料としてのご 活用いただけます。
- フォレンジック調査・対策: 万が一、ホームページやメールで情報漏洩や不祥事が発生した場合でも、原因究明、証拠保全。法令遵守の観点から適切な対応を支援し、再発防止策の立案までを行います。
私たちCYBER VALUEは、単なる外部からの対策だけでなく、「自社起因のリスク」の診断・対策が可能です。専門家による包括的なサポートで、自社だけでは気づけない盲点を洗い出し、企業価値を守るための強固な基盤を築きましょう。
まとめと次のアクション:今すぐ、御社の「盲点」をCyber Valueで診断しませんか?
「まだ大丈夫」という根拠のない自信は、いつか大きな代償となって返ってくるかもしれません。自社の行動や慣行が、企業の致命的なリスクとなりうることを忘れないでください。
手遅れになる前に、専門家による客観的な診断と対策が必要です。 ロードマップ社のCYBER VALUEが、貴社の現状に合わせた最適なリスク対策プランをご提案し、企業価値を守るお手伝いをいたします。