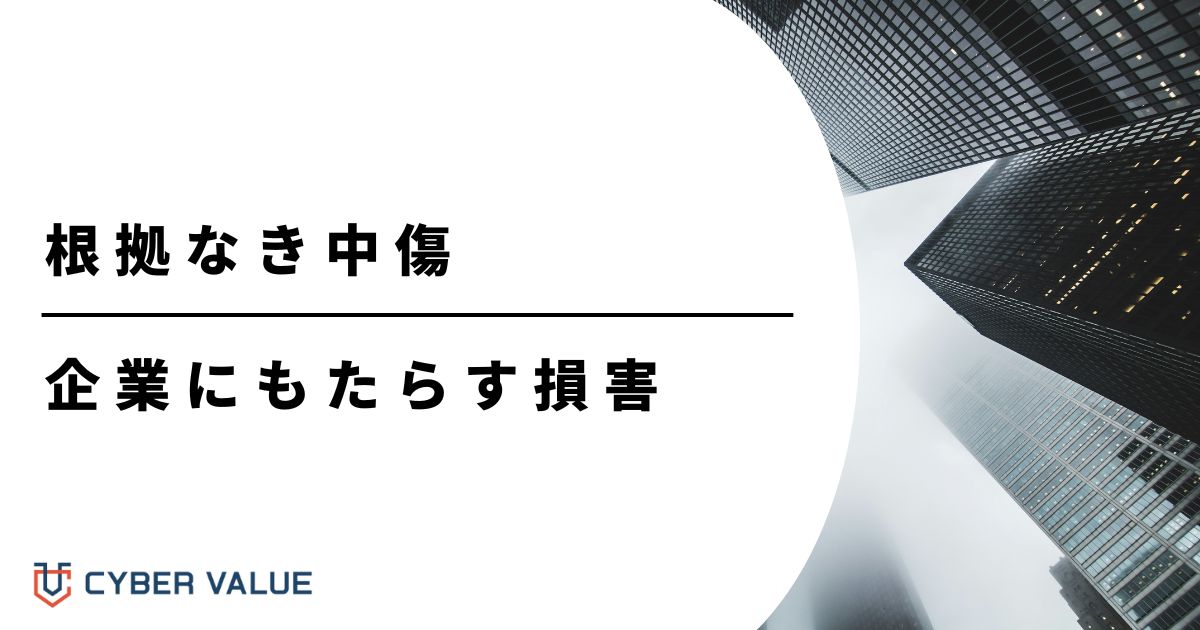その悪評は本当に事実?根拠なき中傷が企業にもたらす損害と取るべき一手
その悪評は本当に事実ですか?
SNSや掲示板、検索サジェストなど、あらゆるネット上の「声」が企業活動に影響を与える時代。たとえ根拠のない中傷でも、ユーザーの印象や判断を大きく左右するため、事実ではない悪評が信用失墜や売上低下などの深刻な風評被害に発展することがあります。
実際、総務省調査によるとインターネット利用者の約80%以上がSNSを日常的に使用しており、企業に関する情報もSNS経由で拡散・消費されやすいのが現状です。
本記事では、企業が直面する「根拠なき風評被害」のリスクと実態、そしてそれに備えるための具体策として、Cyber Valueが提供する実効性の高いソリューションをご紹介します。
風評被害とは?なぜ根拠なき悪評が企業を揺るがすのか
風評被害は「根拠のない評判や噂」が社会的・経済的損失を招くリスクであり、企業にとって無視できない存在です。
近年はSNSや検索結果の影響力が高まり、悪意ある投稿や誤解に基づいた口コミが、瞬時に企業のイメージにダメージを与える時代となっています。
とくに問題なのは「事実ではない」中傷が、印象という形で社会に定着してしまうこと。ユーザーや取引先、求職者の心理にネガティブな影を落とし、営業機会の損失や採用難、株価下落といった連鎖的損害につながる可能性すらあります。
風評被害の定義と特徴
風評被害とは、正当な根拠のない情報・噂・中傷によって、個人や企業が社会的・経済的に損害を被る現象を指します。
法律上の明確な定義はありませんが、総務省の資料や法務省の取り扱いにおいても「事実無根の評判」によって信用や利益が損なわれることとして扱われてるのです。
たとえば、以下のようなケースが風評被害に該当します。
- SNSでの虚偽の書き込みによって「ブラック企業」と認識される
- 掲示板での事実無根な投稿が検索結果に残り続ける
- 商品名とともに「危険」「偽造品」などのサジェストが表示される
このように、一見小さな“声”でも、ネット上では拡散・保存され続けることで持続的な悪影響を及ぼすのが、風評被害の厄介な点です。
SNS・検索経由で拡散する「根拠のない悪評」の実態
かつてはテレビ報道や新聞記事が「世間の声」としての主な情報源でしたが、現在ではSNSや掲示板、検索エンジンが人々の印象を大きく左右する情報源となっています。特にX(旧Twitter)やInstagram、匿名掲示板、Google検索などでは、一部の個人の投稿が爆発的に拡散されるという特徴があります。
実際の調査でも、こうした風評の拡散リスクが顕著に表れています。たとえば、2023年に実施された調査によると、企業に関するネガティブ情報が「実際にはデマや噂だった」と認識した人は34.1%にのぼり、そのうち41.7%が購買行動に影響を受けたと回答しています。
(参考:株式会社エフェクチュアル「インターネット上の風評被害に関する意識調査」)
また、ネガティブ情報を「拡散した経験がある」と回答した人は9.9%。さらに、風評が拡散されやすい情報源としては、検索エンジン(70.5%)、X(50.5%)、ネットニュース(45.2%)が上位に挙がっており、企業にとって無視できない存在となっています。
(参考:株式会社エフェクチュアル「インターネット上の風評被害に関する意識調査」)
さらに厄介なのが、Googleで企業名を検索したときに表示される「関連キーワード(サジェスト)」です。
たとえば、下記のようなワードが表示されるだけで、ユーザーはそれが事実かどうかにかかわらず、不安を抱いて離脱する傾向が強まります。
- 「○○ ブラック」
- 「○○ 詐欺」
- 「○○ やばい」
こうした検索結果の印象が、採用活動や取引、消費者の購入行動にまで影響するため、企業は根拠のない悪評であっても放置できない時代に入っているといえるでしょう。
SNSや検索エンジンが無言の口コミや信頼フィルターとして機能している今、ネガティブな印象は瞬時に拡散し、企業イメージに深刻なダメージを与えるリスクとなっています。
「事実無根でも企業が損害を受ける」理由とは?
企業に対する悪評や中傷がたとえ事実無根であっても、現代の社会では「火のないところに煙は立たぬ」と受け取られがちです。つまり、情報の真偽よりも「どのように受け取られるか」「ネット上でどう見えるか」が、企業へのダメージを左右する時代なのです。
以下は、根拠のない悪評であっても企業が実際に被る損害の代表例です。
採用活動への影響
企業の評判は、求職者の応募意思や入社後の定着率に直結します。2024年の調査では、「口コミサイトを必ず見る」と回答した人が20.9%、「時々見る」が31.3%で、実に半数以上(52.2%)が企業の評判を事前に確認していることがわかっています。
(参考:ベイジ「中途採用における採用サイト利用実態調査」)
さらに、口コミを見て応募・選考・内定を辞退したことがある人は67%にものぼっており、ネガティブな印象が人材確保に深刻な影響を及ぼしていることが浮き彫りになっています。
(出典:PR TIMES)
顧客・取引先からの信用低下
悪評が事実かどうかに関わらず、“疑わしきは避ける”という心理が働くのがBtoB/BtoCの世界です。
- 「あの会社、炎上してたらしい」
- 「口コミが悪かった」
という“なんとなくの印象”が、購買・契約・提携の見送りにつながるケースは少なくありません。とくに法人取引では、「風評リスク=取引リスク」と捉えられることが多く、数千万円〜数億円単位の商談がキャンセルされる事例も報告されています。
株価や資金調達への影響
上場企業や資金調達中の企業にとって、風評リスクは極めて重大な「信用コスト」になります。SNSでの中傷が一気に炎上すれば、記者や株主が注目し、メディア報道につながる恐れも。
それにより、下記のような直接的かつ長期的な打撃を受ける可能性があります。
- 株価の急落
- 投資家や金融機関からの評価悪化
- 資金調達の失敗
「放置」で悪評が半永久的に残る
一度ネットに出た情報は、たとえ事実無根でも削除が難しく、キャッシュ・コピー・まとめサイト等で再拡散されやすいという特性があります。
しかも、Google検索では古い情報でも上位に残りやすく、悪評が企業の顔として表示され続ける状態になってしまいます。
つまり、「事実ではないから大丈夫」と放置すればするほど、企業ブランドがジワジワと損なわれていくのです。
このように、「根拠のない悪評」であっても、企業は人材、顧客、取引、信用、収益といったあらゆる面で損失を被る可能性があります。次章では、実際に起こり得る風評被害のシナリオと、それが企業にもたらす具体的なリスクを詳しく見ていきます。
風評被害による企業の具体的なリスクとは
風評被害は「ただのネットのうわさ話」で済むものではありません。現代では、企業の信用・売上・採用・株価にまで波及する経営リスクとして、真剣に捉える必要があります。
本章では、実際に企業が風評被害によって被り得る代表的な損害を、より具体的に解説していきます。
取引中止・売上減少などの直接的損害
根拠のない悪評や誤解に基づく投稿がSNSや口コミサイトで拡散されると、「この企業と関わって大丈夫か?」という不安が取引先や顧客の間に広がります。
これにより、下記のような直接的な経済的損失が生じるリスクがあります。
- 商談のキャンセル
- 既存契約の見直し
- 商品やサービスの購入中止
- 問い合わせや予約の激減
ある中堅製造業では、掲示板に「不正納品の噂」が匿名で書き込まれたことがきっかけで、複数の取引先から契約保留を言い渡され、売上が1か月で20%減少したという実例も報告されています。
採用難・離職率の増加
先に述べたように、企業の評判は採用にも直結します。企業名で検索した際に「ブラック」「パワハラ」「炎上」などのサジェストが表示されたり、悪評が上位表示されていると、求職者は応募をためらいます。
また、入社後も「やっぱり噂どおりだったのでは」と不安を抱え、早期退職につながるケースも。
採用活動への影響は短期的な人手不足にとどまらず、育成コストや業務品質の低下といった長期的損害を招くリスクもあります。
株主・投資家からの評価低下
株式市場に上場している企業、あるいは資金調達中のスタートアップにとって、風評被害は投資判断に直結する要素です。
仮に悪評が誤情報だったとしても、「イメージが悪い」「ネットで炎上している」といった理由で下記のような影響が出ることは、決して珍しくありません。
- 株価の下落
- 株主の売却
- 出資の見送り
信用の毀損は、資金調達コストを上昇させる「見えにくい損失」でもあるのです。
従業員や家族への精神的影響
風評被害は、社外だけでなく社内にも波及します。
- 社員が「会社の評判が悪い」と言われて気まずい思いをした
- 家族が心配して転職をすすめてきた
- 自社の対応に不信感を抱いてモチベーションが低下した
上記のようなケースは、精神的なストレスだけでなく従業員エンゲージメントの低下や離職にもつながります。
つまり、企業としての「内なる力=人的資産」も、風評リスクによって損なわれるのです。
風評被害を防ぐために企業がとるべき対応策
「事実ではないから放っておいても問題ない」と考えるのは、風評被害リスクへのもっとも危険な誤解です。ネット上に拡散された悪評は、放置すればするほど影響が拡大し、回収不能になる可能性が高まります。
企業がこのリスクに真正面から立ち向かうためには、「早期発見・原因分析・適切な対応」をワンセットで行う体制が不可欠です。
以下では、企業が風評被害に対して講じるべき具体的な対応策を、3つのステップに分けて紹介します。
ネット上の異変を「早期に検知」する
まず重要なのが、悪評や中傷が拡散する前に「兆候」をいち早く察知する仕組みを持つことです。
- SNSや掲示板で企業名が急増していないか
- ネガティブな文脈での言及が増えていないか
- Googleサジェストに悪いワードが出ていないか
上記を継続的にチェックすることで、炎上・風評の予兆を把握し、対応のタイミングを逃さないようにします。
一般的には、Web/SNSモニタリングツールや、検索エンジンにおけるサジェスト表示の監視が行われています。
発信源・被害範囲を「可視化・分析」する
次に必要なのが、拡散された情報の出どころ(発信者)や、被害の範囲を明確にすることです。
- デマの出どころはどこか
- どの媒体で、誰が、どのように拡散しているのか
- 誰がどれだけ影響を受けているのか
このような「状況の全体像」を把握しないと、正しい対策は打てません。
専門的な分析ツールや、必要に応じてデジタルフォレンジック調査などを活用して、証拠の収集や発信元の特定を行うケースもあります。
ネット上の悪評を「抑制・修復」する
最後に重要なのが、すでに拡散されてしまった悪評への対応です。
- 記事削除依頼や非表示措置の交渉
- 誤情報の否定や公式声明の発信
- 検索結果・サジェストの最適化
- 「正しい情報」の発信強化
こうした対応により、企業イメージの修復と再拡散の防止を図ります。検索エンジン対策(サジェスト対策・検索結果最適化)や、セキュリティ体制の見直しを並行して行うことで、再発防止にもつながります。
このように、風評被害のリスクを本質的に抑えるには、「予兆検知」→「被害分析」→「回復施策」の3段階を、継続的かつ一貫して行う体制づくりが重要です。
社内体制で完結することが難しい場合は、外部の専門機関と連携しながら、網羅的なリスク対策を講じることが求められます。
風評被害対策に「CYBER VALUE」が選ばれる理由
根拠のない悪評は、企業の信頼を静かに、確実にむしばんでいきます。
だからこそ、企業は攻めのリスク対策を今すぐ始める必要があります。
では、数ある風評被害対策の中でも、なぜ「CYBER VALUE」が選ばれているのでしょうか?
その理由を、3つの強みに分けてご紹介します。
モニタリングから削除交渉・再発防止までワンストップ対応
CYBER VALUEでは、風評被害の「発見」から「対応」「予防」までを、ひとつの窓口で完結できます。
- SNSや掲示板、検索結果などの常時監視
- ネガティブ情報の発信者特定や証拠保全
- 検索結果・サジェストの最適化
- 弁護士との連携による削除交渉
- セキュリティ診断を通じた再発防止策の提案
上記のような各フェーズに最適な専門対応を、スピーディに実行可能です。
▶関連サービス:
Web/SNSモニタリング|風評被害対策|フォレンジック調査・対策
大手から中堅・中小企業まで幅広い支援実績
「CYBER VALUE」は、上場企業・大手企業から中堅・中小企業、医療法人や学校法人まで、多様な業種・規模のクライアントを支援してきた実績があります。
- リスクに不慣れな企業でも安心のサポート体制
- 業界特性に応じたカスタマイズ対応
- 実例に基づいたアドバイスと提案力
このような点も、選ばれる大きな理由です。
「何から始めればいいかわからない」「まず相談だけしたい」という企業でも、初期診断から丁寧に対応しています。
技術力+法務対応で“実効性”を追求
単なる監視ツールやSEO施策にとどまらず、CYBER VALUEは
- 専門技術を活用した解析・対応
- 弁護士連携による法的措置の準備
- 検索アルゴリズムやSNSの仕様に基づいた施策提案
上記のような「見える効果」にこだわった支援を行っています。
風評被害は「感情」ではなく「仕組み」で広がります。
だからこそ、技術と法律の両輪で根本から対策することが重要です。
まとめ|まずは現状のリスクを知ることからはじめませんか?
企業にとって、ネット上の悪評は見えにくく、しかし確実に広がる火種です。
「事実ではないから大丈夫」「うちはまだ被害がない」-そう思っている企業ほど、対応が遅れてしまいます。
CYBER VALUEでは、無料の初期診断や資料請求にも対応しています。
まずは現状のリスクを知ることから、風評被害対策の第一歩を踏み出してみませんか?